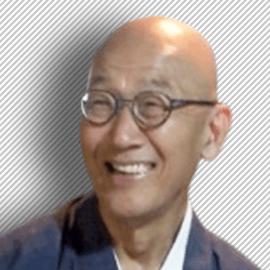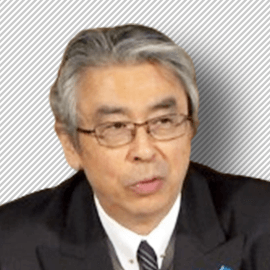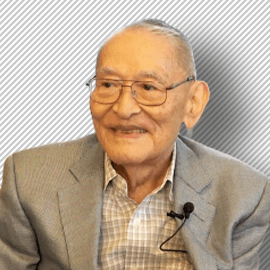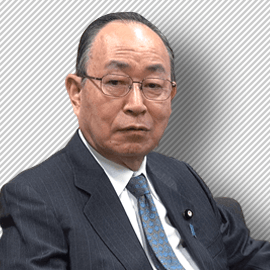大統領への権力集中がアメリカ本来の形?…完全な歴史歪曲
第2次トランプ政権の危険性と本質(6)歪曲された「本来のアメリカ」
ヘリテージ財団が打ち出す「単一執行府論」は、大統領に権力を集中させることが「本来のアメリカ」の姿だと謳う。就任以来、歴史的に類を見ない異常な数の大統領令を発出しているトランプ政権を支えるその思想は、「権力の分散...
収録日:2025/04/07
追加日:2025/06/14
厳格な道徳、そして権利よりも義務を重んずる思想
民主主義を考えるための十二の根本原理(11)アメリカ清教徒の思想
民主主義社会の全ての根源は、アメリカの清教徒社会にある。当時のアメリカをひと言でいえば、「厳格な道徳と、権利よりも義務を重んずる思想」が社会を覆っていた。それをわかりやすく書いたのが、ナサニエル・ホーソンの小説...
収録日:2025/01/16
追加日:2025/05/23
宇宙帝国主義――トランプ2.0の最重要アジェンダの正体
トランプ2.0~アメリカ第一主義の逆襲(3)トランプ2.0のゴールと日米関係
トランプ第2次政権のゴールは、アメリカの「ゴールデンエイジ(黄金時代)」を築くことである。そこでは、究極的なフロンティアとしての宇宙の覇権を取ることや、西半球の欧州との外交が重要視されることを意味する。いったいど...
収録日:2025/03/21
追加日:2025/05/03
米国史の教訓…ドル基軸通貨体制の信認を問う大転換に?
株価と歴史…トランプ関税の影響を読む(1)アメリカ史の教訓とは
トランプ関税の影響は、今後、どのように広がっていくのだろうか? 過去の大きな構造変化や金融環境の変化が各国の「株価リターン」にどのような影響を与えたのかを分析しつつ、今後を考えるヒントがないかを検証していく。第1...
収録日:2025/04/18
追加日:2025/05/02
危機の10年…2つのサイクルが初交差する2020年代の意味
トランプ2.0~アメリカ第一主義の逆襲(2)交差する2つのサイクル
アメリカには、80年周期の制度サイクルと50年周期の社会経済サイクルがあり、その2つの周期が初めて重なるのが2020年代なのだ。「危機の10年」ともいわれており、そのタイミングで始動したトランプ第二次政権。その動きの舵取り...
収録日:2025/03/21
追加日:2025/04/26
100年ぶりのアメリカ第一主義とトランプ新政権3つの焦点
トランプ2.0~アメリカ第一主義の逆襲(1)アメリカ第一主義の歴史
トランプ第2次政権が本格的に始動したアメリカ。トランプが掲げる「アメリカ第一主義(アメリカファースト)」とはなにか。それは100年ぶりともなる「フロンティアの再定義」であり、「地球からの撤退宣言」なのだという。いっ...
収録日:2025/03/21
追加日:2025/04/19
この30年で結果が出てるのにアメリカの真似してはいけない
米国論(8)もう結果は出ている
アメリカ全体が分裂に分裂を重ねている。どの部分と付き合うかで、アメリカ観は全く違ってくる。これはある意味、民主主義国家とは逆で、むしろかつてのソ連や今の北朝鮮などと同じである。また、人間の考える知恵には限界があ...
収録日:2024/10/22
追加日:2025/02/14
移民が多くなれば国が潰れる…民主党の政策をみればわかる
米国論(5)アメリカは一つではない
アメリカと一口で言っても、さまざまな様相のアメリカがあるが、アメリカがよかったのは1960年代前半までである。例えば民主党の移民政策をみればわかるが、あれは国を潰しかねない愚策だ。それがわからないのが金融資本主義の...
収録日:2024/10/22
追加日:2025/01/24
日本はアメリカの真似をやらないほうがいい
米国論(4)1930年代のアメリカは理想郷
「全ては自己責任」と国民全てが考えていた1930年代のアメリカこそ理想郷とも言うべき最高の時代にあった。そんなアメリカと戦争した日本は愚かであったのかもしれない。しかも、日本人は外交下手で、やる気がない、という大欠...
収録日:2024/10/22
追加日:2025/01/17
トランプ大統領就任!アメリカ理解のポイントとは?
編集部ラジオ2025(1)誰かに教えたくなるアメリカ論
いうまでもなく、アメリカは日本にとって、きわめて重要な国です。しかし、そのアメリカについて、日本人は、本当に正しく理解できているのでしょうか。日本について無理解な外国人のあり方を「フジヤマ、ゲイシャ」などという...
収録日:2024/12/17
追加日:2025/01/14
自発性を重んじる――藤田一照師が禅と仏教の心を説く
禅とは何か~禅と仏教の心(1)アメリカの禅と日本の禅
大学院を中退して禅の道に進み、アメリカ東海岸で18年間禅堂を開いた藤田一照師に、禅と仏教の心について話を聞いていく。アメリカの禅にはすでに百年近い歴史があり、最初に鈴木大拙が伝えたといわれている。その後、一時はカ...
収録日:2024/08/09
追加日:2025/01/13
次の時代は絶対にアメリカだ…私費で渡米した原敬の真骨頂
今求められるリーダー像とは(3)原敬と松下幸之助…成功の要点
猛獣型リーダーの典型として、ジェネラリスト原敬を忘れてはならない。ジャーナリスト、官僚、実業家、政治家として、いずれも目覚ましい実績を上げた彼の人生は「賊軍」出身というレッテルから始まった。世界を見る目を養い、...
収録日:2024/09/26
追加日:2024/11/20
理想主義的か利己主義的か…アメリカ史から考える孤立主義
アメリカの理念と本質(10)二つの孤立主義と30年周期説
孤立主義の中には「理想主義的な孤立主義」と「利己主義的な孤立主義」がある。これはしっかり区別しなければいけないが、アメリカの歴史の文脈でいえば、本当は「理想主義の孤立主義」なのだと中西氏は言う。実際にアメリカは...
収録日:2024/06/14
追加日:2024/10/22
起源は南北戦争…アメリカ再建への道とリンカーンの演説
アメリカの理念と本質(9)南北戦争の意義とリンカーンの理念
アメリカには共和主義と自由主義が並立している。共和党と民主党の二大政党は、それを象徴する存在である。しかし南北戦争の前は、国家主義がフロンティア精神を誘発し、権力者が弱者をないがしろにしていた。南北戦争はアメリ...
収録日:2024/06/14
追加日:2024/10/15
いまだ残る「馬車の時代」の制度…アメリカ最大の課題とは
アメリカの理念と本質(8)連邦と州の問題
独立宣言と独立戦争を経てアメリカ合衆国を構成したのは13の植民地だった。入植の経緯も文化もバラバラな13の州は、当時それぞれ独立した国として機能していたため、国家間の条約として「アメリカ合衆国憲法」を起草する。その...
収録日:2024/06/14
追加日:2024/10/08
ウォルター・ラッセル・ミード提唱「四つのアメリカ」とは
アメリカの理念と本質(7)四つのアメリカ
日本人のアメリカ理解を促すのに役に立つのが「四つのアメリカ」である。これはアメリカ外交史の泰斗といえるウォルター・ラッセル・ミード氏が提唱するもので、第一は「ピューリタンのアメリカ」、第二に「バージニアのアメリ...
収録日:2024/06/14
追加日:2024/10/01
「アメリカ・ファースト」と通底するアメリカの帝国観
アメリカの理念と本質(6)帝国としてのアメリカ
アメリカ合衆国建国の父は、アメリカ合衆国独立宣言またはアメリカ合衆国憲法に署名した政治的指導者、また愛国者たちを指導してアメリカ独立戦争に関わった人々を指す。彼らの頭にあったアメリカの国家像、その原型は古代ロー...
収録日:2024/06/14
追加日:2024/09/24
『風と共に去りぬ』で表現されたアイルランド移民の精神史
アメリカの理念と本質(5)アメリカのアイルランド問題
アイルランド本国で始まったアングロ・サクソンからの差別は大西洋を越えても消えず、逆にアメリカへ移民するアイルランド人たちに不撓不屈の精神を植え付けた。名作『風と共に去りぬ』には、その姿がビビッドに描かれている。...
収録日:2024/06/14
追加日:2024/09/17
カトリックでも例外!? アイルランドに対する偏見とその背景
アメリカの理念と本質(4)アングロ・サクソンの社会
ヨーロッパのカトリック社会では人と人のつながりを大切にするが、プロテスタントの国々では個人主義がより先鋭に主張される。中でもアングロ・サクソンの社会に冷たさを感じた日本人留学生はイギリスに留学した夏目漱石をはじ...
収録日:2024/06/14
追加日:2024/09/10
ピューリタンの2つの柱と3つの人生哲学とは
アメリカの理念と本質(3)ピューリタンの特性と影響
ピューリタンは「聖書を信じろ」という柱と、「予定説」という考え方にもとづき「勤勉を尊ぶ」という柱で支えられている。そこから「謹厳、勤勉、謙虚」という人生哲学が生まれ、富の蓄積を尊ぶ倫理が資本主義の精神を産んでい...
収録日:2024/06/14
追加日:2024/09/03
ピューリタニズムとは?アメリカ建国の核とその歴史に迫る
アメリカの理念と本質(2)ピューリタニズムの歴史
アメリカの本質を知るにはキリスト教の中でも特殊なピューリタニズムを理解する必要がある。アメリカ建国の礎をなしたアングロ・サクソンはイギリスで迫害から逃れたピューリタンであり、新しい土地で理想国家をつくろうとする...
収録日:2024/06/14
追加日:2024/08/27
三つの建国――その歴史的背景から迫るアメリカの原点
アメリカの理念と本質(1)西洋文明の行き着いた先と三つの建国
「日本の近代を語るとき、アメリカという存在を抜きにしては全く本質が見えてこない」と中西氏は言う。しかし、日本にとって死活的に重要な存在である国にもかかわらず、アメリカがどんな国か、アメリカの原点は何なのかという...
収録日:2024/06/14
追加日:2024/08/20
アメリカは日本の意見を求めている…きちんと旗を立てよ
「同盟の真髄」と日米関係の行方(8)(質疑)アメリカは日米同盟を捨てるか?
アメリカでは日本との同盟関係についてどのように考えているのか。そこでポイントとなるのは、日本の対中政策である。軍事的な緊張が増している今般の世界情勢の中で、日米の信頼関係を維持するために重要なのは、中国に対して...
収録日:2024/04/23
追加日:2024/07/31
2016年、2020年の米大統領選の各州の結果はどう違ったか?
「同盟の真髄」と日米関係の行方(6)アメリカ大統領選挙を占う3つの州
2024年11月に控えたアメリカ大統領選挙。激戦が予想されるが、大統領選挙には、その鍵を握る3つの州がある。それはどういうことなのか。アメリカ大統領選挙の仕組みを詳細に語る。(全8話中第6話)
収録日:2024/04/23
追加日:2024/07/17
世界の紛争…アメリカの空母機動部隊は3正面で戦えるのか
「同盟の真髄」と日米関係の行方(1)日本を占う3つの選挙と軍事作戦
2024年は日本にとって重要な選挙が3つある。それは1月に行われた台湾総統選、4月の韓国総選挙、そして11月のアメリカ大統領選である。これらの選挙結果は、ロシア・ウクライナの戦争や、ガザ地区での紛争が収束の気配を見せない...
収録日:2024/04/23
追加日:2024/06/12
どうなるアメリカ大統領選…多極化時代の潮流を読む
グローバル・サウスは世界をどう変えるか(7)世界システムの変容と多極化
第2次世界大戦後、圧倒的な経済力でアメリカ中心の国際秩序が形成された。しかし、変動相場制移行や冷戦終結などでパクス・アメリカーナが終焉すると、その後はグローバリゼーションが世界を覆っていった。そして近年、グローバ...
収録日:2024/02/14
追加日:2024/05/15
なぜアメリカはロシア、中国より圧倒的に地理的優位なのか
地政学入門 歴史と理論編(3)地政学でみたアメリカ・ロシア・中国
国や地域がどこに位置するかという普遍的な要素から、国際政治の歴史や情勢を分析する地政学。今回はアメリカ、ロシア、中国という3つの大国を例にとり、地図を俯瞰しながらどのような分析が可能になるかを具体的に見ていく。ラ...
収録日:2024/03/27
追加日:2024/05/14
なぜソ連は崩壊したか?…新冷戦とアメリカへの恐怖心
歴史から考える「ロシアの戦略」(5)冷戦の時代とソ連解体
キューバ危機以降、アメリカを警戒しながらも核兵器の開発などにより一定の地位を築いたソ連。冷戦構造の中で社会主義国を牽引していたソ連だが、1980年代以降、その足場は崩れ出す。社会的背景や疑心暗鬼が生んだ悪手をひも解...
収録日:2024/01/18
追加日:2024/03/18
トランプ政治で加速する分極化…2024年大統領選の行方
加速する「アメリカの政治的分極化」と今後の可能性
政治的分極化が進んでいるアメリカ。特に共和党内での分裂が顕著で、2023年10月には下院議長選挙が大混乱した。この背景にはイデオロギー的、感情的な分極化がある。トランプ政権以降、分極化が加速すると、中道が失われて両極...
収録日:2023/12/21
追加日:2024/02/20
労働市場が硬直的な日本…転職率はアメリカの4分の1以下
衰退途上国ニッポン~その急所と勝機(5)3つの「メガトレンドの変化」
流動的な労働市場というと、日本では「解雇しやすくなる」「首を切られる」といったマイナス面として捉えられる。だが実は、流動的な労働市場のほうが労働者にとってプラスなのである。どういうことなのか。実は今、日本は3つの...
収録日:2023/06/30
追加日:2023/11/28
アメリカの一流大学でMBAの学位を取得する3つの意義
経済と社会の本質を見抜く(5)MBAをアメリカで取得する意義
経済政策や企業経営に携わる人間にとって、いまや欠かせない学位となっているのが「MBA(経営学修士)」だ。日本国内でも取得可能な学位だが、アメリカの一流大学でのMBA取得にはとくに重要な意義があるようだ。AIなどの技術革...
収録日:2023/08/09
追加日:2023/11/26
デカップリングへ突き進むアメリカの半導体支配戦略
半導体から見る明日の世界(5)バイデン政権の半導体戦略
米中対立による半導体戦争は今後さらに激化すると考えられるが、最先端技術の頭脳部分では圧倒的にアメリカが優位に立つ。ただし、半導体の新戦略をアメリカ国内で推進していくためには、それ相応の問題も立ちはだかる。今回の...
収録日:2023/07/14
追加日:2023/09/25
CHIPS法成立!半導体支配を目論むアメリカの2つの理由
半導体から見る明日の世界(4)米国「CHIPS法」成立と中国の脅威
5G通信で先行した中国に対して、アメリカは情報ネットワークの脅威に直面した。中国への危機意識は、トランプ政権からバイデン政権に代わってもますます強まっている。そこでバイデン大統領は「CHIPS法」といわれている半導体製...
収録日:2023/07/14
追加日:2023/09/18
河合栄次郎、石橋湛山、ルーズベルト…日米自由主義者の主張
日本人が知らない自由主義の歴史~前編(6)日本とアメリカのニューリベラリズム
「ニューリベラリズム」は日本やアメリカにも影響を与えていった。日本では河合栄次郎や石橋湛山が紹介に努めることになる。アメリカでは、大恐慌で市場経済への信頼が失墜したことが決定的となり、「ニューリベラリズム=リベ...
収録日:2022/07/01
追加日:2023/05/23
「2027年・台湾有事」説が飛び交った背景
台湾有事を考える(3)アメリカの対中戦略と台湾有事の可能性
日本の防衛費が大幅に増額したことは、それほど日本の周辺環境が危険な状態になっていることを示している。それは、中国の軍事費の驚異的な伸びによって東アジアにおける米軍優位が崩壊しているからだ。これが台湾有事の可能性...
収録日:2022/12/19
追加日:2023/02/06
法の支配があるから自由がある…信仰の自由と政治の基本
「アメリカの教会」でわかる米国の本質(5)成文憲法・自由・人権・法の支配
植民地だったアメリカは、イングランド国王から独立するため、政府をつくり大統領を立てて独立戦争に臨んだ。そこで必要になったのがアメリカの基本的な考え方を書いた契約書で、それが成文憲法である。そこには条件があり、一...
収録日:2022/11/04
追加日:2023/02/03
橋爪大三郎先生の「アメリカの教会」解説で米国がわかる!
編集部ラジオ2023:2月1日(水)
名講義をコンパクトにお伝えする、編集部ラジオの「要約シリーズ」。ぜひ講義のチョイスや、学びの予習、復習にもお役立てください。
今回は、橋爪大三郎先生の《「アメリカの教会」でわかる米国の本質》を、スライド資料つ...
収録日:2023/01/17
追加日:2023/02/01
知っておくべきアメリカの5つのキリスト教宗派の特徴は?
「アメリカの教会」でわかる米国の本質(4)「5つの宗派」紹介
アメリカの教会には主だった宗派が30、諸派を合わせると約1000ものキリスト教信仰が存在する。今回ではその宗派の中から、イングランド国教会、会衆派、クエーカー、メソディスト、バプティストの5つについて紹介していく。アメ...
収録日:2022/11/04
追加日:2023/01/27
「回心」「覚醒」…アメリカを突き動かす「信仰復興の波」
「アメリカの教会」でわかる米国の本質(3)回心と覚醒
アメリカにおけるキリスト教社会の歴史は「回心」が重要視された。さらに宗教的「覚醒」が大規模に巻き起こる“信仰復興の波”が幾度も起こり、アメリカ社会を大きく動かしていったという。では、「回心」や「覚醒」とは、どのよ...
収録日:2022/11/04
追加日:2023/01/20
カトリックとプロテスタントの違いは?「救済予定説」とは?
「アメリカの教会」でわかる米国の本質(2)プロテスタントと「予定説」
日本人の中には、そもそもカトリックとプロテスタントの「一番の違い」がどこかも、よくわからない人が多い。さらに「誰が救われて、誰が救われないのかは、予め神様が決めている」という、プロテスタント(特にカルヴァン派)...
収録日:2022/11/04
追加日:2023/01/13
「キリスト教は知らない」ではアメリカ市民はつとまらない
「アメリカの教会」でわかる米国の本質(1)アメリカはそもそも分断社会
アメリカが日本の運命を左右する国であることは、安全保障を考えても、経済を考えても、否定する人は少ないだろう。だが、そのような国であるにもかかわらず、日本人は、本当に「アメリカ」のことを理解できているだろうか。日...
収録日:2022/11/04
追加日:2023/01/06
日本の武士も古き良きアメリカ人も、すべて自己責任だった
作用と反作用について…人間と戦争(8)すべては自己責任
今の日本の間違いは、弱い人を中心にしていることである。学校も、勉強ができる人ではなく、できない人に合わせている。また、外国で活躍しているある日本人女性が「昔の、あの偉そうなおじさんは、どこにいったの?」とインタ...
収録日:2022/05/19
追加日:2022/08/19
新しい脱グローバル化の時代へ、鍵は「知恵の賢明な外交」
グローバリズムの“終わりの始まり”(3)アメリカと中国の覇権競争の帰趨は決した
現在このタイミングでウクライナの戦争が起こったことが、グローバリズムの転換点として非常に重要な意味を持つ。21世紀の米中覇権競争を経て、世界の構図はどのように移り変わっていくのだろうか。そして、日本がなすべきこと...
収録日:2022/05/30
追加日:2022/07/29
アメリカの「ベタ下り」がプーチンの蛮行の根拠となった!?
ウクライナ戦争に揺らぐ国際秩序(3)日本の立ち位置とアメリカの責任
ウクライナに対する一方的な戦争に反発し、日本や欧米諸国はロシアに対して厳しい経済・金融制裁を科している。しかし、ロシアの軍事侵攻は止まる気配がなく、制裁が十分に機能しているとはいえない。国際社会はなぜプーチンを...
収録日:2022/04/01
追加日:2022/05/13
アメリカのエネルギーを作り出している神話のせめぎ合い
古事記・日本書紀と世界神話の類似(6)神話とアメリカの関係
われわれはなぜ類似するほど神話を持つ必要があるのだろうか。神話がわれわれに伝えようとしたメッセージ、与えた影響など、人類が世界各地で神話を持ち続けてきた意味を、アメリカという世界と神話の関係から読み解く。(全10...
収録日:2021/09/29
追加日:2022/04/24
アメリカを「舐められた獅子」に貶めるロシア、中国、イラン
ロシアのウクライナ侵攻と中国、イラン(2)米国の誤認
ウクライナ危機は、今、バイデン大統領のウクライナに対する戦略の貧しさだけではなく、実はそれを通して対イラン戦略の欠陥を露呈させる鏡にもなっていると山内昌之氏は語る。アメリカのバイデン政権は、明らかにロシアの思惑...
収録日:2022/02/15
追加日:2022/03/13
アメリカが経済安全保障として進める6つの管理強化とは
米中戦略的競争時代のアジアと日本(4)アメリカの安全保障戦略
中国の脅威が高まる中で、米中の覇権争いは激化している。2017年にトランプ政権の下で出された「国家安全保障戦略」や、2019年に施行した「国防授権法」から、アメリカが中国の戦略をどのように理解しているのか、そしてそれを...
収録日:2021/11/24
追加日:2022/03/02
トヨタから学んだ重要な戦略要素は「時間」の概念
シリコンバレー物語~IT巨人の実像と今後(6)トヨタ方式に学ぶアメリカ
アメリカはトヨタの「カイゼン」や「カンバン」方式に学び、研究を進めてきた。その最初の一歩はトヨタが再生させたGMの工場視察である。彼らはこれをケーススタディとするだけでなく、普遍化し、一般的に通用する理論を導き出...
収録日:2021/07/08
追加日:2021/12/26
アフガンで起こった現代の「風声鶴唳」、その真相に迫る
不安定化したアフガン、ウイグル、中国(1)アメリカ軍の撤退とアフガンの混迷
20年にわたる駐留を終え、2021年8月にアメリカ軍がアフガニスタンから撤退した。それをきっかけとして、武装勢力タリバンがあっという間に首都カーブルを制圧し、政権を復活させた。これまでアメリカを始めとする国際社会から多...
収録日:2021/11/12
追加日:2021/12/18
バイデン政権は今後、民主主義のレジリエンスを示せるのか
バイデンの政治とアメリカの民主主義(4)民主主義の灯台になれるのか
新型コロナウイルスの感染者数・死者数ともに世界一を記録しているアメリカだが、経済回復に向けて、バイデン政権の手腕が問われている。これから、人種差別問題や所得格差、政治的分断を乗り越え、失われつつあるアメリカ民主...
収録日:2021/07/07
追加日:2021/10/12
小さな政府からの転換?アメリカの政府と市場の関係は?
バイデンの政治とアメリカの民主主義(3)「大きな政府」を目指すバイデン
小さな政府による市場経済を進めてきたアメリカだが、所得格差や気候変動の問題が顕著になっており、バイデン政権のもとで「大きな政府」への転換に舵を切っている。そこで問われているのは政府と市場の関係だ。バイデン政権に...
収録日:2021/07/07
追加日:2021/10/05
『ヒルビリー・エレジー』に読む白人労働者の不満と絶望
バイデンの政治とアメリカの民主主義(2)バイデン大統領の経歴と試練
歴代最高齢の米大統領ジョー・バイデン氏は、実は大変な苦労人でもある。幼少期には吃音に悩まされ、また29歳で上院議員に当選した直後、交通事故で妻と娘を失ったが、そうした悲劇、逆境を乗り越えていったことが、現在の彼の...
収録日:2021/07/07
追加日:2021/09/28
10分でわかる「バイデン政権」
バイデンの政治とアメリカの民主主義(1)バイデン政権の特徴
2020年のアメリカ大統領選挙において、民主党のジョー・バイデン氏が共和党のトランプ氏に勝利し、史上最高齢ながら第46代大統領に就任した。政治的分断が深まる中、中道派を貫くバイデン政権の特徴について解説する。(全4話中...
収録日:2021/07/07
追加日:2021/09/07
日本とアメリカのベンチャーキャピタルはどう違うのか
「研究開発型ベンチャー」成功の条件(2)動機とスピード
日本でもベンチャー企業の数や投資額は急速に増えている。しかし、欧米と比較すると、その市場規模はまだまだ小さい。アメリカのシリコンバレーやボストンのような、有名スタートアップ地区を生み出すにはどうしたらいいのか。...
収録日:2021/05/12
追加日:2021/08/21
百年前のトランプ?…ハーディング大統領と狂騒の20年代
米国史から日本が学ぶべきもの(4)アメリカの「もう一つの顔」
第一次世界大戦後、ウィルソンに代わって政権を担ったのは共和党のウォレン・ハーディングであった。「常態への復帰」を掲げて、民主党のコックスに大差をつけて当選した彼の政策には、トランプ政権との類似性が多く見られる。...
収録日:2021/05/21
追加日:2021/07/03
中国を新たな標的としたアメリカ帝国主義時代の始まり
米国史から日本が学ぶべきもの(3)産業革命と帝国主義の始まり
南北戦争後のアメリカは、移民労働力を基盤に世界有数の工業国へと変貌する。この飛躍的な発展を可能にしたのは、アメリカ大陸の東部と西部を結ぶ大陸横断鉄道の開通であった。19世紀以降のアメリカは帝国主義段階へと入り、そ...
収録日:2021/05/21
追加日:2021/07/03
南北戦争は奴隷解放のためではなく利害の対立
米国史から日本が学ぶべきもの(2)アメリカの起源と南北戦争
イギリスの北米植民地であったプリマスとジェームズタウン。その後、一気に13州にまで領地を拡大し、アメリカ独立運動へと発展する。しかし、領土拡大につれて、基幹産業や連邦制のあり方の違いから南北の対立が激化し、ついに...
収録日:2021/05/21
追加日:2021/07/03
アメリカの全体像をつかむ上で理解すべき「いくつもの顔」
米国史から日本が学ぶべきもの(1)アメリカ社会の複雑性
1960年の「日米安保条約」の締結により、アメリカは日本で唯一の同盟国となった。しかし、われわれは本当にアメリカを理解しているといえるのか。戦前日本の3人の知米家と当時のアメリカ大統領の特徴から、アメリカ社会が持つ複...
収録日:2021/05/21
追加日:2021/07/03
湾岸戦争以来のアメリカ一国主義時代が終わろうとしている
対中国戦略・日本の決定的な決断(5)アメリカの真の姿
バイデン政権の誕生に伴い、親中路線への方向転換があるのではないかといったことなど、日本国内ではさまざまな危惧がささやかれた。なぜ国内世論はしばしばアメリカの出方を間違えてしまうのだろうか。中西氏によれば、バイデ...
収録日:2021/04/23
追加日:2021/06/16
博物館や回想録を通じて、日本も戦争当時の教訓を思い出す必要がある
戦時徴用船の悲劇と大洋丸捜索(6)アメリカの潜水艦
日本の船が戦った当時のアメリカの潜水艦に目を移すと、多くの船が沈没していることがわかる。当時の米海軍の名将・ニミッツの生家近くには、太平洋戦争を記念する博物館がある。ニミッツの回想録は、モノを作ることは得意だが...
収録日:2020/02/28
追加日:2021/06/12
「日本防衛」を誓約したアメリカが懸念する経済安保問題
対中国戦略・日本の決定的な決断(4)対中国包囲網分断の可能性と経済安保
今後の中国が「連衡策」を外交戦略の主軸に据えるとすれば、日本が注意すべきなのは、中国相手に目先の利を追い、「抜け駆け」による利益相反者との分断を起こすことだ。先般、中国企業による出資を受け、経済安保問題が浮上し...
収録日:2021/04/23
追加日:2021/06/09
米中間での「股裂き状態」、日本は二者択一を迫られるのか
2021年米中関係と日本外交の針路を読む(4)【質疑編】アメリカか中国か、難しい選択
米中関係は今後、どんな展開を見せるのだろうか。「トゥキディデスの罠」という話が出ているように、パワーバランスが変わるときは戦争が起こる可能性があるということで、米中もその罠に陥るのは何としても避けないといけない...
収録日:2021/04/20
追加日:2021/05/15
アメリカの排日運動に「国民外交」で挑んだ渋沢栄一の努力
曾孫が語る渋沢栄一の真実(6)日本とアメリカにかける橋
渋沢栄一の事績として日米親善事業は欠かせない。栄一はあくまで民間の立場を守りつつ、「世界の中の日本」の位置を正確に弁える人だった。アメリカ人実業家とは特に深く親交を結び、青淵文庫に招くことも多かったが、時代の波...
収録日:2020/10/14
追加日:2021/03/08
バイデンの勝利とトランプの抵抗の経過を追う
2021年激変する世界と日本の針路(2)アメリカ大統領選と新大統領選出
世界中をゆさぶる大変動があった2020年、アメリカでは大統領選挙が行われた。トランプ氏とバイデン氏による熾烈な選挙戦が繰り広げられたが、選挙人投票でバイデン氏の勝利が確定。それを認めないトランプ支持者は2021年1月、議...
収録日:2021/02/02
追加日:2021/02/20
中国とアメリカでダイナミズムを生んでいる理由
日本企業の弱点と人材不足の克服へ(8)日本でダイナミズムを生むために
中国の驚異的な経済発展は、中国が「大国」であることが大きい。大国の強みはアメリカのシリコンバレーを見ても分かる。シリコンバレーには政府から多額のお金が落ちているが、一方で無政府主義者も多い。相容れない2つが共存し...
収録日:2020/10/28
追加日:2021/02/14
日本にとってアメリカの停滞期は対米ディールのチャンス
米国史サイクル~歴史の逆襲と2020年代(4)日米関係と米国史サイクル
日米関係を理解する上で米国史サイクルは非常に重要な示唆を与えてくれる。アメリカの停滞期に日米関係を再構築するチャンスが訪れるが、それに失敗すると転換期のアメリカに見捨てられて、日本は大きな不利益を被る。ハーディ...
収録日:2020/07/29
追加日:2021/02/10
アメリカ建国以来初、2つの停滞期が重なる危機の2020年代
米国史サイクル~歴史の逆襲と2020年代(2)2つのサイクルと危機の時代
制度サイクルとは異なる社会経済サイクルもアメリカの歴史を理解する上で重要である。社会経済サイクルは50年周期で循環するが、制度サイクル同様、2020年代は停滞期に当たる。中でも特に2020年から25年にかけては、アメリカの...
収録日:2020/07/29
追加日:2021/01/27
アメリカ史上80年ごとの制度サイクルを生んだ3つの戦争とは
米国史サイクル~歴史の逆襲と2020年代(1)3つの制度サイクルと戦争
アメリカは歴史上、約80年ごとに制度サイクルが交代する。第一のサイクルは1787年から1865年までのフロンティア時代制度、第二のサイクルは1865年から1945年までの工業化時代制度、そして第三のサイクルは1945年から今日まで続...
収録日:2020/07/29
追加日:2021/01/20
アントレプレナーシップはアメリカ精神そのもの
“アメリカとは何か”~米国論再考Vol.2(4)深掘り編:アメリカ精神と今後
東秀敏氏によれば、アメリカの外交方針は短期的な視点で決定されているために、転換のペースが早い。これに対応するためには、歴史感覚を学ぶことやアメリカ国民との接触の中で知識を蓄えることが必要となる。本講義終了後の質...
収録日:2020/06/11
追加日:2020/12/05
歴代大統領の外交方針とは異なるトランプ的取引主義
“アメリカとは何か”~米国論再考Vol.2(3)アメリカ外交の4パターン
アメリカ外交は、歴代大統領の外交方針から4つのパターンに分類することができる。外国に対する姿勢と関心度という2つの軸によって、これまでの大統領の外交がそのいずれかに当てはまるのだが、トランプ政権の外交は、相手国に...
収録日:2020/06/11
追加日:2020/11/28
2016年トランプ当選につながる孤立主義復興の契機を追う
“アメリカとは何か”~米国論再考Vol.2(2)太平洋を越えて中国へと至る
アメリカの西漸運動は中西部を開拓し、やがてテキサスやカリフォルニアといった地域まで併合し、太平洋まで到達した。その後、アメリカは奴隷解放後の新たな労働力確保のために、中国市場に進出することを目論む。第一次世界大...
収録日:2020/06/11
追加日:2020/11/22
“アメリカ”という概念の覚醒は欧州での7年戦争に起因する
“アメリカとは何か”~米国論再考Vol.2(1)アメリカの源流と地理
アメリカという国を理解するためには、その広大な土地をどのように開拓してきたのかを正しく知る必要がある、と東秀敏氏は強調する。アメリカの基礎は、英国系移民によって形成された。地理的な特徴を理解した上で、西部へと開...
収録日:2020/06/11
追加日:2020/11/22
「日本の武士道」で「アメリカ民主主義」の裏打ちをする
李登輝に学ぶリーダーの神髄(4)「脱古改新」という考え方
2004年頃から李登輝は「脱古改新」という言葉を用いた。これは、「脱中国」「一国二制度の否定」をも意味する。彼の死後、遺族は総統府や蔡英文総統に「『脱古改新』を誠実に守ってくれ」と伝えた。李登輝がいなければ、台湾は...
収録日:2020/08/24
追加日:2020/11/18
中国の「国家資本主義・大国意識・強権」を許せぬアメリカ
米中貿易摩擦の核心と展望(2)なぜ利害が衝突するのか
そもそも、なぜ中国は世界への輸出を増やせたのか? 1つの理由として、中国が「途上国ステータス」を享受できたことがあった。たとえば、先進国は関税率を低くしているが、中国は高い関税で国内産業を守ってきた。また、日本...
収録日:2020/10/27
追加日:2020/11/06
トランプはアメリカ停滞期の大統領…日本は判断ミスに注意!
“アメリカとは何か”~米国論再考Vol.1(3)テクノロジーの限界と可能性
アメリカという国を設計したのは、独立宣言と米国憲法だった。歴史を持たないアメリカは、世界史上初めて政治哲学のみに頼った人工的な政体をつくり上げた。これは一種の発明であったが、発明には限界点があり、その度にアメリ...
収録日:2020/06/11
追加日:2020/11/05
1ドル紙幣のシンボルに秘められたアメリカの建国理念とは
“アメリカとは何か”~米国論再考Vol.1(2)国章に込められた意味
アメリカの建国の高尚な精神を後世に残すために、建国の父たちは国章にその理念を余すところなく残した。平和を希求する市民による国家であることと自由を守るためなら暴力も構わないという強い意志を示す国章と、創造主によ...
収録日:2020/06/11
追加日:2020/10/29
トランプ氏が共和党を乗っ取るか?移民問題や格差での分極化
日本人が知らないアメリカ政治のしくみ(5)分極化と米中関係への影響
トランプ政権誕生以前からアメリカやヨーロッパの政治を見守ってきた人びとにとって、ポピュリズムの蔓延と分極化の進行は世界的な課題である。アイデンティティ・ポリティクスや移民問題、アメリカの対中国外交は、今後どのよ...
収録日:2020/08/27
追加日:2020/10/28
アメリカとは革命を基礎とした「発明」である
“アメリカとは何か”~米国論再考Vol.1(1)アメリカという発明
日本ではしばしばアメリカが誤解されている。アメリカは終わらない実験と発明によって成立している国であり、それが繰り返されていく。よってアメリカの歴史は、その両方に極端にぶれる、いわばローラーコースターのようなもの...
収録日:2020/06/11
追加日:2020/10/22
シンクタンクを使わないトランプ政権の特異性
日本人が知らないアメリカ政治のしくみ(4)シンクタンクとポピュリズム
アメリカには多くの傑出したシンクタンクが存在して、他国では官僚機構の行う業務を補完している。ただ、トランプ政権の場合はもともと反エスタブリッシュメントを旨とし、そのことがポピュリスト的人気につながっていると考え...
収録日:2020/08/27
追加日:2020/10/21
清教徒的なキリスト教原理主義がわからないと理解できない
Qanonとは何か?(3)Qanonとアメリカ史のディープな関係
実は、Qanonのような「陰謀論」は、アメリカ史においては特別なものではないという。そもそも、独立戦争への機運が高まったのも、「英国王ジョージ3世がアメリカ植民地の入植者全員を奴隷にしようとしている」というフェイク...
収録日:2020/10/07
追加日:2020/10/18
対中関与政策終了で中国依存のリスク回避を進めるアメリカ
米中関係の行方と日本の今後を読む(6)アメリカの模索する道
戦狼化する中国外交に対し、アメリカは「対中関与政策」終了を告げ、デカップリングを進めている。だが、国民の生活に根付いた中国依存を拭い去ることは容易ではなく、中国を顧客とする企業活動にもさまざまな軋轢が起こってい...
収録日:2020/09/08
追加日:2020/10/17
ホワイトハウスは「アメリカ最大のロビイスト事務所」
日本人が知らないアメリカ政治のしくみ(3)議会の実態とホワイトハウスの動き
教科書で見るアメリカ政治と実際の姿は相当違う。議員提出法案が基本とはいえ、半分ほどは役所起源だという。一方、大統領起源のものもある。オバマケア法案がそうで、オバマ氏が民主党議員に猛烈に働きかけ、修正と否決を繰り...
収録日:2020/08/27
追加日:2020/10/14
銃社会のアメリカと監視社会の中国、問われる国家の安全
米中関係の行方と日本の今後を読む(3)主権か治安か、監視か銃か
コロナによる複合危機の中、問われているのは社会や国家の安全をどう考え評価するかということだ。それは為政者のみならず市民一人一人が考えるべき問題である。銃を持つことは権利でもあればリスクでもあり、監視され管理され...
収録日:2020/09/08
追加日:2020/10/10
定年のないアメリカの最高裁判事、大統領が選ぶ時に大論争
日本人が知らないアメリカ政治のしくみ(2)最高裁判所と連邦制
アメリカの議員は党議拘束に縛られないが、「院内総務」と呼ばれる人びとに尻を叩かれて投票を行っている。最高裁の判事は終身制で、大統領よりもその任期は長くなることが多い。さらに連邦制を取るアメリカでは、州が強い権限...
収録日:2020/08/27
追加日:2020/10/07
「ポイント・オブ・ノー・リターン」を通り過ぎた米中関係
歴史から見た中国と世界の関係(4)対中戦略の大転換を図るアメリカ
2008年のリーマンショックで、15兆元もの大々的な景気対策を行った中国をアメリカは「世界経済の救世主」と持ち上げ、「世界の繁栄と安定のためのパートナー」とさえ思うようになる。オバマ政権までそうした流れできたが、トラ...
収録日:2020/08/21
追加日:2020/10/05
アメリカの過ちは冷戦の勝利で中国に幻想を抱いたこと
歴史から見た中国と世界の関係(3)戦後の中国に夢を抱いたアメリカ
第二次世界大戦での国民党の態度に幻滅したアメリカは、清廉潔白な共産党こそ民主主義の担い手という新たな夢を見る。ところが国民党との戦いに勝利した共産党政権はソ連に接近し、アメリカは中国を徹底的に敵対視する。その後...
収録日:2020/08/21
追加日:2020/10/05
権限の少ないアメリカ大統領は政治をどう動かしているのか
日本人が知らないアメリカ政治のしくみ(1)アメリカの大統領権限
アメリカ政治には、日本人から見ると不明な点が多い。大統領の権限はほぼ拒否権だけに限られていて、予算編成の力も立法権もない。立法の要は議会だが、ねじれ国会や分裂政府に悩み、最近では妥協案をつくる柔軟性に欠けてきた...
収録日:2020/08/27
追加日:2020/09/30
コロナを逆手に取ってアメリカを悪者にするイランの強かさ
イスラム世界におけるコロナ問題(3)アメリカ批判のイラン外交と政府の責任
イランのハーメニー最高指導者は、感染拡大はアメリカによる医療テロが原因だと発言している。確かに、アメリカの数々の制裁がイランの外貨獲得を困難にし、医療崩壊を招いたことは否めない。しかし、感染拡大の根本的な原因は...
収録日:2020/08/04
追加日:2020/09/26
ハーディングとトランプがつくり出したのは別のアメリカ
ハーディングとトランプ~100年前の米大統領選を読む(5)新たなスタイルの政治家
ハーディングの特異性はいくつかの特徴によって語られる。後ろ盾を持たないことをよく理解していたため、エリート内でも対立を避け、共和党の重鎮からの信頼を勝ち取った。また、ビジネスの経験や縁故主義によって強く結束した...
収録日:2020/06/11
追加日:2020/09/17
あのまま存命なら「原・ハーディング」ディールの可能性も
ハーディングとトランプ~100年前の米大統領選を読む(4)新世界としてのアメリカ
およそ100年前のアメリカの大転換は、大英帝国的な国際協調主義を取るウィルソン大統領の姿勢に反発し、ヨーロッパとは異なるアメリカという自己意識を追求する人々に呼応する形で生まれた。この転換は、現代アメリカの姿勢にも...
収録日:2020/06/11
追加日:2020/09/10
世界的大変化の潮流からコロナパンデミック後の世界を考える
コロナパンデミックと闘う世界と今後の課題(9)アメリカ中心の戦後体制の変化
コロナパンデミックの影響を考えるにあたって、それ以前の国際状況の変化を正しく認識する必要がある。そこには大変化の潮流が4つあり、一つ目は、アメリカを中心とした戦後の政治経済体制が揺らぎつつあるということである。か...
収録日:2020/07/16
追加日:2020/09/02
世界最悪の感染拡大が進むアメリカの状況を確認する
コロナパンデミックと闘う世界と今後の課題(3)経済活動再開と第二波
コロナウイルス対策としての活動制限が各国の経済に与えた打撃は深刻だったため、各国政府は感染拡大が落ち着いてくると迅速に経済活動の再開に尽力した。しかし、その結果再度コロナウイルスの感染拡大が広まりつつあり、感染...
収録日:2020/07/16
追加日:2020/08/28
1920年のアメリカファースト…ハーディング大統領の勝利
ハーディングとトランプ~100年前の米大統領選を読む(1)米国第一主義の台頭
ポスト冷戦期のグローバリズムの流れに対して「アメリカファースト」を強く打ち出したドナルド・トランプ氏。だが、1920年の大統領選挙を制したハーディングも、アメリカファーストを掲げて勝利していた。第1次世界大戦前から続...
収録日:2020/06/11
追加日:2020/08/13
バンドワゴン現象も発生、トランプ大統領の発言で市場大混乱
コロナ禍で揺れる世界経済の行方(6)トランプ発言とアメリカの悲劇
新型コロナの感染は迅速で週ごとに様相を変えるが、6月前半の時点で世界最大の被害を被ったのはアメリカである。先進国のトップを走るアメリカが、なぜそんな事態になったのか。すでに多方面から能力不足が指摘されているトラン...
収録日:2020/06/15
追加日:2020/07/14
日本が進むべき道は、アメリカか中国かの二択ではない
激動の世界情勢を読む~米中対立の行方(9)アメリカと中国の間の日本
アメリカがこれまでのような国際秩序の維持から撤退していくという動きを見せる一方、中国は経済発展こそ遂げたが、いろいろと問題を抱えていることも事実。そんななか、アメリカと中国の間で、日本はいかなる態度を取るべきな...
収録日:2020/02/15
追加日:2020/04/03
スノーデン氏によって明らかになったアメリカ諜報機関の真相
米中ハイテク覇権戦争(7)「諜報戦略」と「強国化戦略」
ここまで中国の諜報、情報収集の脅威に関するアメリカの警戒に関して議論してきたが、アメリカの諜報活動も決して明るみにできるものではないことが内部告発によって示された。自国の諜報活動を制限したくないアメリカは、直接...
収録日:2019/11/20
追加日:2020/02/22
ファーウェイは本当にアメリカへの深刻な脅威なのか
米中ハイテク覇権戦争(5)5Gと中国脅威論:前編
デジタル技術がわれわれの生活を急速に変化させつつある現代社会において、次世代ネットワークである5Gの開発にはファーウェイが大きく貢献している。中国の政治体制を考慮すると、ファーウェイによって開発された技術が、中国...
収録日:2019/11/20
追加日:2020/02/08
中国型とアメリカ型グローバル化の衝突が米中貿易摩擦の真相
グローバル化のトリレンマ(2)米中問題とデカップリング
グローバル社会において唯一、国家主権を打ち出しながら成長してきたのが中国だろう。20年間で貿易を10倍に拡大した中国は、それゆえアメリカに代表される西欧社会との軋轢を生じている。米中貿易摩擦は、単なる関税の問題より...
収録日:2019/10/31
追加日:2019/12/18
『ヒルビリー・エレジー』が示す私たちの知らないアメリカ
アンチ・グローバリズムの行方を読む(2)アメリカの闇
アメリカは、もはやこれまでにはない新しい時代に入っている。特に中西部の白人男女を中心とする大衆の悲痛な叫びが、東部のインテリやリベラル派への反感とともに、トランプ支持の強力な地盤をつくっていった。他方でその根底...
収録日:2019/11/07
追加日:2019/12/07
アメリカ国内では北朝鮮よりイランのほうが関心が高い
北朝鮮の脅威と日本の国益(8)米・中・韓の駆け引き
北朝鮮の韓国への駆け引きは、米韓関係を引き裂き得る踏み絵のようなものである。現状では国連制裁に抵触するために経済的援助はできないが、今後のアメリカ、中国、韓国の出方次第では一気に情勢が変化し、融和方向にも緊張方...
収録日:2019/08/21
追加日:2019/11/10