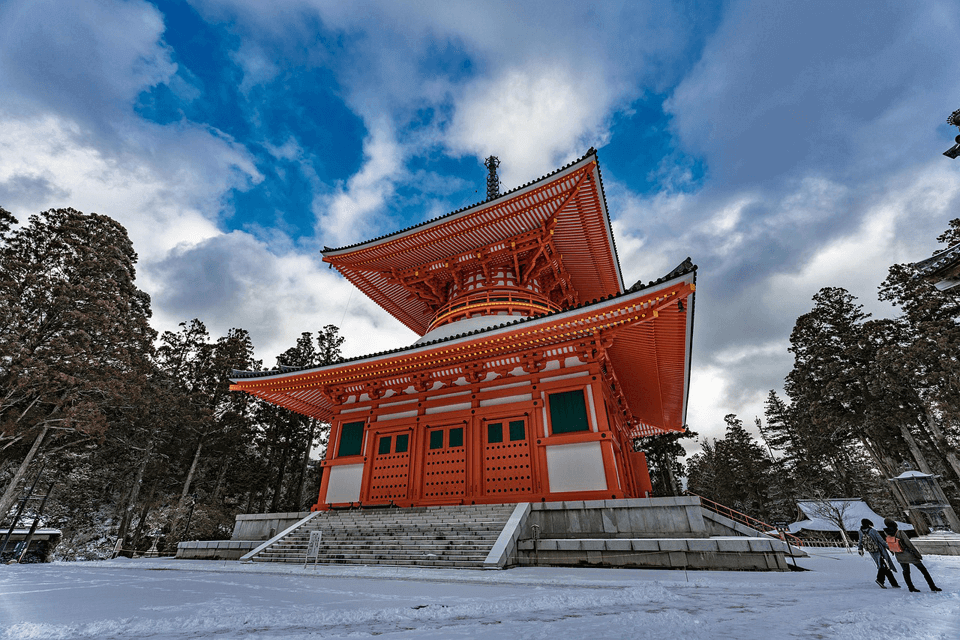●あらゆる教えを集大成して段階を分けた『十住心論』
―― では、次の文章にいきたいと思います。第1話でも少しお話の出た『十住心論』ですが、これはどういう書物になるのでしょうか。
賴住 『十住心論』は、空海の主著といっていいと思います。先ほど少し申し上げたように、世界のあらゆる教えや人間のあり方などを集大成して、最終的にそれが真言密教の立場の中で包み込まれていく。そのようなことを空海自身が言っていますので、非常に体系的な書物であるといわれています。
―― 以下の10項目を挙げていただいていますが、この10個はそれぞれどういうものですか。
賴住 まず、「異生羝羊心(いしょうていようしん)」とありますが、これは人間の一番原形のようなものです。「善悪の道理に暗く、煩悩のままに生きる段階」と書きましたが、まだ人間が人間になっていない動物のような段階で、何がいい・悪いというものも分からず、欲望のまま、煩悩のままに生活している段階ということです。
―― ということは、これは一番低い段階だという位置づけですね。
賴住 そうですね。一番低い出発点ということになります。
●動物から童へと進んでいく「非・仏教」の階梯
賴住 その後が「愚童持斎心」ということで、だんだん人間らしくなっていきます。よく倫理の立場ということを言いますが、世の中のルールがだんだん分かり、何がいいのか悪いのかが分かってきます。それにより、こうしなければいけない、ああしなければいけないということができてくる段階。仏教的な立場からいえば、人間の本来持っている仏性(仏の本質)が少しずつ花開いてきた最初の段階ということで、少し人間らしくなった段階です。
ただ、倫理の立場については全部で10個あるうちの2番目ということで、空海の立場からは非常に初歩的と考えられているわけです。
―― なるほど。現代に生きるわれわれは、もしかするとせいぜいこの段階のような感じかもしれないですね。
賴住 そうですね。本当になかなか1、2の段階から抜けられないということもあります。
―― 抜けられない。さらに8つあるわけですけれども、3番目はどういうところでございましょうか。
賴住 3番目は「嬰童無畏心(ようどうむいしん)」といいます。これは人間界の苦を逃れ、天上界に憧れて安心立命を求...