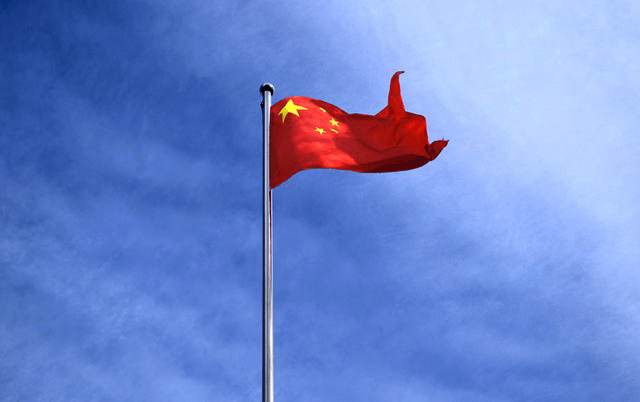●ウクライナ侵攻の動向を中国がどう見ているかを考える
―― 翻って考えた場合に、われわれの身近な東アジアがどうなるかという問題もあります。特に最近、台湾危機などもかなり危険なのではないかという情報も出たりしております。このウクライナの侵攻があった後で、台湾問題(台湾海峡の問題)がどうなったかという部分についてはどういう変化が起きたと思われますか。
小原 世界的にいろいろな影響があったと思うのです。皆さんもご承知の通り、この戦争を止められなかったと。なぜ止められなかったのかと。これは戦争の前から想定はされていたことなのですけれども、国連が機能しなかったのです。国連安保理ではロシアは常任理事国ですから、拒否権を使えば決議は通らないわけです。もちろん総会で決議は通りましたけれども、総会には強制力はないわけです。
要するに、国連が動かない。ではどうするのだと、例えば経済制裁をします。しかし、その経済制裁というのは、今、世界の相互依存が高まってくる中で、諸刃の剣のようなことになるわけです。
つまり、ヨーロッパがロシアからのエネルギーの輸入を止めてしまうことによって、その収入が戦争に使われることを防ごうとします。しかし、その結果、エネルギー危機がヨーロッパに起こるわけです。よく、両者の相互依存はwin-winだから戦争を防げるというのですけども、一旦こういう状態になるとlose-loseになるわけです。
他方でロシアの場合には、中国やインド(との関係がポイント)です。特にインドもQUADの一員なのですけれども、どうしても国益というものを皆、考えます。成熟していない国際社会の中では、例えばインドは安い石油が入るのであれば、それを買いましょうとなる。もともと伝統的には、インドとロシアは非常に深い関係があります。
このように、ヨーロッパではエネルギー危機に陥ってでも(ロシアの)制裁をしないといけない、(ロシアからの)エネルギーの輸入をできる限り止めるということをやっている、その他方で、国やインド、あるいはそれ以外の途上国では、(石油が)安くなったからどんどん買おうということになってきています。よって、経済制裁もなかなか当初の効果は上がらないのです。
片やアメリカは、ウクライナに対して、NATOに入っていないわけですから軍の派遣はしないということを前々から言っていたわけです。こ...