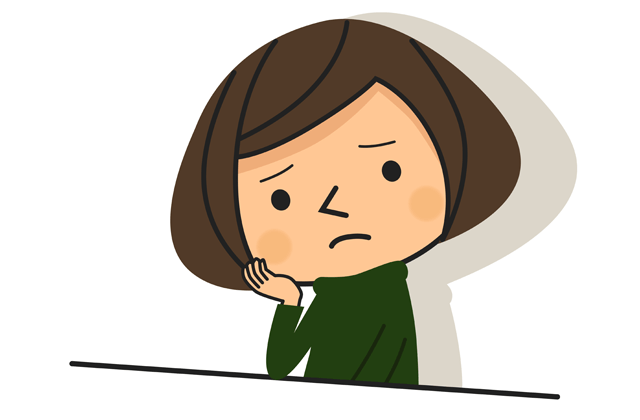
「うつ病」とは何か?―『新・臨床心理学事典』を活用する―
世界のうつ病患者3億人、全人口の約4%に
東京新聞(2017年2月24日)によると、世界保健機関(WHO)は、世界でうつ病に苦しむ人が2015年に推計3億2200万人に上ったと発表しました。これは、世界の全人口の約4%に当たり、05年から約18%増加したとのことです。そのうち、日本は約506万人。国内総人口の約4%に当たり、世界とほぼ同じ水準にあると言えます。なお、厚生労働省によると、うつ病など気分障害で医療機関を受診している人は約112万人(14年)ですが、WHOの統計は専門家による推計値のため、医師にうつ病と診断された人以外も含んでいます。これについてはさまざまな意見があるかと思いますが、少なくともWHOはこの状況について警鐘を鳴らしています。ところで、「うつ病」がそもそもどういう病気のことなのか、ご存知でしょうか。昨今、「うつ病」という言葉はかなり一般化してきたといえますが、それと同時に誤用や誤認も増えてきているようです。そこで、あらためて「うつ病」とは何か、考えてみましょう。
あらためて、「うつ病」とは何か
『新・臨床心理学事典』(石川勇一著、コスモス・ライブラリー)によると、うつ病とは、感情の「振れ幅が極端になり、制御できなくなる気分障害」とあり、そのキッカケは、人間関係のストレス、過酷な労働、結婚・出産、生理、季節の変化など、さまざまであるということです。また、うつ病の原因は不明の場合も多く、うつになりやすい「病前性格」というものもあります。その特徴は、まじめ、几帳面、勤勉、律儀、責任感が強い、などです。そのため、仕事場で評価が高く、周囲からの信頼の厚い人がうつ病にかかることも少なくありません。具体的には、
(1) 気分が沈んで憂鬱である
(2) 興味や喜びが著しく減退した
(3) 食欲の減退または増加がある
(4) 不眠または過眠である
(5) 心に焦燥感や制止がある
(6) 疲労感や気力の減退がある
(7) 無価値観や不適切な罪責感がある
(8) 思考力や集中力の減退、または決断困難がある
(9) 死について繰り返し考えたり、自殺を企てたりする
のうち、(1)か(2)のどちらかが当てはまり、9つの症状のうち5つ以上が2週間にわたってほとんど毎日あり、苦痛によって生活に支障を来していて、他の疾患によるうつ病ではない場合は、「DSM-5」ではうつ病と診断されます。「DSM-5」とは、米国精神医学会作成の精神科診断統計マニュアルのことで、日本で最も広く用いられている心の病を特定するための診断基準です。
病院に行くと、ほとんどの場合は薬物療法が行われ、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)と呼ばれる一群の抗うつ薬を投与されます。SSRIは60~70%の有効性があると言われていますが、薬物療法は50%ほどの頻度で再発するので、心理療法の併用もしばしば必要とされます。
心理療法では、ストレスの強い環境を改善すること、性格傾向を改善すること(「いい加減」を覚える)、歪んだ否定的な認知を改善すること(適切なものの受け取り方を覚える)、生きがいを発見することなどが主題になることが多いそうです。
『新・臨床心理学事典』を活用する
あらためて調べてみると、「うつ病」の実相がだんだんと見えてきました。一言でいえば、日本において「うつ病」は「DSM-5」の基準に沿って決まるということです。「うつ病」についても、「DSM-5」についても、『新・臨床心理学事典』を典拠としました。『新・臨床心理学事典』は記述が、細やかで、分かりやすく、テーマは広範多岐にわたります。サブタイトル「心の諸問題・治療と修養法・霊性」とあるように、心のさまざまな問題や治療法から仏教思想まで幅広くカバーしており、アカデミックな心理学に関心がある人はもちろん、心の癒しや成長に興味を持っている人も、質の良い知識を得ることができる一冊です。通読して学ぶことも、また事典として活用することもできます。
最後に、周囲にうつ病者がいる場合の対応の仕方についても簡単にご紹介します。本書によると、原則として「励まさないこと」が重要です。なぜかというと、「うつの人はすでに自分で自分を限界まで追い込んだり、自責の念に駆られている場合が多い」ため、「励ましてさらに頑張らせると、逆に追い詰めることになりかねません」とのことです。また、否定したり、過度なアドバイスも控えたほうが良いそうです。支えるのは簡単なことではありませんが、ともかく聞き役になって相手が「受け入れてもらえている」と感じられるようにすることが大切です。
『新・臨床心理学事典』の著者・石川勇一氏は相模女子大学人間社会学部の教授で臨床心理士です。自他ともにうつ病の疑いがあるときは、ひとりで抱え込まず、なるべく早い段階で、石川氏のようなプロのカウンセラーや専門医に相談することです。
<参考文献>
『新・臨床心理学事典』(石川勇一著、発行:コスモス・ライブラリー、発売:星雲社)
http://www.kosmos-lby.com/books/shosai159.html
<関連サイト>
石川勇一氏の研究室ホームページ
http://www.sagami-wu.ac.jp/ishikawa/
『新・臨床心理学事典』(石川勇一著、発行:コスモス・ライブラリー、発売:星雲社)
http://www.kosmos-lby.com/books/shosai159.html
<関連サイト>
石川勇一氏の研究室ホームページ
http://www.sagami-wu.ac.jp/ishikawa/
人気の講義ランキングTOP20
欧州では不人気…木村資生の中立説とダーウィンとの違い
長谷川眞理子







