テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
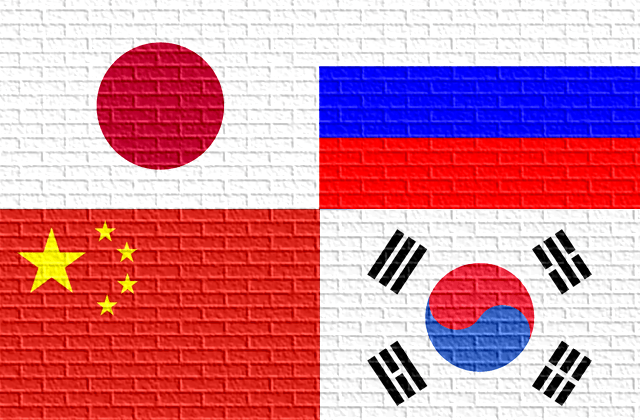
「逆さ地図」にみる日露中韓の宿命的な関係
所変われば、地図も変わる
世界の日々のニュースを見聞きするなかで、地図で国や地域を確認するといった場合、その地図は当然、日本が真ん中に位置して左に韓国、中国、ユーラシア大陸、海を挟んで右に南北アメリカ大陸、といった形をとっていると思います。私たちにとって、これが「世界地図」と思ってしまいがちですが、たとえば、ヨーロッパで使われているのはイギリスが中心にくる地図で、日本はうんと右端に位置しています。欧州から見れば日本はまさに「極東」、「Far East」なのだな、と実感します。一方、アメリカで一般的なのはもちろんアメリカが中心で、日本はぐっと左に寄せられて、アメリカとヨーロッパの近さが際立って見えてきます。南半球の国々では、上下さかさまでオーストラリアが上になっている地図、とよく聞きますが、これはどちらかというと観光客のおみやげ用といったところ。実用として使われているのは、北半球が上、南半球が下、と普段私たちが見慣れている地図と同じだそうです。いずれにしても、「所変われば地図も変わる」と言えそうです。
視点ががらりと変わる「逆さ地図」
世の中にはまだまだ変わった地図があるもので、その中の一つに富山県が国土交通省国土地理院の承認を得て作成した「環日本海・東アジア諸国図」(通称・逆さ地図)なるものがあります。これはその名が示すとおり、東西南北を逆さにして中国や朝鮮半島、ロシアといった大陸から日本を見た、従来の日本人の視点を文字通り逆さまにしたような地図で、大陸を覆うように左に北海道、右に九州・沖縄と日本列島が細長く横たわっています。ノンフィクション作家として数多くの著書があり、そしてジャーナリスト、評論家としても活躍する石川好氏は、この逆さ地図には日本と大陸との宿命的な関係が凝縮されていると語ります。「逆さにすると随分と見え方が変わってくるな、おもしろいな」、だけでは済まないというわけです。
外海進出を阻む日本は「邪魔な国」
近代以降、交易が盛んになってくる中で、中国も韓国もロシアも外海進出を狙っていたわけですが、逆さ地図を見ると日本がこれらの国が海へ出て行くのを阻んでいるのがよく分かります。ロシアは不凍港を手にしつつ、日本海、日本を越えてさらにその先の海に出て行くことを戦略としていました。広大な大陸中国からすれば、目の前に広がる黄海、東シナ海はごく狭いもので、自由に動ける範囲は限られてしまいます。彼らにとっても、沖縄、南西諸島、台湾、フィリピンとつながる南の海は、手中に収めたいものでした。これらの国々にとって、日本はいわば、ずっと「邪魔な国」であり続けてきたのです。通商上、どうしても進出したい道をさえぎる国・日本は、中国、韓国、ロシアにとっては目の上のたんこぶ以外の何ものでもありません。だからこそ、ロシアは日露戦争と第二次世界大戦末期に、強引に日本に入ろうとしてきました。一方、日本は中国と日清戦争、十五年戦争で激しく衝突し、朝鮮半島との対立も深めました。隣国でありながら、利害が全く相反する国・日本とロシア・中国・韓国の戦いは、地政学上から見ても避けられない、宿命的なものであったのです。
日本は自国の位置をもっと意識するべき
逆さ地図が見せる日本とこれらの国々の宿命的な位置関係は、実質的な戦争が終わった現代でも続いています。ロシアが北方四島を日本に返還しないのは、ここを手放してしまってはロシアが自由に太平洋に出て行けないからであり、また、中国が尖閣諸島の領有権を主張するのは、ここが外海に出て行くための出入り口であるからです。政治、経済、あらゆる面で、日本は国際社会の一員として世界各国と関係を築いていかなければなりませんが、この日本の位置、大陸との位置関係はどうにも変えようがありません。私たちは、大事な隣人とつき合っていく中で、常にこの逆さ地図をイメージしながら議論・対話を重ね、問題解決に向かっていくべきなのだ、と石川氏は語ります。
日本の位置というものを意識・理解するという意味では、学校の歴史や地理の授業でこの逆さ地図を使って、日本と諸外国の関係を俯瞰してみる、ということも必要かもしれません。
人気の講義ランキングTOP20










