テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
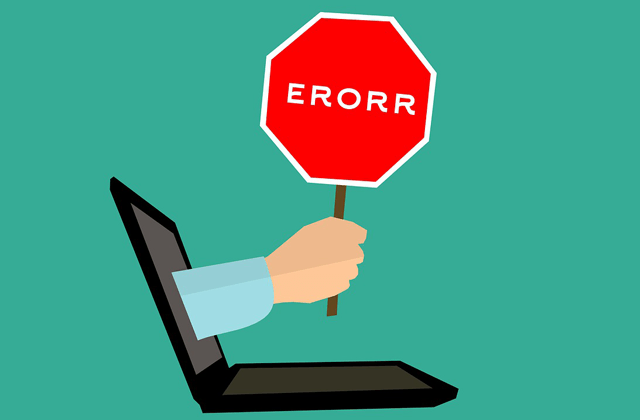
「エラーを減らす」より「良い仕事をする」べき
「エラーを減らす」より「良い仕事をする」
鉄道、バス、飛行機などの事故や情報漏えいによるトラブルなど、その多くはヒューマンエラー、つまり人為的ミス、過失が原因となっているようです。ヒューマンエラーによる事故が起きた場合、会社としては社員に対する厳重注意、現場での徹底指導に動き、そのためには完璧なチェックリストやマニュアルが必要だと考えるのが一般的でしょう。しかし、これが企業が陥る落とし穴なのだと慶應義塾大学理工学部管理工学科教授・岡田有策氏は言います。岡田氏によれば、ヒューマンエラー防止対応策の本質は、「エラーを減らす」ではなく「いかに良い仕事をするか。仕事の質を上げるか」にあるとのこと。つまり、それはれっきとした成長戦略の一部になり得るのです。
100点の仕事ができたなどと勘違いしないこと
生じた事故に対して、一つ一つ絆創膏を貼るように対処しても、根本解決にはならないのは自明のこと。まず手をつけるべきなのは、それぞれがどのように行動するべきだったのかを洗いだし、現場の作業や指示系統のあり方を改善していくことだと心得なければなりません。そのためには、常に「自分の仕事はよくてせいぜい95点。100点ということはあり得ない」という意識を持つことだと岡田氏は言います。そもそも、マニュアル通りに行動しても、100点の仕事にはなりません。マニュアルを信奉し、「この通りにやっているから自分の仕事は100点だ」という勘違いがエラーの元凶。このような考えでは、同僚や上司の意見も耳に入ってきません。
頑張ってせいぜい70点、80点、すべてうまくいっても95点。この足りない部分をどう埋められるかを分析し、自分の仕事を少しずつでも改善しようとする。そして、その結果をきちんと周りに評価してもらう。改善点をクリアしたら今度はそのレベルを「95点」とみなして、さらに良い仕事に高めようとする。この姿勢がヒューマンエラー防止の本質です。仕事する人の努力とそれを適正に見る管理職の評価能力が、企業の仕事の質を上げていくことで、企業全体の成長を促すのです。
「安全とは何か」を明確に定義する
このような企業体質にするためには、会社として「安全とは何か」をきちんと定義することも重要になってくる、と岡田氏は続けます。いくら過去の失敗例、事故の事例を参照して対応策を練っても、それだけでは前例のない、あるいは前例を超える「想定外」の事態になった場合、無策になってしまう危険がつきまといます。そこで、前提条件として、自社にとっての安全とは何かをきちんと定義することが求められるのですが、それはすなわちお客さまに安心をもたらすことにつながります。ここで気をつけなければいけないのは、「お客さまに安心をもたらす」ということは、お客さまの「利用したい、買いたい」という顧客満足度を上げるのとは、別物だということ。「利用したくない、買いたくない、二度と行きたくない」といった不安要素、その原因を解明し、徹底して取り除く。これが第一なのです。
鉄道のような公共サービス、病院などを思い浮かべれば分かりやすいかもしれません。あの電車が定刻通りに目的地に着いた、あるいはあの病院で病気が治ったからといって、その時点では有難いと感じても、理由もなくまた「あの電車に乗りたい」「あの病院に行きたい」ということにはならないでしょう。重要なのは、利用してもらうときにいかに不安な思いをさせないかであり、それが利用者の信頼に結実していくのです。
「エラー error」とは、「さまよう、放浪する」を意味するラテン語errareが語源だといいます。会社がどのような安心をどれほど顧客にもたらすことができるのか。そのためにはどのように仕事の質を上げていけばよいのかをきちんと分析し定義するのが肝要。膨大なマニュアルやチェックリスト項目の間をさまよっているようでは、ヒューマンエラーには対応できず、企業の成長もあり得ないということなのです。
人気の講義ランキングTOP20










