テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
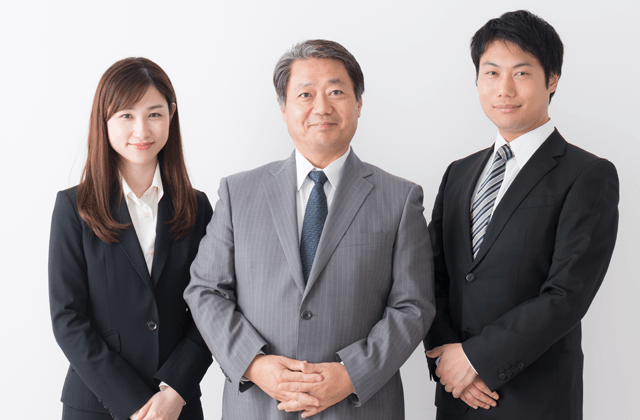
やはり「中途」と「新卒」で扱いは違うのか?
働き方改革の追い風を受けて、日本型の終身雇用・年功序列制度は、今や風前の灯火となっています。しかし一方で、大学生の就活は新卒一括定期採用に向けて、従来通りに進行中。このズレに、違和感を抱く方も多いのではないでしょうか。雇用システムが崩壊しつつある今もなお「新卒」と「中途採用」による差はあるのかどうか、調べてみました。
「新卒」採用のメリットは、社会人1年生で何の「色」もついていない学生の中から、自社に関心を持つ優秀な人材を集められること。彼らの「可能性」を伸ばし、将来の幹部候補に育てていくことが、企業の新卒採用目的です。また、定期採用により企業全体の年齢構成も調整でき、長期・中期のスケジュール管理をしやすいこともあります。
逆に「新卒」であることのデメリットは、選考プロセスに長い時間がかかり、即戦力としてはまったくアテにできないこと。さらに教育コストもかさみ、就労体験がないため、配属先でミスマッチを起こすこともしばしばあります。景気によって、新卒を採用できる時期とできない時期があることにより、優秀な人材を取りこぼすのも痛しかゆしです。
「中途採用」であることのデメリットは、以前のやり方、前職での進め方にこだわる人が多いこと。さらには、よそから転職してきた人なので「いずれまた、この会社からも転職するのではないか」という可能性も考えられます。スキルのある人を雇ってしまうと、その分若い世代を育てる余裕がなくなるという人もいます。
つまり、「新卒」の給与は〝将来の可能性〟に、「中途採用」の給与は〝現在のスキル〟に対して支払われるという違いがあるのです。収入は、採用された時点でのスキルが高ければ、中途採用者が新卒者を上回る場合もしばしばありますが、そこからの伸び率はあまり期待できません。企業の状況が変わっていくにつれ、未知のポジションへ配置してみようとするのは、新卒が先になります。つまり、出世に関しても、新卒採用された人のほうが期待できるということです。
社内の「風通しの良さ」「相互尊重」「評価適正」、いずれの面でも新卒社員が働きやすさを感じている。これは、転職・就職のための情報プラットフォーム「Vorkers」による調査結果です(同サイトに投稿された20歳から54歳までの約7万5929人の在籍企業の評価レポートから比較)。
年代別にみると、「風通しの良さ」と「社員の相互尊重」では、20~24歳を除くすべての年齢層で、新卒社員の感じる「風通しの良さ」や「相互尊重(チームワーク)」が中途社員を上回りました。「人事評価の適正感」については、20~29歳で中途社員が新卒社員を上回っていますが、30代からは逆転。とくに35~39歳の世代では、新卒2.94ポイント、中途2.75ポイントと大きな差がついています。
また、すべての項目を通じて、新卒社員は年齢が上がるにつれて「自社の良さ」を評価する率が上がり、どんどん「会社大好き人間」になっているのに対し、中途社員からの会社評価は年齢につれて下がる傾向があります。若いうちは感じなかった「不公平」が、歳を経るにつれて積み上がってくるのでしょうか。
新卒のメリット・デメリットを採用する側から考える
「新卒」と「中途採用」の待遇の差を見るには、採用する企業側の事情を考える必要があります。企業にとって、「新卒採用」と「中途採用」のメリット・デメリットを、どうバランスを取っているのか。それを知れば、待遇の差にも自ずと思い当たるはずです。「新卒」採用のメリットは、社会人1年生で何の「色」もついていない学生の中から、自社に関心を持つ優秀な人材を集められること。彼らの「可能性」を伸ばし、将来の幹部候補に育てていくことが、企業の新卒採用目的です。また、定期採用により企業全体の年齢構成も調整でき、長期・中期のスケジュール管理をしやすいこともあります。
逆に「新卒」であることのデメリットは、選考プロセスに長い時間がかかり、即戦力としてはまったくアテにできないこと。さらに教育コストもかさみ、就労体験がないため、配属先でミスマッチを起こすこともしばしばあります。景気によって、新卒を採用できる時期とできない時期があることにより、優秀な人材を取りこぼすのも痛しかゆしです。
中途採用のメリット・デメリットは?
企業が「中途採用」で人を雇い入れるのは、欠員補充や新規事業開拓のためです。求められる人、すなわち中途採用のメリットは、即戦力であることが第一。それに伴い、研修コストが抑えられ、採用にかかる時間も短くて済みます。さらに、中途採用の社員は、自社にはない外部からの知識やノウハウ、社風の改善案などを持ち込んでくれる存在としても注目されます。「中途採用」であることのデメリットは、以前のやり方、前職での進め方にこだわる人が多いこと。さらには、よそから転職してきた人なので「いずれまた、この会社からも転職するのではないか」という可能性も考えられます。スキルのある人を雇ってしまうと、その分若い世代を育てる余裕がなくなるという人もいます。
つまり、「新卒」の給与は〝将来の可能性〟に、「中途採用」の給与は〝現在のスキル〟に対して支払われるという違いがあるのです。収入は、採用された時点でのスキルが高ければ、中途採用者が新卒者を上回る場合もしばしばありますが、そこからの伸び率はあまり期待できません。企業の状況が変わっていくにつれ、未知のポジションへ配置してみようとするのは、新卒が先になります。つまり、出世に関しても、新卒採用された人のほうが期待できるということです。
在職期間につれて「会社大好き度」がアップする新卒組
では、実際に中途入社した社員たちが、新卒組との差をどう感じているのか、アンケートを見てみましょう。社内の「風通しの良さ」「相互尊重」「評価適正」、いずれの面でも新卒社員が働きやすさを感じている。これは、転職・就職のための情報プラットフォーム「Vorkers」による調査結果です(同サイトに投稿された20歳から54歳までの約7万5929人の在籍企業の評価レポートから比較)。
年代別にみると、「風通しの良さ」と「社員の相互尊重」では、20~24歳を除くすべての年齢層で、新卒社員の感じる「風通しの良さ」や「相互尊重(チームワーク)」が中途社員を上回りました。「人事評価の適正感」については、20~29歳で中途社員が新卒社員を上回っていますが、30代からは逆転。とくに35~39歳の世代では、新卒2.94ポイント、中途2.75ポイントと大きな差がついています。
また、すべての項目を通じて、新卒社員は年齢が上がるにつれて「自社の良さ」を評価する率が上がり、どんどん「会社大好き人間」になっているのに対し、中途社員からの会社評価は年齢につれて下がる傾向があります。若いうちは感じなかった「不公平」が、歳を経るにつれて積み上がってくるのでしょうか。
<参考サイト>
・VORKERS:「新卒入社」vs「中途入社」働きやすさギャップに関する調査レポート
https://www.vorkers.com/hatarakigai/vol_6
・VORKERS:「新卒入社」vs「中途入社」働きやすさギャップに関する調査レポート
https://www.vorkers.com/hatarakigai/vol_6
人気の講義ランキングTOP20
2025年のテンミニッツ・アカデミーを振り返る
テンミニッツ・アカデミー編集部










