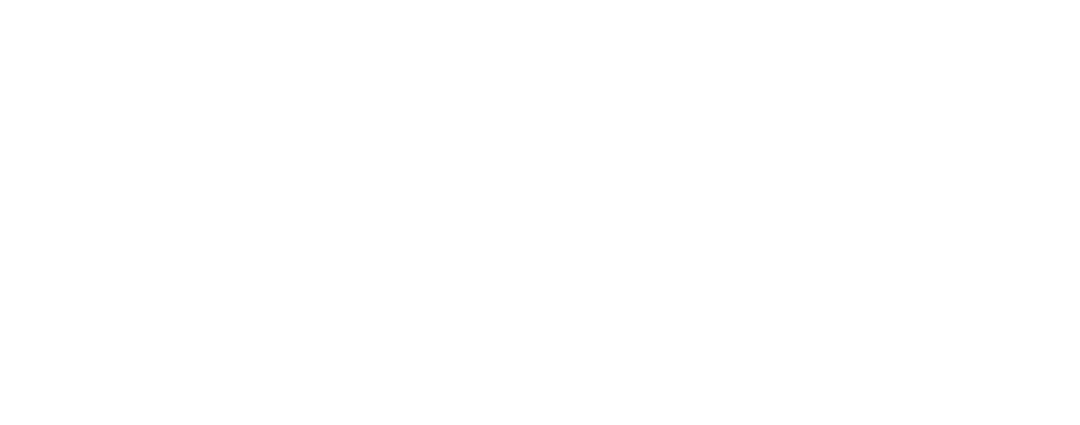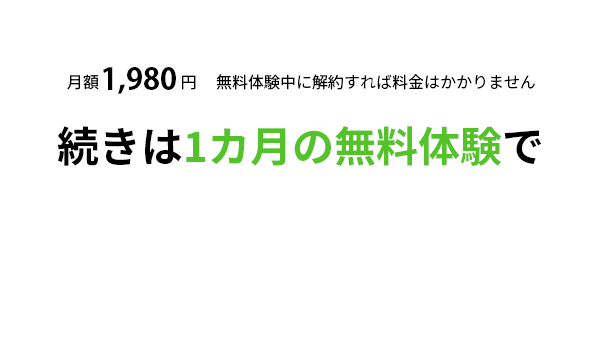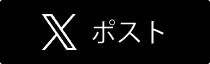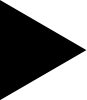●2020年代、都市部での目視外の自動飛行が実用化される
官民協議会では、安全にドローンを活用するためのさまざまな技術や、制度のロードマップ、つまり目標計画が検討されています。このロードマップは2016年に作成され、2017年に改定されました。そこではドローンの飛行による利活用が、レベル1から4までの4段階に分けられています。
レベル1は、目視内の範囲で遠隔・手動操作をするという、現在すでに行われている段階です。レベル2は、やはり見えている範囲で自動操縦を行うという、これもすでに一部で行われている飛ばし方です。
それに対してレベル3は、今後の課題です。つまり、無人地帯において、目視外で自動操縦で飛ばすという段階になります。例えば、物流で利用する場合には、こうした飛ばし方が必要でしょう。レベル3は、2018年頃をめどに実用化しようと、目標が立てられています。最後にレベル4は、こうした目視外の自動飛行を、都市部でも行うというものです。これは、2020年代以降の実用化が目標とされています。こうした目標を達成するためには、新たな技術開発だけでなく、それを社会で利用していくための制度の充実が求められるでしょう。
●GPSが使えない環境での自動飛行を可能にする技術
技術的に大きな課題となるもの、新たな技術開発が必要なものとして、まずは、GPSが使えない環境での自動飛行が挙げられます。GPSはカーナビなどで広く普及している技術ですが、その信号は非常に微弱です。建物の中では利用できません。また、屋外でも、建物の近くや橋の下、トンネルの中などでは、GPSが機能しないこともあります。
こうした状況においても、自動飛行を可能にするために、さまざまな技術が今、開発されています。ここでは4つの新たな技術を紹介しましょう。
第1に、モーションキャプチャーという技術があります。それは、建物の中でドローンを飛ばす際に、部屋の天井の周囲にカメラを設置して、その映像を基に、機体の位置を計測するという仕組みです。モーションキャプチャーを機能させるためには、部屋の中のインフラが必要です。
そこで第2に、新しいインフラを必要としない技術も開発されつつあります。機体に搭載したセンサーで周囲を把握し、自動で飛行させるという技術です。例えば、レーザー測距計を用いることで、障害物までの距離を検知することが試みられてい...