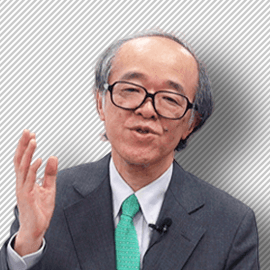●2016年はVR普及元年
VRの技術そのものに関しては、今まで話してきましたように、一定のめどがついてきたという状況だろうと思います。やっと動くようになったという状況ではなく、ある程度のクオリティのあるシステムがすでにリーズナブルなコストで利用可能だという状況にはなってきたということです。
そして、まさにこれから大胆に始まろうとしているのは、VRの技術をどうやって社会実装していくかというところでしょう。ですから、シリーズ1話目の最初の方で「2016年がVR元年」と申し上げましたが、VR普及元年だということであれば、そんなに間違ったことではないと思います。
●HMDが目に与える影響とその可能性
もちろん普及に当たっては、さまざまな障害がこれから立ちはだかってくるということはもちろんですし、それを克服できて初めて、技術として一人前のものに成長していくと思います。
即物的に考えると、おそらく皆さんが最もご心配されるところは、「HMDって大丈夫?」というようなことではないでしょうか。また、「目に悪くないのか」あるいは「斜視になるのではないのか」ということもよくいわれています。こういった問題は、どんな技術に対しても、すべからく起こってくることで、そこはその分野で権威のある人たちにそういう側面から研究していただき、実際の影響などについて見ていくということだと思います。
短期的な影響に関しては、研究者はすでに30年ほど使っていますから、そういった人たちの目がおかしくなったという話は聞いていません。少なくとも通常のVR体験に使うというくらいなら、そんなに心配はいらないのかなと思います。
ただ、それが一般に広く普及していったときはどうでしょうか。研究者は実は、そんなに耽溺するほど没入して使うという状況にはまだなっていません。よって、それが趣味化して広がっていったとき、本当に大丈夫かというのは時間的問題として、これから恐らくぽろぽろと出てくるのではないかと思います。
実際の機械は人間の外にありますから、そういう意味においては、例えば「自動車が人間に悪い影響があるんじゃないの?」といっても、自動車は人間から比べれば基本的に何メートルも先にあり、そんなに近いわけではありません。ところが、VRのヘッドマウンテッドディスプレイは人間の体に非常に近いところにありますから、そういう意味...