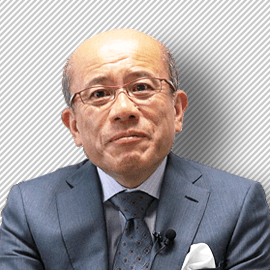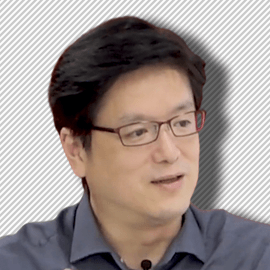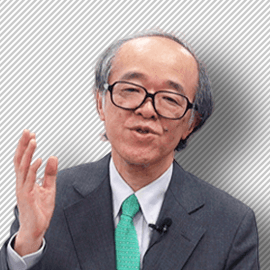このように投資にお金を回せば、社会課題も解決できる
お金の回し方…日本の死蔵マネー活用法(6)日本の課題解決にお金を回す
国内でいかにお金を生み、循環させるべきか。既存の大量資金を社会課題解決に向けて循環させるための方策はあるのか。日本の財政・金融政策を振り返りつつ、産業育成や教育投資、助け合う金融の再構築を通した、バランスの取れ...
収録日:2024/12/04
追加日:2025/03/29
デモクラシーは大丈夫か…ポピュリズムの「反多元性」問題
危機のデモクラシー…公共哲学から考える(1)ポピュリズムの台頭と社会の分断化
ショーヴィニズム(排外主義)、反エリート主義、反多元性を特徴とする政治勢力が台頭するなどポピュリズムと呼ばれる動きが活発化する中、「デモクラシーは大丈夫なのか」という危惧がかなり強まっている。アメリカのトランプ...
収録日:2024/09/11
追加日:2025/03/28
水資源リスク情報開示…野心的な気候変動目標は得なのか
水から考える「持続可能」な未来(4)前途多難社会から持続可能社会へ
気候変動に対処するべく持続可能な社会の実現が求められるが、実は世界はそうではない「前途多難社会」に向かっている。そうした中、どのようにして私たちは持続可能な社会づくりへと舵を取ることができるのだろうか。企業活動...
収録日:2024/09/14
追加日:2025/03/27
なぜ温暖化対策は必要か?気候変動の総費用から考える
水から考える「持続可能」な未来(3)気候変動社会の持続可能な開発
人口が増えることは地球温暖化に影響があるのか。日本は田畑を利用したバイオマス燃料の開発にもっと注力するべきではないのか。聴講者から寄せられた質問への応答を通じ、持続可能な社会づくりを具体的に考える。(2024年9月14...
収録日:2024/09/14
追加日:2025/03/20
薬局調剤医療費の「莫大なムダ」はいかに発生しているか
緊急提言・社会保障改革(2)調剤医療費8兆円のカラクリ
令和7年度予算をめぐる国会審議では、国民民主党が提起した「103万円の壁」問題と、日本維新の会が提起した「高校授業料無償化」に大きな注目が集まった。結果的に、少数野党となった自民党・公明党が維新の会と三党合意を結び...
収録日:2025/03/06
追加日:2025/03/15
国民医療費の膨張と現役世代の巨額の「負担」
緊急提言・社会保障改革(1)国民負担の軽減は実現するか
令和7年度予算をめぐる国会審議では、国民民主党が提起した「103万円の壁」問題と、日本維新の会が提起した「高校授業料無償化」に大きな注目が集まった。結果的に、少数野党となった自民党・公明党が維新の会と三党合意を結び...
収録日:2025/03/06
追加日:2025/03/15
長寿雇用戦略…いくつになっても働きたい人が働ける社会へ
第2の人生を明るくする労働市場改革(6)長寿雇用戦略と健全な危機感
労働市場を流動化させることが急務である日本だが、企業や個人はどのように対応していくべきなのだろうか。労働者の生産性に応じた給与システムの導入、スキルアップによる能力向上が求められる中、政策としては非常に重要なの...
収録日:2024/08/03
追加日:2025/03/14
信用創造・預金創造とは?社会でお金が流通する仕組み
お金の回し方…日本の死蔵マネー活用法(1)銀行がお金を生む仕組み
日本経済が低迷する原因は何か。大きなポイントとして「お金が回っておらず、死蔵されてしまっていること」が挙げられる。そもそも、お金が市中にどのように流通し、どのような役割を果たしていくのかを理解しなければ、経済を...
収録日:2024/12/04
追加日:2025/02/22
時計とカレンダーが支配する現代社会とストレスの問題
進化的人間考~ヒトの性質と異様な現代社会(3)近未来の情報革命に対する提言
ヒトは本来の進化環境における基本的欲求を満たしながら、文明社会を形成してきた。産業革命によってヒトも社会も大きな変化を遂げ、この百年余りの社会ではカレンダーと時計がヒトを支配し、貨幣が全てに介在するようになった...
収録日:2024/06/12
追加日:2025/01/31
心の共有、共感、推論、言語…ヒトの脳が大型化した理由
進化的人間考~ヒトの性質と異様な現代社会(2)ヒトの脳の大型化と大規模社会の形成
ヒトと他の動物の違いに、食料の獲得方法と調理の多様さがある。食料を得る生計活動があまりに大変なため、ヒトは共同体をつくり、次世代にさまざまな方法を継承して、より良く改良を重ねてきた。それは進化ではなく、生活自体...
収録日:2024/06/12
追加日:2025/01/24
ヒトの進化史を文明の発展の時間軸から考える
進化的人間考~ヒトの性質と異様な現代社会(1)進化のスパンと現在の人間生活
現代人が直面する諸問題には、個人が原因というより、社会や環境によるとみなすしかないことも多い。しかし、社会も文明も、われわれ自身がつくりあげてきたものだ。まずは、人類が育ってきた環境を振り返ってみよう。進化の長...
収録日:2024/06/12
追加日:2025/01/17
知らないうちに成功している社会と生きるのがしんどい社会
米国論(2)国家にとって一番重要なのは中流
ハートランドの人たちの考えは「自由を守るためには銃で武装する」で、これは合衆国憲法に忠実な考えでもある。「アメリカドリーム」という言葉があるように、南北戦争後のアメリカは富をずっと集積してきた。そのため才能や運...
収録日:2024/10/22
追加日:2025/01/03
日本が目指すべきは「資源自給・人財成長・住民出資」国家
2050年「プラチナ社会」実現への挑戦(3)資源自給・人財成長・住民出資国家へ
2050年には多くの国が脱炭素を達成する見込みだが、日本も森林とエネルギー産業を変革していけば、地方財源が期待できる。また、エネルギーを地元の小企業が賄うことになれば、住民出資・住民所有の道も開ける。それは、資源自...
収録日:2024/11/27
追加日:2025/01/01
エネルギー不足克服の鍵「ソーラーシェアリング」に注目
2050年「プラチナ社会」実現への挑戦(2)プラチナ産業イニシアティブ、始動
5つの「プラチナ産業イニシアティブ」創りの動きとして、第1弾「プラチナ森林産業イニシアティブ」、第2弾「再生可能エネルギー産業イニシアティブ」がそれぞれ立ち上がっている。それぞれどのような戦略のもと進められているの...
収録日:2024/11/27
追加日:2025/01/01
2025年頭所感~5つのプラチナ産業イニシアティブ創りへ
2050年「プラチナ社会」実現への挑戦(1)「プラチナ社会」実現のルーツと現況
プラチナ社会を目指すプラチナ構想ネットワークが発足して16年、課題と最適解がともに目に見えるようになってきた。第1話の今回は「プラチナ社会」構想のルーツにあたる『成長の限界:ローマ・クラブ「人類の危機」レポート』と...
収録日:2024/11/27
追加日:2025/01/01
世襲では駄目!? 社会的流動性を回復させるための鍵は教養
寛政の改革・学問吟味と現代の教育改革(2)社会的流動性を回復させるために
社会的流動性という言葉があるが、それが高い社会のほうが活気ある社会だと中島氏は言う。江戸後期、松平定信による寛政の改革はそれを後押ししたのではないだろうか。よほどの危機感があったのだろう。それを契機とした教育改...
収録日:2024/04/11
追加日:2024/12/22
北欧諸国の真似では解決せず!? 少子化問題への妙案はあるか
教養としての「人口減少問題と社会保障」(8)今こそ制度改革にチャレンジする時期
日本の人口減少問題への対応として、医療にしても、行政にしても、これまでの制度自体を根本的に見直し、制度改革にチャレンジする時期に来ているのではないかと森田氏は言う。その際、メディアでよく取り上げられる北欧諸国が...
収録日:2024/07/13
追加日:2024/12/17
人口減少社会での新たな仕組みづくりへ、鍵はデジタル化
教養としての「人口減少問題と社会保障」(7)デジタル化で社会を変える
人口減少の流れは止められないとすると、どうやって今の社会を維持していくかが課題となる。そこで、森田氏が提案するのが「デジタル化」の推進である。どの分野でデジタル化を進めればよいか、バーチャルな総合病院の構築など...
収録日:2024/07/13
追加日:2024/12/10
超深刻化する労働力不足、解消する方策はあるのか
教養としての「人口減少問題と社会保障」(6)労働力の絶対的不足という問題
人口減少によって深刻となる問題の2つ目が「労働力不足」である。今盛んにいわれている女性活用、高齢者活用、外国人労働者受け入れは、労働力の絶対的不足を解消する有効な方法となり得るのか。これからの労働力不足の問題と方...
収録日:2024/07/13
追加日:2024/12/03
人生前半の支援を手厚く!社会保障と税の一体改革の真髄とは
総理として実感した国家経営の要諦(3)財源の話を先送りしない
「財源なくして政策なし」という方針のもと、国家経営の基本として2番目に重きを置いたのは、財源の話を先送りしないことだったという野田氏。超高齢社会に突入し財政難を抱える日本だが、歳入の減少と歳出の増加という、いわゆ...
収録日:2024/04/18
追加日:2024/11/27
買い物難民、スポンジ化…地方消滅という人口減少の課題
教養としての「人口減少問題と社会保障」(5)地域社会の崩壊
人口減少がもたらす社会の変化として顕著に現れているのは、労働力不足が課題になっている大都市圏ではなく、むしろ地方だと森田氏は言う。地域社会の崩壊は、「スポンジ化」といわれる空き地・空き家問題をはじめ、「買い物難...
収録日:2024/07/13
追加日:2024/11/26
国の借金は誰が払う?人口減少による社会保障負担増の問題
教養としての「人口減少問題と社会保障」(4)増え続ける社会保障負担
人口減少が社会にどのような影響を与えるのか。それは政府支出、特に社会保障給付費の増加という形で現れる。ではどれくらい増えているのか。日本の一般会計の収支の推移、社会保障費の推移、一生のうちに人間一人がどれほど行...
収録日:2024/07/13
追加日:2024/11/19
「自分さえよければいい」では社会問題は解決しない
対談・反生命論(5)「自分が大切」は下品な考え方
「自分が大事」「自分さえよければいい」というのは、下品な人間の考え方である。グリム童話などではずる賢いおじいさん、おばあさんが登場するが、そんな人たちばかりを目にする状況が、日本は70年以上続いている。ロシアなど...
収録日:2024/05/24
追加日:2024/11/15
高福祉国家フィンランドでも…世界的に進む人口減少の実態
教養としての「人口減少問題と社会保障」(3)なぜ少子化は止められないのか
なぜ人口減少は止まらないのか。日本の場合、合計特殊出生率の低下に加え、20~30代の女性の数自体が大幅に減っているという現状がある。さらにこの人口減少は日本だけの傾向にとどまらず、世界的にも問題となっている。それは...
収録日:2024/07/13
追加日:2024/11/12
生産年齢人口が4割減に!? なぜ人口減少は起こったのか
教養としての「人口減少問題と社会保障」(2)人口減少のメカニズム
今回はまず、戦後の日本の人口推移を年代別に見てみよう。すると、子どもや現役世代の人口数のピークはとうの昔に過ぎ去り、それが日本の人口減少につながっていることが分かる。では、なぜそのような人口変化が起きるのか。そ...
収録日:2024/07/13
追加日:2024/11/05
毎年100万人ずつ減少…急降下する日本の人口問題を考える
教養としての「人口減少問題と社会保障」(1)急速に人口減少する日本の現実
昨今、日本において「少子化」や、それに伴う「人口減少」が大きな話題となっている。なぜ少子化や人口減少は問題なのか。どうすれば解決できるのか。それについて考えるための前提知識として、まずは日本の人口が歴史的にどの...
収録日:2024/07/13
追加日:2024/10/29
契機はリスボン大地震…ルソーが中間団体を考えなかった訳
独立と在野を支える中間団体(2)中間団体なきルソーの「社会契約論」
中間団体について深く考える上でルソーの『社会契約論』は基本的な議論の1つといえる。『社会契約論』では、個人が契約して国家を形成し、そこで形成された一般意志に皆が従い、犠牲を払うというものだが、そこには中間団体とい...
収録日:2024/06/08
追加日:2024/10/25
若返りは可能!?今こそ抗加齢医学を社会実装するタイミング
新しいアンチエイジングへの挑戦(2)アンチエイジングの現在地
加齢による変化、つまり老化を制御することはできるのか――「人生100年時代」ともいわれる今、どれだけ健康に若々しく長生きできるかは誰しもが気になるところだが、最新の研究では、身体の老化を抑え若さを保つアンチエイジング...
収録日:2024/06/26
追加日:2024/10/17
ノイズを楽しむ――半身社会の「読書と教養のすすめ」
なぜ働いていると本が読めなくなるのか問答(2)ノイズと半身社会の処方箋
「読書はノイズを含むもの」と語る三宅香帆氏。ノイズとは知りたいことの背景となる知識やその後ろにある歴史的文脈を教えてくれるものだが、仕事が忙しく余裕がなくなってくると、そうした周辺情報がまさにノイズだと感じてし...
収録日:2024/08/26
追加日:2024/10/13
結婚も競争も個人の責任…「家」の崩壊と個人化社会の現実
ヒトの性差とジェンダー論(7)「配偶」と「個人化」の問題
結婚・配偶者選択の文化が大きく変わっている部分もあるが、それは生物学的に見ると、どう位置づけられるのだろうか。実は、生物学的に見ただけでも、雄雌がどうやって配偶して、一緒になって、子どもを持つかということには、...
収録日:2024/05/18
追加日:2024/09/30
ヒントは幕末期の処士横議!?…タテ社会の構造改革に向けて
『タテ社会の人間関係』と文明論(8)タテ社会の構造改革を議論する
タテ社会の問題をどう乗り越えていけばいいのか。この問題に関連して、平安時代の朝廷における「陣定」という貴族会議で、発言しやすいように身分に準じて発言の順番を変えたという話が取り上げられているが、そうした小手先の...
収録日:2024/05/27
追加日:2024/09/26
「金属社会」が経済を支え、考えない人間は家畜となる
反生命論(9)反生命が真の人間を創り上げる
人間の歴史は、金属の精錬の歴史である。結果として人間は、AIをはじめとする機械を生み出した。我々人間から魂が去りつつある中、機械が新しい人間になるかもしれない。そこで今、武士道という魂の一部をAIに打ち込んでいると...
収録日:2024/05/16
追加日:2024/09/20
『失敗の本質』より先に指摘した日本型組織の弱点
『タテ社会の人間関係』と文明論(7)日本型組織とリーダーシップの問題
日本軍研究で知られる『失敗の本質』よりも前に、日本型組織の弱点を指摘していた『タテ社会の人間関係』。日本の軍隊と英米の軍隊を例にとって、人間関係を重視する日本型組織の特徴を鋭く指摘、さらに法然と弟子の話を取り上...
収録日:2024/05/27
追加日:2024/09/19
タテ社会はアウトソーシング嫌い!? AIでも変わらない日本
『タテ社会の人間関係』と文明論(6)エモーショナルなタテ社会のつながり
日本は江戸時代から競争が激しい社会で、敗者への救済は乏しく、非公式な集団に救いを求めてきた。現代では企業が従業員の福祉などを担う形が一般化されたが、こうした「タテ社会」の構造が日本独自の終身雇用や企業内福祉とし...
収録日:2024/05/27
追加日:2024/09/12
カトリックでも例外!? アイルランドに対する偏見とその背景
アメリカの理念と本質(4)アングロ・サクソンの社会
ヨーロッパのカトリック社会では人と人のつながりを大切にするが、プロテスタントの国々では個人主義がより先鋭に主張される。中でもアングロ・サクソンの社会に冷たさを感じた日本人留学生はイギリスに留学した夏目漱石をはじ...
収録日:2024/06/14
追加日:2024/09/10
なぜ平成は失敗したのか…究極の競争社会と日本の特殊性
『タテ社会の人間関係』と文明論(5)建前で動く日本社会と平成の失敗
「海外よりも、より究極の競争をしてきたところがあるのではないか」と、『タテ社会の人間関係』で示唆した中根氏。「タテ社会」の日本では、法制度は建前としての役割が大きく、契約が情緒的な駆け引きの道具になっているとい...
収録日:2024/05/27
追加日:2024/09/05
武士の誇りにも影響…中世のヨコ社会から近世のタテ社会へ
『タテ社会の人間関係』と文明論(4)ヨコ社会からタテ社会への転換
江戸時代以前の日本社会では「ヨコ型」の要素も多く存在しており、象徴的な言葉として中世の日本にあった「兼参」を紹介する呉座氏。兼参とは複数の主君に仕えることで、つまり中世ではリスクヘッジとして複数の集団に属するこ...
収録日:2024/05/27
追加日:2024/08/29
日本人は分業がヘタクソ!? ワン・セット主義の是非を問う
『タテ社会の人間関係』と文明論(3)日本型の競争原理とワン・セット主義
「日本人は分業するのがヘタクソである」――『タテ社会の人間関係』が書かれた戦後の高度経済成長期、日本型の競争原理はうまくいっていたのだが、半世紀以上たち、グローバル化した現代社会でそれが行き詰っている要因について...
収録日:2024/05/27
追加日:2024/08/22
『東京物語』原節子が象徴的!? 場による日本の人間関係
『タテ社会の人間関係』と文明論(2)場から日本社会を動かすダイナミクス
日本とインドの社会構造は対極の位置にあるというのが『タテ社会の人間関係』での中根氏による分析である。日本の「タテ社会」は場を重視し、例えば移民や転出者が帰国するとよそ者扱いされるのに対し、インドや中国、イギリス...
収録日:2024/05/27
追加日:2024/08/15
「暴力はいけません」では済まない…国際社会が抱える難題
紛争が絶えない世界~私たちは何ができるか(2)国際社会の問題点と人間の本性
なぜ国際社会は世界から戦争や紛争を止めることができないのだろうか。その原因について、「国家とは何か」といった根本的な問いから考える。しかし、そこには「暴力の独占」を正当化する国家を超越する「至上の権力」がない国...
収録日:2024/04/27
追加日:2024/08/14
誤解された『タテ社会の人間関係』…日本社会の本質に迫る
『タテ社会の人間関係』と文明論(1)誤解を招いた「タテ社会」の定義
『タテ社会の人間関係』は戦後日本の社会構造を的確に分析した社会人類学者・中根千枝氏の著書で、当時ベストセラーとして大変注目を集めた名著である。日本を「タテ社会」と定義して鋭い視点で切り込んでいるのだが、その定義...
収録日:2024/05/27
追加日:2024/08/08
私たちはどんな社会を望むのか?鍵は「希望のレッスン」
人の資本主義~モノ、コトの次は何か?(2)社会システムの洗練と希望のレッスン
生成AIなど情報技術が著しく発達した現在、資本主義にはより賢くなってもらう必要がある。同時に、私たちの社会が真に豊かになるためには、社会システムを洗練することがどうしても必要であるという中島氏。そのためにも、私た...
収録日:2024/04/11
追加日:2024/08/03
「人生で最も虚しかった日は?」…笑いは大事な文化
世界のジョーク集で考える笑いの手法と精神(4)文化としての笑いと寛容な社会
「差別か、笑いか」――昨今、ポリコレなどの浸透によって、その線引きがだんだんと厳しい方向へ進んでいる。「笑いは人間にとって大事な文化だ」という早坂氏もそのことをとても危惧している。そこで最終話の今回は、シャンフォ...
収録日:2024/03/14
追加日:2024/07/05
山上憶良が示したグローバル社会に生きるためのヒント
山上憶良「好去好来の歌」を読む(4)改良・改善と「墨縄」の思想
日本人の創造力の源は改良・改善にある。改良・改善とは、海外から得たものを「身の丈に合ったものにしていく」ことである。そこで山上憶良である。彼は遣唐使に対して「墨縄」という言葉を用いて「一直線に帰ってこい。無事で...
収録日:2024/04/02
追加日:2024/06/09
小さな不幸と大きな安定をバランスする社会のあり方とは
価値と人間(8)小さな不幸と大きな安定
「国家は消滅しなければならない」とレーニンが『国家と革命』で述べた。本当にいい社会とは、国家のない社会なのだろうか。一方、日本の大問題は少子高齢化だが、国民が少なくても成り立つ社会を築けば問題は解決する。つまり...
収録日:2024/01/31
追加日:2024/05/17
戦後ダメになったのは日本だけでない、欧米はより堕落した
価値と人間(5)欧米社会の堕落
現代の政治・社会を動かしている民主主義の考え方は、全面的にダメなのではない。しかし、下が上を選ぶ現在の選挙制度がある限り、多数派にしか正義はない。そうなると、エリートが生まれなくなるから、やがて国が滅びてしまう...
収録日:2024/01/31
追加日:2024/04/26
カーボンニュートラル社会に必要な「発想の逆転」とは
日本のエネルギー&デジタル戦略の未来像(2)電力の需給バランス
これからの社会では、電力化の進展によるモビリティやロボットの「カンブリア爆発」によって、電力の消費量も増えていくことも予想される。そのような社会を支える電力をいかにサステナブルに供給するかが重要な課題となるが、...
収録日:2024/02/07
追加日:2024/04/20
努力した人間を認める社会にならなければ滅びるしかない
価値と人間(4)縁の下の力持ち
明治時代は、本などで取り上げられる対象となるのは優れた人物であり、その歴史的業績だった。しかし、今は褒められ、評価されるのは、本来陰で行うものでわざわざアピールするものではなかったボランティアが対象になっている...
収録日:2024/01/31
追加日:2024/04/19
規範違反を繰り返すロシア…国際社会が果たすべき役割とは
歴史から考える「ロシアの戦略」(7)今後のロシアと国際社会
プーチン政権が戦争を続ける目的が何なのか。2022年に始まったウクライナへの軍事侵攻は、ロシアにとってはもはや引くに引けない状況になっている。今後もその状況は続きそうだが、そこで問われるのが国際社会の姿勢である。硬...
収録日:2024/01/18
追加日:2024/04/01
古代日本語の発音はなぜわかるのか…ヒントは中国の唐詩
文明語としての日本語の登場(2)文字社会の成立―漢字と発音―
日本で奈良時代に文字が使われるようになったのは、律令国家の成立が社会的急務だったからである。戸籍や税務など、公文書は文字によって成り立ち、国家社会の秩序維持は文字に依拠している。では当時の発音はいかにすれば復元...
収録日:2023/12/01
追加日:2024/03/15
GDP・貯蓄・社会保障・財政政策…高齢化がもたらす影響
日本の財政政策の効果を評価する(2)高齢化が経済に与える影響
日本の高齢化率は現在世界一で、2030年には国民の3人に1人以上が高齢者になるといわれている。では高齢化は経済にどのような影響を与えるのか。最近の研究結果から、GDP、貯蓄、社会保障の3つに影響を与えることが分かっている...
収録日:2023/12/14
追加日:2024/03/14
数字を追いかけるな、説明責任を求めるな…共感経営への道
日本企業の病巣を斬る(9)社会的共感経営の実現
野中郁次郎氏の唱える「知識創造企業」を築くには、「暗黙知」の活用と、地域やお客さんとの「共感」が重要である。まさに「共感経営」が重要だが、そのためには、数字を追いかけたり、説明責任を求めたりするのが間違いだとわ...
収録日:2023/10/18
追加日:2024/01/26
生成AIは人類の希望…生成AIで教養を高めて問題解決せよ
完全循環型社会と教養の時代(2)生成AIで教養を高める
人類は再生可能エネルギーと都市鉱山による「完全循環社会」という方向へ向かっている。再生可能エネルギーはその普及予測が何度も書きかえられるほど急速に普及しており、都市鉱山への可能性としてスクラップからEV車を作ると...
収録日:2023/11/22
追加日:2024/01/08
2024年・年頭所感…完全循環型社会と健康長寿社会へ
完全循環型社会と教養の時代(1)これから何が起こるか
いま、生成AIが信じられないくらいのスピードで進化している。これは、人間の知的生活にも、間違いなく大きな影響を与える。地球環境も、日本各地で40度を超える気温になるなど、大問題になっている一方、世界中で再生可能エネ...
収録日:2023/11/22
追加日:2024/01/01
賃金上昇の格差が経済を活性化!?最適なインフレ論の真相
インフレ社会への転換と日本経済の行方(2)賃上げの問題と最適なインフレ論
「停滞と安定の時代」といわれる20年以上のデフレ社会が終焉を迎え、インフレ社会へと移行する日本経済。その大きな変化の中で重要なのは賃金についてである。賃上げの問題は実体経済、とりわけ企業経営に非常に大きな影響を与...
収録日:2023/11/01
追加日:2023/12/19
なぜ仮名序で六歌仙を批評?ポイントは「さま」と社会性
『古今和歌集』仮名序を読む(6)六歌仙の先輩たち
古来、謎とされてきたのが「仮名序」で登場する六歌仙への批判めいた言葉である。六歌仙とは、『古今和歌集』の撰者から数えて50~80年ほど先輩にあたる、僧正遍昭、在原業平、文屋康秀、喜撰法師、小野小町、大伴黒主の6人であ...
収録日:2023/07/05
追加日:2023/12/13
物価も賃金も2%上昇する社会へ…資産運用に敏感な動きが
インフレ社会への転換と日本経済の行方(1)値上げの問題と財政への影響
日本は今、物価も賃金も2パーセント上昇する社会へと移行しようとしている。30年近く続いたデフレの間、国民にはデフレマインドが定着し、値上げができないままでいたが、2022年の後半から3パーセントを超えるような水準でイン...
収録日:2023/11/01
追加日:2023/12/12
和歌には社会的な意義もあった…『古今和歌集』の思想とは
『古今和歌集』仮名序を読む(5)いにしへの歌
「仮名序」では「いにしへの歌」を通して歌の社会的意義が述べられる。『古今和歌集』が編纂された頃(900年頃)について、「仮名序」は「今の世の中は派手さを求め、人の心も移ろいやすくなってしまったがために、不実な歌、い...
収録日:2023/07/05
追加日:2023/12/06
公共心だけで人材確保は無理…迫られる給与体系の見直し
経済と社会の本質を見抜く(6)公的機関の人材確保
官僚を志望する優秀な学生の減少が取り沙汰されているが、日本銀行にも優秀な人材がなかなか集まらなくなっているという。それは、若くて優秀な人材が民間企業に流れてしまうからだが、ではパブリックセクター(公的機関)とし...
収録日:2023/08/09
追加日:2023/12/03
アメリカの一流大学でMBAの学位を取得する3つの意義
経済と社会の本質を見抜く(5)MBAをアメリカで取得する意義
経済政策や企業経営に携わる人間にとって、いまや欠かせない学位となっているのが「MBA(経営学修士)」だ。日本国内でも取得可能な学位だが、アメリカの一流大学でのMBA取得にはとくに重要な意義があるようだ。AIなどの技術革...
収録日:2023/08/09
追加日:2023/11/26
コンプライアンスよりも重いレピュテーショナルリスク問題
経済と社会の本質を見抜く(4)コンプライアンスとリスクの境界線
経済を動かす企業の活動に大きく関わるのが「コンプライアンス」の問題だ。事業の透明性を担保し健全に事業を運用する上では欠かせないコンプライアンスだが、そこには活動を萎縮させる負の側面もあるようだ。それが「レピュテ...
収録日:2023/08/09
追加日:2023/11/19
失敗もポジティブに評価――チャレンジできる社会つくりへ
経済と社会の本質を見抜く(3)スピード感のある意思決定
経済政策を考えるうえでは、国という単位にとらわれず、地域ごとの特性を見ていく視座が必要だ。それを可能にする細かなデータは、近年の研究や技術の発達で集まるようになっている。AI開発も著しい進展を見せる現代社会におい...
収録日:2023/08/09
追加日:2023/11/12
欧米の落ち方は日本の比ではない…これは「人類問題」だ
電脳社会の未来(9)この堕落は「人類問題」
かつて国家は、「働くことが好き」「勉強が好き」という人たちに支えられていた。だが今や、その文化を国家が否定している。知性や合理性、平等、民主主義、科学は全てAIに移行し、われわれホモ・サピエンスが担うのは悪いもの...
収録日:2023/08/02
追加日:2023/11/10
世界の超富裕層は日本の比ではない…国単位の政策の限界性
経済と社会の本質を見抜く(2)マクロ政策に対するミクロ的視座
続いて考えるのは、それぞれの社会の「違い」がどのように影響するのか、ということである。欧米と日本では、労働市場の構造からして異なる経済を持っており、それが金融政策にも影響を与えている。そもそも「日本」や「アメリ...
収録日:2023/08/09
追加日:2023/11/05
「ずる賢い考え方」をしたがる人類に科学や民主主義は無理
電脳社会の未来(8)やはり最後の記念碑は芸術である
「法の前の平等」は、人間が裁判官をやっている限り絶対に達成できない。人間は平等、正義、科学を標榜しているのに、例えば、縁故とずる賢さと自分だけうまいことをしたいという、さもしい根性を捨てないからだ。AIに、全面的...
収録日:2023/08/02
追加日:2023/11/03
インフレ激化の真実…デフレ脱却を困難にした日本の労働市場
経済と社会の本質を見抜く(1)世界的インフレと労働市場の影響
現在の経済、そして社会の本質を、どのように見抜いていけばいいのだろうか。最初に考えるのは、インフレについてである。可能性は低いが、インフレが激化する「ハイパー・インフレーション」が起こると、いったい社会はどうな...
収録日:2023/08/09
追加日:2023/10/29
現行人類に残された部分は混沌、不合理、魂の野蛮さ
電脳社会の未来(7)魂の野蛮な部分が人間の特質
人に感化を与えるのは、真の教養を持っている人である。同時に、人間は危険な存在でもある。「希望」があると思って、「悪」をやめないからである。だからこそ、悪意に満ちた人類性善説、機械性悪説を打ち砕かなければいけない...
収録日:2023/08/02
追加日:2023/10/27
自由主義、保守主義、全体主義…真の社会全体の利益とは?
日本人が知らない自由主義の歴史~後編(13)「自由な社会」を守るために
現代では「保守主義と自由主義(リベラル)は対立する」と思っている人も多い。だが本来、自由主義と保守主義は対立する概念ではない。そして、本当に自由主義と対峙するものは全体主義である。最終話である今回は、「保守主義...
収録日:2022/07/25
追加日:2023/10/20
考えてみれば人類が発展したのは「性悪説」の時代だった
電脳社会の未来(6)人類は性善説によって滅びる
理解しておかなければいけないのは、人類の発展を支えたのは「性悪説」だということである。だが、現在は「生まれただけで素晴しい」という性善説ばかりがもてはやされている。それでは、しつけも教育もできるはずがない。そし...
収録日:2023/08/02
追加日:2023/10/20
悪と善とが交互になって、初めて物事が転がっていく
電脳社会の未来(5)善の魂と悪の魂
物事は陰と陽の関係で進む。「陰と陽」を「悪と善」と言い換えれば、悪がなければ善はない。悪と善は交互になって初めて物事が回転していくということだ。悪といわれる場から希望という善が生まれる。悪にはそれぐらい何かを生...
収録日:2023/08/02
追加日:2023/10/13
行き過ぎた「綺麗事」で人間が自らを否定している
電脳社会の未来(4)綺麗事と人間
われわれは民主主義や平等といった綺麗事に侵され過ぎて、人類が滅びるところまで来ている。それは武士道と騎士道が受け持っていた「悪をぶった切る悪」を認めないからである。「AIには人情がない」などと言うが、その人情は人...
収録日:2023/08/02
追加日:2023/10/06
「人間の健康にとって何がいいか」の答えが「読書」?
電脳社会の未来(3)再び中世のような時代になる
あるとき、テレビでAIが質問に対して答えを出していく番組をやっていたが、そのとき、「人間の健康にとって何がいいですか」と質問すると「読書」という答えが出され、「では健康によくて長生きする方法は何ですか」と尋ねたら...
収録日:2023/08/02
追加日:2023/09/29
フリードマン『資本主義と自由』…自由な社会を守るために
日本人が知らない自由主義の歴史~後編(9)ミルトン・フリードマンの主張
古典的自由主義について、経済学の古典の1つにミルトン・フリードマンの『資本主義と自由』がある。“事実”を非常に重視するフリードマンは、ここで政治的自由と経済学的自由の関係性を実証的に明らかにしている。そして、政府の...
収録日:2022/07/25
追加日:2023/09/22
混沌=魂を持っている人間だけが家畜にならずに生きていく
電脳社会の未来(2)家畜になるかならないか
われわれは今、ホモ・サピエンスの頂点の文明として、自由、平等、民主主義、科学などを掲げて現代を生きている。しかし、こういった人類の掲げた「理想」=綺麗事をAIが受け持つ社会になっていくのではないか。人類が受け持つ...
収録日:2023/08/02
追加日:2023/09/22
ハイエク『隷従への道』…社会主義はなぜ弊害だらけなのか
日本人が知らない自由主義の歴史~後編(8)ハイエクの『隷従への道』
リバタニアニズムの古典的著作はさまざまある中で、まずはハイエクの『隷従への道』をとり上げる。なぜ社会主義ではいけないのか、人間社会がどのようにして成り立っているかなど、思想家としてのハイエクの考え方を理解するこ...
収録日:2022/07/25
追加日:2023/09/15
現行人類の限界を考えれば電脳社会への見る目も変わる
電脳社会の未来(1)人類唯一の希望
執行草舟が「AIの発展は人類唯一の希望」だというのは、われわれが人類は自分たちを「よいもの」と考えている、その前提がそもそも間違っているという考えから電脳社会の未来を語るシリーズの第一回。人間にはよいところもあれ...
収録日:2023/08/02
追加日:2023/09/15
脳の「やる気スイッチ」ドーパミンが大きな社会問題!?
知られざる「脳」の仕組み~脳研究の最前線(6)4つの情報伝達方式と広範囲調節系
脳の中には「一対一」だけではなく、「一対多」や「多対多」といった情報伝達の仕組みもある。大きく分けると、4つの情報伝達の方式があるという。その中でも特に注目したいのが「広範囲調節系」という伝達方式で、私たちの日々...
収録日:2022/10/21
追加日:2023/08/07
計画経済が失敗する理由…ミーゼス、ハイエクの鋭い指摘
日本人が知らない自由主義の歴史~後編(2)社会主義計画経済への批判
第一次世界大戦後、リベラリズムは社会主義に傾倒していく流れがさらに顕著となっていく。この時期、ニューリベラリズムへの異を唱えたのがミーゼスやハイエクといった自由主義経済学者たちであった。彼らはニューリベラリズム...
収録日:2022/07/25
追加日:2023/07/21
生命情報・社会情報・機械情報と本居宣長「もののあはれ」
ChatGPT~AIと人間の未来(8)シンギュラリティと「もののあはれ」
AIに関する議論では、シンギュラリティのような悲観論も多い。未来が暗くならないために必要なことは何か。重要なのは、アメリカ的な考え方をそのまま受け入れるのではなく、日本の伝統と文化を尊重した日本ならではのAIとの関...
収録日:2023/03/15
追加日:2023/07/06
学生運動はなぜ暴走したのか?「加害と被害」意識の関係
『「甘え」の構造』と現代日本(6)日本人の被害的心理と社会運動の過激化
『「甘え」の構造』が出版された1971年は、学生運動が盛んな時期だった。その中で、あさま山荘事件など過激化する社会運動の背景として深く関わっているのは、日本人が抱く被害的心理ではないか。その点について、本書の中で著...
収録日:2023/03/13
追加日:2023/07/01
イヌを通じて広がる「イヌ友」コミュニティのメリット
もっと知りたいイヌのこと(3)社会的動物としてのイヌ
サルの社会性については研究が多いが、イヌの社会性に関する研究は最近始まったばかりである。人間はサルの仲間であり、イヌとは違った系統なので、行動にも違う部分が多い。たとえばサルは「個食」だが、イヌは同じものを分け...
収録日:2023/03/29
追加日:2023/06/26
カミュ『異邦人』を考察…タイトルは『他人』と訳すべき?
『「甘え」の構造』と現代日本(5)カミュの思考実験と遠近法なしの社会
フランスの作家カミュに『異邦人』という小説がある。土居健郎氏は、正しい訳題は『他人』だったのではないかという問題提起をしている。そこには、ある種一つの思考実験としてカミュが描き出した問題を通して、人間関係と甘え...
収録日:2023/03/13
追加日:2023/06/24
民主主義社会で一番の悪魔は「幼稚な人間」である
人生のロゴス(3)堕ちた者も自由に堕ちたのだ
次の座右銘は道元の言葉で、執行氏がもっとも尊敬しているという橋田邦彦の愛読書だった『正法眼蔵』からである。橋田邦彦は戦争責任を押し付けられて散った。また、ジョン・ミルトンは〈正しく立てる者も自由に立ち、堕ちた者...
収録日:2023/03/29
追加日:2023/06/09
「ペロブスカイト太陽電池」のサブスクで世界の先端へ
日本の「新しい成長」実現のために(3)循環型社会に合ったビジネスモデル
日本の発明品である「ペロブスカイト太陽電池」をいかに世界に先駆けて商品化するか。今後、循環型社会にマッチするシステムはサブスクビジネスによる実験的手法なのかもしれないと、小宮山氏は言う。前回お伝えした再生可能エ...
収録日:2023/01/31
追加日:2023/05/29
介入主義?社会主義?…ニューリベラリズムとは何か?
日本人が知らない自由主義の歴史~前編(5)ニューリベラリズムの台頭
19世紀後半になると、リベラリズムに変容が見られるようになる。自由実現のために政府が積極介入すべきという「大きな政府」を肯定するニューリベラリズムの台頭である。ここでは、ニューリベラリズムが登場した背景やその思想...
収録日:2022/07/01
追加日:2023/05/16
妄想が過激化…ハインリッヒ13世の陰謀とSNS社会の危険
ハインリッヒ13世の事件…他人事ではない陰謀論の恐怖
2022年12月、ドイツでハインリッヒ13世の事件が起こった。これは、古い貴族の出身者であるハインリッヒ13世が中心人物の極右グループが政府転覆を企てて逮捕されるという事件だが、グループの実態を調べると、インターネットを...
収録日:2023/03/31
追加日:2023/05/14
経営幹部のセクハラは一発退場!ハラスメント問題を考える
本質から考えるコンプライアンスと内部統制(2)社会の変化から考えるハラスメント
セクハラ、パワハラ、マタハラなど、ハラスメントにはさまざまな種類がある。その全てが法令違反というわけではないが、企業のリスク管理において、役員・経営幹部のセクハラは一発退場になるのが現在の常識となっている。では...
収録日:2023/01/16
追加日:2023/05/10
儒家の思想「天人相関」…天に代わり愉快な社会をつくる
徳川家康と貞観政要(6)人情と天人相関
儒教に「天人相関」という思想がある。自然現象と人間の行為には密接な関係があるという思想だが、今回は天災による大飢饉が起きたときに太宗が取った政策について、臣下との問答から「長」という立場にある人間が心得なければ...
収録日:2020/02/08
追加日:2023/04/16
大伴旅人の「梅花の宴」序文に込めた日本文化への想い
万葉集の秘密~日本文化と中国文化(5)「梅花宴序」と多文化社会
日本文化は中国的なものやグローバル文化とは切っても切り離せないが、一方で「われわれの文化を大切にしなければいけない」という想い、ローカルなものを生かそうという姿勢も持っていた。それは、『万葉集』巻5、元号「令和」...
収録日:2022/09/13
追加日:2023/04/11
1000兆円規模の可能性?台湾有事の日本への影響は甚大
台湾有事を考える(8)日本への影響と国際社会の支援
台湾有事による日本への影響はどれくらいになるのだろうか。サイバー攻撃による社会経済システムの機能不全、原発へのミサイル攻撃など想定される可能性を踏まえて考えると、損害はGDPの数年分になるのではないかという予測もあ...
収録日:2022/12/19
追加日:2023/02/27
ゲノム編集技術も培養肉へ展開可能!課題は社会受容性
培養肉研究の現在地と未来図(5)これからの培養肉研究と社会受容性の問題
技術がいくら進歩しても、それを人々が拒んで使わなければ、その技術は社会に普及しない。進展著しい培養肉研究を、人々はいったいどのように受け止めているのだろうか。大規模な調査によって、日本人の培養肉への抵抗の強さが...
収録日:2022/10/11
追加日:2023/02/07
培養肉が社会で受け入れられるための「3つの課題」
培養肉研究の現在地と未来図(4)「本物の肉」再現への課題
日進月歩の培養肉研究において、本物と遜色ない肉をいかに培養するかについてはまだまだ課題も少なくない。特に、本物同様の肉の厚みを再現するには技術的な困難がある。肉の構造や味を分析し、その再現を試みる研究の現在と課...
収録日:2022/10/11
追加日:2023/01/31
国際政治を理解するために知っておくべき「3つの危機」
戦争と平和の国際政治(3)3つの危機と「国家と社会の関係」
ロシアのウクライナ侵略や台湾危機などの国際的緊張だけでなく、感染症や気候変動といった人類規模の問題に直面している現代。かつてないほど「安全」というものの価値が高まる中、いかにして個人の「自由」を守っていくべきだ...
収録日:2022/12/01
追加日:2023/01/26
「キリスト教は知らない」ではアメリカ市民はつとまらない
「アメリカの教会」でわかる米国の本質(1)アメリカはそもそも分断社会
アメリカが日本の運命を左右する国であることは、安全保障を考えても、経済を考えても、否定する人は少ないだろう。だが、そのような国であるにもかかわらず、日本人は、本当に「アメリカ」のことを理解できているだろうか。日...
収録日:2022/11/04
追加日:2023/01/06
私心を捨てる――幕臣・山岡鉄舟が体現した武士道
江戸とローマ~「父祖の遺風」と武士道(6)武士道の喪失と現代社会の問題
新渡戸稲造の『武士道』には、古代ローマの「父祖の遺風」に訴えるエピソードが多数盛り込まれていた。「義」を貫き、相手への思いやりを「惻隠の情」として表し、私心を捨て捨て身になることの大切さである。幕末には武士道を...
収録日:2021/07/16
追加日:2022/12/17
異端の経済学者…ドイツ歴史学派、社会主義、マルクス主義
本当によくわかる経済学史(5)古典派を批判した異端者たち
古典派経済学が一世を風靡した時代には、それに批判的な意見も登場する。それが、ドイツ歴史学派や、社会主義、マルクス主義といわれるグループだった。これらの考え方は今でも根強く残っているのだが、やはり「異端」であって...
収録日:2022/06/08
追加日:2022/12/14
社会の真実がよくわかる!柿埜先生の経済学史講座
2022年11月23日(水)
たとえば、各政党の経済政策を聞いても、どれも「一理」はありそうに見えてしまう。様々な経済学説や経済的な議論が盛んに行なわれるけれども、どれが正しいかわからない……。
そのような経験をされている方も多いと思います。
...
収録日:2022/11/07
追加日:2022/11/23
「リスクを取らず」では発展なし…日本社会の負の螺旋構造
現代人に必要な「教養」とは?(7)日本型タテ社会と語学教育の問題
日本型タテ社会で多様性が叫ばれインターネットが進展するに伴って、社会的なつながりが希薄になっているといわれる昨今。ではそうした状況の中、どう社会性を育めばいいのか。母国語と英語教育についてと合わせて、両先生が非...
収録日:2022/06/29
追加日:2022/11/11
人間の本質とは?混沌とした現代社会に対する大事な問い
現代人に必要な「教養」とは?(6)議論と雑談、人間の本質について問う
「本質を捉える知」は教養にとって大事だが、では「人間の本質」とは何か。また、多様性の時代、「議論」とともにビジネス世界で見直されている「雑談」についてなど、ウェビナー参加者からの質疑応答編第1弾。(全8話中第6話:...
収録日:2022/06/29
追加日:2022/11/04
通勤は本当に必要か、メタバースが創造する新都市スタイル
ゼロからわかるメタバース(5)拡張認知による自律協調型社会
コロナ禍で体験している「リモート化」により、われわれは新しい価値観の一端に触れている。例えば、20世紀の特徴に大都市に通勤する会社員が増えたという点が挙げられるが、「リモート化」が進む中、通勤は本当に必要なのかと...
収録日:2022/03/10
追加日:2022/10/26