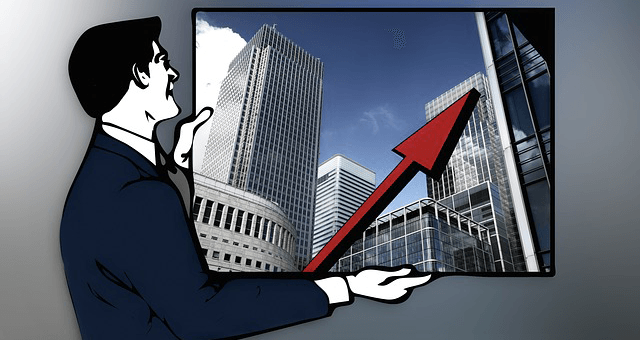●「経済学」の名のもとに多種多様なアプローチがある
―― そもそも経済学とは、また「経済学的な発想」とは何か、というところを少しお話しいただきたいです。
柳川 まず、なかなか難しいお題だと思うんですけど、経済学というのは、幅が広い学問だと思います。いろんな側面がある、というのが今の経済学で、だからある意味で、「いろんな関心のある人が経済学をやれる」、という面があります。これは伊藤元重先生からも、学生のときに言われたことです。
例えば、非常に数学的なところに関心があるなら数理経済学の分野で、現実の経済を数学的に解く、というものです。逆に、その反対でいうと、歴史に近い分野だと経済史で、「実際何が起こっていたか」、ということを古文書とかを読んで解読する、というのも経済学です。
それから、話をわざとあっちこっちにさせますけど、数理的なところでいけば、統計学に近いものは、データを分析して、現実に起こっている経済の事象を明らかにする。皆さんが経済学といったときにイメージしやすいのはこういう話だと思います。統計データを使って、「GDPがどう」とか、「物価がどう」とかということを分析する、と。今は統計学だけではなくて、コンピュータの発達でいろんなデータをまわしたりする、ということだと思います。
もう一つ、理論的な分析ということで、数学とは少し離れて、現実の経済の活動というのはかなり複雑なものなので、これを抽象的な理論モデルに落とし込んで、「実際の世の中はどんなふうに動いているのか」ということをモデルに立てる。それを使って、例えば、政府の政策を考えたり、あるいは、企業のあるべき戦略を考えたり、というようなことで、多面的に考えられると。
それぞれ一個一個学問の名前がついても良さそうなものが幅広く入っている、というのが経済学の特徴です。なので、経済学者の人でも、最初は数学的なことをやっていたけれども、途中で歴史のほうに変わる人もいますし、政策提言のほうに変わる人もいます。ということで、経済学者、あるいは経済を研究している人の中でも、分野を変えていくとか、自分に合った分野を選んでいくことが、かなり幅広くできる、という意味では、例えば、数学などを専攻している人に比べて、幅が広い、というのが、経済学の一つの特徴だと思います。