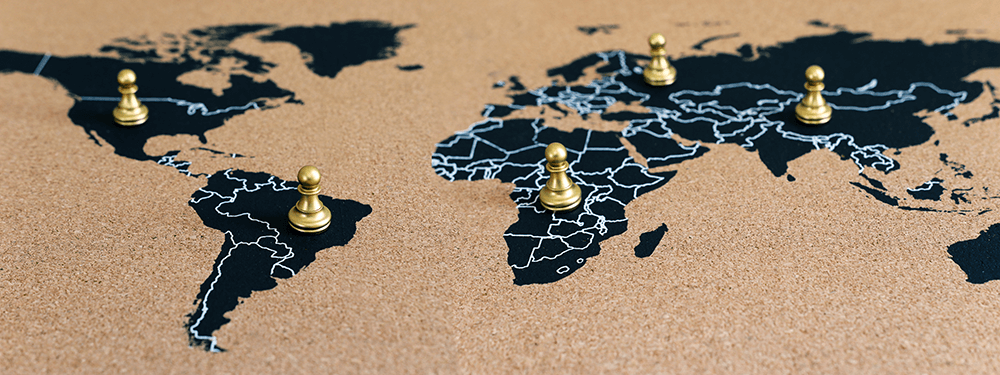●グローバル化の中で新興国の割合が倍に
今、ご紹介にあずかりました白石です。今日は「米中戦略的競争時代のアジアと日本」というテーマでお話ししたいと思います。
これはある意味で私自身の癖でもあるのですが、非常にマクロ的に世界を見たとき、少なくとも冷戦終焉以降、あるいは21世紀に入って、いわゆるグローバル化の時代の中で何が起こっているか、一言でいうと「多極化」だと思います。多極化という言葉自体に私は少し不満があるのですが、もう少しフワッとした言い方をすると、「富と力の分布が急速に大きく変わっている」ということで、その結果、先進国と新興国が出てきています。
これについてどういうことかをまずお話しします。少し資料が見えにくいかもしれませんが、申し上げたいことは極めて単純です。1990年ないし2000年と、2019年を比べると、非常にはっきりした違いが3つあります。1つは20世紀、つまり1990年にも、また2000年にも先進国が世界経済のだいたい80パーセントを占めていました。また、2000年までは「新興国」という言葉はなく、2001年から使われ始めました。20世紀の最後の頃では、途上国は20パーセントぐらいしか占めていませんでした。それが2019年になると、だいたい先進国が60パーセント、途上国・新興国が40パーセントになります。これだけシェアが動いたということが1つです。
2つ目ですが、“N.America”は北米のことで、北米とEU地域を合わせると、1990年、また2000年にも世界のシェアのだいたい60パーセントを占めています。それが2019年になると50パーセントを切っていきます。代わりにどこが伸びたかというと、最近の言葉でいうところの「インド太平洋」です。
それから3つ目ですが、インド太平洋の中では、日本は1990年、また2000年にもそれ以外のインド太平洋の国々を全部合わせたよりも大きかったのです。しかし、2019年には中国が、日本も含めたそれ以外の経済全部合わせたものと同じぐらいの規模になっています。この3つとも、皆さんは非常によくご存じのことだと思います。
●変わりつつある国際社会のパワーバランス
その結果、何が起こっているか。この表は、経済規模の大きいほうからトップ20の国を選んだものです。2000年にはまだ上から5つは全部いわゆる先進国のG...