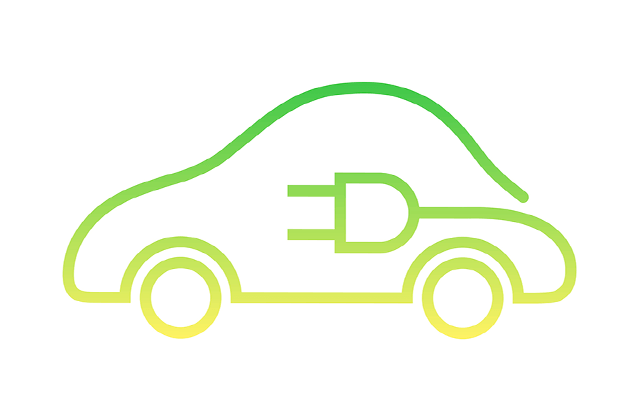●カイゼンか、ドラスティックな変化か
―― 今まで日本の場合は、例えば脱石炭については高効率石炭火力発電を進めたり、あるいは再生可能エネルギーについてはハイブリッドを進めるなど、ドラスティックな変化というよりは、「今までより良くする」という“カイゼン”的な取り組みでやってきたと思います。ですが、もはや“カイゼン”レベルではなく、ドラスティックに全てを変えていくというようにギアチェンジしたと見たほうがいいでしょうか。
小原 私は日本の強みの1つは“カイゼン”だと思います。一気に再生可能エネルギーにはもっていけません。今も述べたように(第2話)、電力供給の安定性は非常に重要です。今もエネルギー危機とまでいわれるように、石油にしろ天然ガスにしろ、化石燃料価格が非常に上がっている。そういった中で電力の安定供給、特に電力のバックアップといったことになると、どうしても天然ガスなどに頼らざるを得ない面があります。
そうした難しい状況の中で、日本としては、やはりエネルギー効率を上げていく必要があります。そうした技術革新は日本が非常に得意です。また同時並行的に、そのカイゼンも行う。そして同時に、新しいエネルギーである再生可能エネルギーへの転換も急ぐ。その全てが必要だと思います。
―― ありがとうございます。
●ガソリン車から電気自動車への転換
小原 CO2排出をどう削減していくかについて、きわめて大事になってくるのが「技術革新」です。「技術革新」を取り上げるとき、ポイントが2つあると思います。
1つは電気自動車(EV)です。独自動車大手メルセデス・ベンツの社長による「EVファーストからEVオンリーに動いていく」という言葉に象徴されるように、将来的には電気自動車がこれまでのエンジン自動車に取って替わるでしょう。そうした流れが今、できあがっていると思います。
COP26でもイギリスが「主要市場は2035年までに、世界は2040年までにエンジン車の販売を終了しましょう」と提案しました。こうした提案に対して、世界24カ国とアメリカのGMなど自動車メーカーが賛同しています。
今、電気自動車の市場はどうなっているかというと、世界の販売台数はテスラが圧倒的に世界一です。2021年は93万台という数字もあります。右の写真はもっとも売れている「モデル3」です。
...