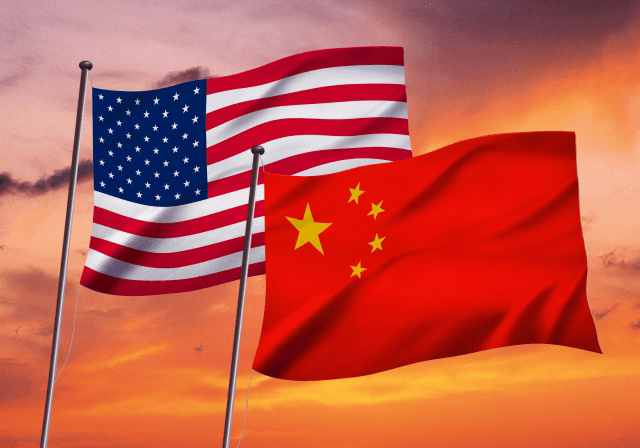●米中覇権争いの帰趨は決した
―― 前回、非常に重要なお話がありました。一つは、1979年がターニングポイントだったというお話です。ここで、サッチャーリズムの登場やホメイニ革命、鄧小平の改革開放等々が起きていたということですが、そこからちょうど40年あまり経て、今の状況があります。もし今が何かの転回点だとすると、現在のどういったものが次の時代をつくっていくのでしょうか。
中西 今回のウクライナ戦争が一番大きな意味を持つのは何か。私は、「グローバリゼーション」「グローバル化」というキーワードで考えてきたわけですが、もう一ついえるのは、このタイミングで起こったウクライナ戦争は、米中のグローバルな覇権争い、米中という超大国の覇権競争の帰趨を決する意味を持ったということだと思います。
―― 帰趨が決するわけですね。
中西 帰趨が決したと思います。これは大胆な言い方で、「ここまで言っていいのか」とお聞きになっている方には思われるかもしれません。いろいろな感想をお持ちいただいて結構ですし、それぞれがお考えいただきたいと思いますが、私はここで「中国、敗れたり」と思います。
中国がアメリカの覇権に挑戦するということは、あくまで未来に投影した“未来図”だったわけです。この大きな世界の大変動といわれるような秩序の転換を経ることなく、一応現状の中国経済が世界の中で占めている位置をキープできる状態が続いたという前提で、2030年、2035年、2040年代に米中の力関係がどうなるかといったことを、われわれは論じてきたわけです。
けれど、ウクライナ戦争がこのタイミングで起こりました。ロシアは世界経済からデカップリングされて当然です。そして、すでに現実にデカップルされています。さらに、そのロシアと中国がどういう距離感、スタンス、関係性を持つかということが今、問われている焦眉の国際政治、国政経済のテーマでもあります。
●「第三勢力」にどうアプローチするか
中西 今、世界は3分化されていると言われます。まずロシアの陣営で、そこには中国も入っていると見なされようとしています。それからアメリカを中心とする先進国、民主主義陣営。そして、そのいずれともはっきりと帰趨を定かにしない、旗幟を鮮明にしない第三勢力――インドがそうだといわれますが、ASEAN諸国、アフリカ諸国、中南米諸国、あるいはBRICSといわ...