●専門家さえも陥る「合理性の罠」
―― 本日は紀伊國屋書店(新宿本店)3階のアカデミック・ラウンジからのお届けということで、先生、この場所はどんなご印象ですか。
小原 素晴らしいですね。このアカデミック・ラウンジもそうなのですけれども、書店として本質的な魅力というのですか、そのようなものを感じる書店で、今日はこういう場所でお話ができるのを大変嬉しく思います。
―― 本当に知に囲まれた場所です。本日はこちらの『戦争と平和の国際政治』というご本についてお話を伺ってまいります。この本をもうお読みになった方も多くいらっしゃるかと思うのですけれども、私が最初に感じましたのは、現在起こっていることと国際政治の考えなり、議論なり、学問と政治ががっぷり四つになっていて、両面で理解ができるという大変有難い本だということです。限られた時間ですので、そのポイントを先生にお聞きしてまいりたいと思います。
最初に私が印象深かったのは序章の部分です。当然、大きな問題というとロシアによるウクライナ侵攻ですけれども、思い起こすと、戦争が始まる前の段階ないし始まった直後の段階で、「専門家」と呼ばれる方が読み誤ったという非常に印象深いお話を書いておられます。
例えば、先生、一番の読み誤りというと、まず戦争がそもそも起こるのかどうかというところですね。
小原 はい。私はロシアの専門家でもありませんし、軍事の専門家でも歴史家でもありません。ただ、外交の実務というものをやって、その後、理論を大学で勉強、研究してきたということもあって、そうした自分の経験だとか知識から、「これはどうしてそういうことになったのだろう」ということを考えてみたときに、序章にも書きましたが、一つは「合理性の罠」ということがあったのではないかということです。
これは国際政治を勉強されている方には特にそうだと思うのですが、国内社会と国際社会は全く違うわけです。
何が最も違うかというと、国内社会というのは中央政府があって、そのもとで一元化されたような「法の支配」というものがあるわけです。何か法に違反することがあると警察に捕まり、裁判を受けて、それなりの罰を受けるわけです。
ところが、国際社会に今、国内社会にあるような中央政府がないのです。世界政府もありません。国際...











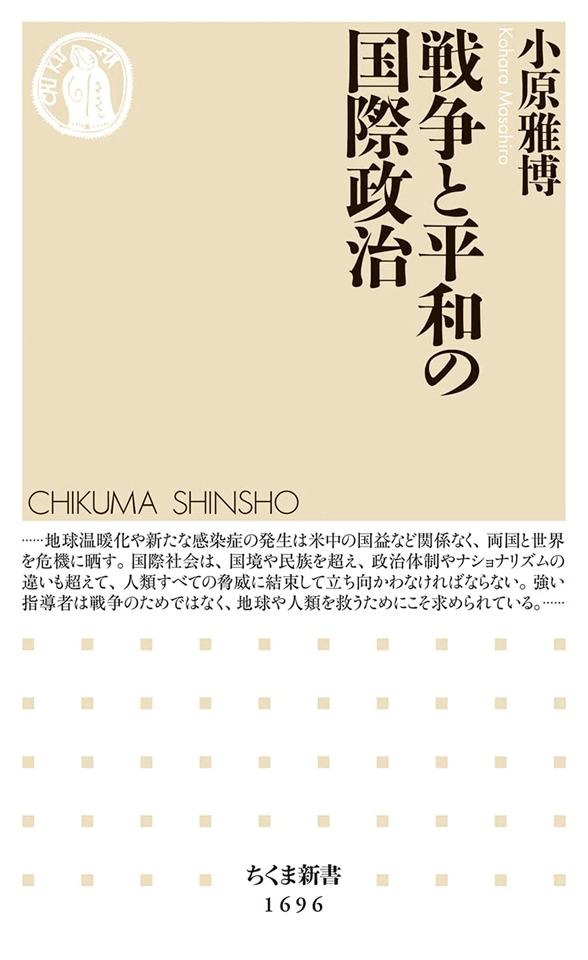

(小原雅博著、ちくま新書)