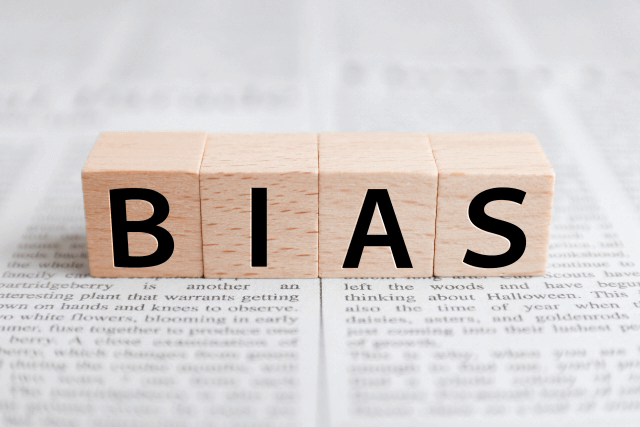●「アブダクション」は日常的に行われている原因の推定
次に、「アブダクション(仮説推論)」というものを取り上げてみたいと思います。アブダクションという言葉も、仮説推論という言葉もあまりピンと来ないかもしれないのですが、もっとも典型的にアブダクションが現れるのは原因の推定なのです。
私たちはあることを観察すると、半ば自動的にその原因を考えます。例えば、時計が止まってしまったときに「電池が切れたのかな」とか、友人が不機嫌な顔をしているときに「何か嫌なことがあったのか、嫌なことしてしまったかな」とか、あるいは地面が濡れているときに「雨降ったのかな」とかです。あるいは、自分が乗っているバスが急に止まったときに「赤信号で止まったのかな」「渋滞なのかな」「ガス欠かな」(ガス欠はあまりないでしょうが)とか、それからテストの点が資料に挙げたようなとき(よかったとき)、「猛勉強したからなのか」「カンニングしたからなのか」「簡単なテストだったのか」とか、そういういろいろな結果を観察すると、それをもたらした原因を考えたくなるわけです。
非常にこれも大事なことで、これ抜きに知的な人間とはいえないというくらい、ごく基本的な認知の機能です。
●「事前確率の無視」がもたらす、誤った原因の推定
実は原因の想定においても認知バイアスというものが出ています。これも非常に有名な問題で、ドイツの心理学者のゲルト・ギゲレンツァーという方が使った問題です。
40代の女性の乳癌の比率は1パーセントである。乳癌を持つ人にマンモグラフィー検査を行うと、80パーセントの確率で乳癌であるという結果が出る。「乳癌を持つ人に」というのはどういう意味かというと、乳癌だということが生検などを使って、もう分かっている人という意味です。一方、乳癌でないということが分かっている人に同じ検査を行うと、9.6パーセントの確率で乳癌であるという結果が出ます。擬陽性ということです。ある40代の女性がこの検査で陽性、つまり乳癌であるという結果が出たのですが、この人が実際に乳癌である確率はどれほどかという問題です。
どうでしょうか。これはそんなに簡単ではないので、すぐに答えは出ないので...