テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
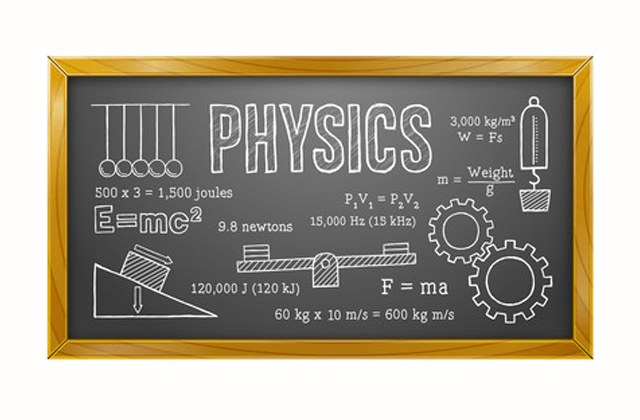
眠れなくなるほど面白い身近な物理
少年少女のころ、毎日のように新しい発見があり、驚きの連続だったのではないでしょうか。そうしたことが大人になるにつれて、だんだんとなくなってしまったとすれば、残念なことです。
忙しい日々を送る現代人には仕方のないことかもしれませんが、そんな中、子どものころの好奇心をすこしばかり取り戻して、身近な生活を眺めてみませんか。たとえば、空はどうして青いのだろう。夕方の空はなぜ赤いのか。そもそもどうして色があるのか。今回のコラムでは、そうした身の回りのちょっとした謎について、『眠れなくなるほど面白い 図解 物理の話』(長澤光晴著、日本文芸社)をもとにして、いくつか考えてみたいと思います。
著者の長澤光晴氏は東京電機大学工学部自然科学系列・工学研究科物質工学専攻の教授で、長澤氏の研究室では「物質の性質と特徴を基礎的な立場から解明する研究」を行っています。
光は電磁波という波の一種です。それぞれの色には波長があって、一番長いのは赤、逆に短いのは青系の光です。そして、青色は波長が短い分、飛んでいきやすいという特徴があります。そのため、他の色より私たちのもとに届きやすく、それで空は青く見えるのです。
青は赤に比べて8倍もレイリー錯乱しやすいのだそうです。つまり、光が地面に届くまでの距離が長くなるほど青は私たちのもとに届きにくくなるということです。それは、逆に波長の一番長い赤は届きやすくなるということですので、夕方の空は真っ赤に染まるというわけです。
ゴルフ好きの方はご存知かもしれませんが、表面のくぼみは「ディンプル」といってボールをより遠くへ飛ばすための工夫です。ボールを打ち飛ばすと空気抵抗が生まれます。この空気抵抗を極力抑えるためには、できるだけボールに沿って空気が流線を描くように工夫する必要があります。
ディンプルをつくることで、空気はそのくぼみに吸われるようにしてボールの表面を通っていくようになります。つまり、ディンプルが空気の流れを整えてくれているわけです。それによって抵抗が減り、ボールは遠くまで飛ぶようになります。ちなみにこの技術は水泳ウェアの開発などさまざまなスポーツ分野で活用されています。
このように、物理の知はいたるところにひそんでいると言っていいでしょう。ふと不思議に思ったら面倒くさがらずに調べたり考えたりする癖をつけてみましょう。しくみが分かると世界の見え方がガラッと変わります。
忙しい日々を送る現代人には仕方のないことかもしれませんが、そんな中、子どものころの好奇心をすこしばかり取り戻して、身近な生活を眺めてみませんか。たとえば、空はどうして青いのだろう。夕方の空はなぜ赤いのか。そもそもどうして色があるのか。今回のコラムでは、そうした身の回りのちょっとした謎について、『眠れなくなるほど面白い 図解 物理の話』(長澤光晴著、日本文芸社)をもとにして、いくつか考えてみたいと思います。
著者の長澤光晴氏は東京電機大学工学部自然科学系列・工学研究科物質工学専攻の教授で、長澤氏の研究室では「物質の性質と特徴を基礎的な立場から解明する研究」を行っています。
空はどうして青いのだろう
まずは冒頭に挙げた謎から始めます。空はどうして青いのだろう。太陽の光は白色の光ですが、これは青や緑や赤色などが重なってできています。いろいろな色があることは7色の虹を思い出すとわかりやすいですね。光は電磁波という波の一種です。それぞれの色には波長があって、一番長いのは赤、逆に短いのは青系の光です。そして、青色は波長が短い分、飛んでいきやすいという特徴があります。そのため、他の色より私たちのもとに届きやすく、それで空は青く見えるのです。
夕方の空はなぜ赤いのか
夕方になるとなぜ赤くなるのかということも考えてみましょう。夕方は昼間にくらべて太陽の光が地面に届くまでの距離が長くなります。そのため、飛んでいきやすい青は地面に届く前に大気中の物質にぶつかってどこへ飛んで行ってしまうのです。この進路変更をレイリー錯乱といいます。青は赤に比べて8倍もレイリー錯乱しやすいのだそうです。つまり、光が地面に届くまでの距離が長くなるほど青は私たちのもとに届きにくくなるということです。それは、逆に波長の一番長い赤は届きやすくなるということですので、夕方の空は真っ赤に染まるというわけです。
ゴルフボールの表面のくぼみ
もうひとつ紹介します。今度は空の色の話とは打って変わって、ゴルフボールについてのお話です。皆さん、ゴルフボールの表面のくぼみのわけを知っていますか。これも物理で説明できます。ゴルフ好きの方はご存知かもしれませんが、表面のくぼみは「ディンプル」といってボールをより遠くへ飛ばすための工夫です。ボールを打ち飛ばすと空気抵抗が生まれます。この空気抵抗を極力抑えるためには、できるだけボールに沿って空気が流線を描くように工夫する必要があります。
ディンプルをつくることで、空気はそのくぼみに吸われるようにしてボールの表面を通っていくようになります。つまり、ディンプルが空気の流れを整えてくれているわけです。それによって抵抗が減り、ボールは遠くまで飛ぶようになります。ちなみにこの技術は水泳ウェアの開発などさまざまなスポーツ分野で活用されています。
このように、物理の知はいたるところにひそんでいると言っていいでしょう。ふと不思議に思ったら面倒くさがらずに調べたり考えたりする癖をつけてみましょう。しくみが分かると世界の見え方がガラッと変わります。
人気の講義ランキングTOP20










