テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
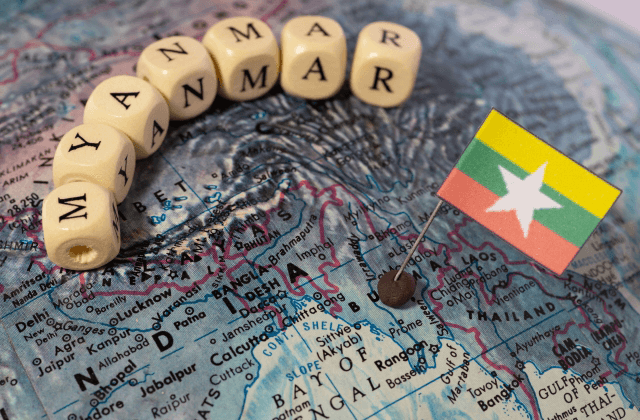
『ミャンマー現代史』で鳥瞰する軍事化と民主化のクロニクル
2021年2月1日、ミャンマーで勃発した軍事クーデターのニュースが世界中を駆けめぐりました。
世界中で民主化が進む現代において、ノーベル平和賞受賞者でミャンマーの事実上の最高指導者であるアウンサンスーチー氏を中心とした政府中枢が、ミャンマー軍最高司令官のミンアウンフライン上級大将とした軍に一発の銃弾も放つことなく掌握されたこと。さらに、軍事クーデター後に全国に広がったが抵抗運動に参加する市民に軍が容赦なく実弾を発砲したことに、数多くの人がショックを覚えたことでしょう。
しかし、ニュースを聞いて「軍事クーデターが起こった」という事実は認識できたとしても、東南アジアの西に位置するミャンマーでいったい何が起こっているのか、なぜそうなったのか、そして現状はどうなっているのかなど、よくわからない人も多いのではないでしょうか。そのような疑問に真正面から取り組んだ一冊の新書、『ミャンマー現代史』が刊行されました。
本書において中西先生は、「スーチーはなぜクーデターを防げなかったのか」「市民に暴力を振るってまで軍はミャンマーをどうしたいのか」「民主化勢力に勝機はあるのか」「国際社会は事態をなぜ収束させられないのか」といった問いを立て、「たとえ朧ろげではあっても、ミャンマーの行方を見通すこと」を課題としています。
そのために、序章「ミャンマーをどう考えるか」では、ミャンマーという国をどうみるのかについて、中西先生の基本的な視座を提示しつつ、本書が主に対象とする1988~2011年以前の時代について大きな流れがまとめられています。
(1)1988~2011年:タンシュエ(軍人・政治家)
(2)2011~2016年:テインセイン(軍人・政治家)
(3)2016~2021年:アウンサンスーチー(民主化運動指導者)
(4)2021年~現在:ミンアウンフライン(軍人・政治家)
まず1988~2011年、タンシュエ氏が最高権力者であった時代が、第1章「民主化運動の挑戦(1988-2011)」と、第2章「軍事政権の強権と停滞(1988-2011)」です。1988年から始まった民主化運動がアウンサンスーチー氏を政治指導者とし民主化を求める大衆運動へと変容した一方で、軍と民主化勢力という基本的な対立構図が生まれた時代。なぜ国民から反発を受け、欧米の制裁で国際的に孤立し、経済を停滞させながらも、23年間も軍事政権が続いたのか、その理由を探究しています。
つぎの2011~2016年、テインセイン氏が最高権力者であった時代は、第3章「独裁の終わり、予期せぬ改革(2011-2016)」です。軍事政権からの転換といえる2011年の民政移管に焦点を当てると同時に、5年間続いたテインセイン政権下の政治と経済を検証しています。
つづく2016~2021年、アウンサンスーチー氏が最高権力者であった時代は、第4章「だましだましの民主主義(2016-2021)」です。ミャンマーを民主化に導く指導者として世界中から期待されたアウンサンスーチー氏が最高権力者の座に就いた5年間を、スーチー政権の実態を通しても論じています。
そして2021年~現在、ミンアウンフライン氏が最高権力者である時代は、第5章「クーデターから混迷へ(2021-)」です。冒頭でも述べた、2021年2月1日に起きたクーデターを検討しつつ、その後の余波として混迷が続くミャンマーの現状を考察しています。
以上のように本書の主軸は、23年間続いた軍事政権のあと、2011年から進んだ民主化・自由化・市場経済化・グローバル化の試みがクーデターによって頓挫した2022年現在から振り返る、約35年間のミャンマー現代史です。
中西先生は「断言してもよい。この国(ミャンマー)がクーデター前の状況に戻ることはない。混迷含みの新たな時代に突入する。だが、その新たな時代がどういったものになるのかは、いまだに像を結ばない」と述べています。エキスパートの中西先生をもってしても、ミャンマーが予断や想像すらおよばない、厳しい状況下にあることがうかがえます。
ミャンマーは同じアジア地域に属し、日本と縁が深い国です。しかしながら、このままではやがて多くの人が約5000キロも離れた紛争国として忘れてしまいかねません。「忘却でも単純化でもなく、現実を変えるための冷めた他者理解が必要とされていると思う。現状の救いのなさに戸惑うことになるかもしれないが、それでも、変容するアジアと世界を前にした大事な心構えだろう」と、中西先生は説いています。
個人であっても国であっても、歴史に学ぶことはとても大事です。ただ、そのなかでも現在と地続きの現代史と真正面から向き合うことは、ときに痛みを伴うため、簡単なことではありません。それだけに、現在までの約35年間と真摯に対峙した本書は、グローバリゼーションや民主主義の恩恵と弊害を読み解くための合わせ鏡としての現代史にもなりえる、大変貴重な一冊なのです。まさに混沌とする今の時代から未来を考えるために、ぜひ本書『ミャンマー現代史』を手に取り、ページをめくってみてください。
世界中で民主化が進む現代において、ノーベル平和賞受賞者でミャンマーの事実上の最高指導者であるアウンサンスーチー氏を中心とした政府中枢が、ミャンマー軍最高司令官のミンアウンフライン上級大将とした軍に一発の銃弾も放つことなく掌握されたこと。さらに、軍事クーデター後に全国に広がったが抵抗運動に参加する市民に軍が容赦なく実弾を発砲したことに、数多くの人がショックを覚えたことでしょう。
しかし、ニュースを聞いて「軍事クーデターが起こった」という事実は認識できたとしても、東南アジアの西に位置するミャンマーでいったい何が起こっているのか、なぜそうなったのか、そして現状はどうなっているのかなど、よくわからない人も多いのではないでしょうか。そのような疑問に真正面から取り組んだ一冊の新書、『ミャンマー現代史』が刊行されました。
ミャンマー現代史のエキスパート・中西嘉宏先生
著者である中西嘉宏先生は、京都大学東南アジア地域研究研究所准教授。専攻はミャンマー政治、東南アジア地域研究、比較政治学と、まさにミャンマー現代史のエキスパートです。本書において中西先生は、「スーチーはなぜクーデターを防げなかったのか」「市民に暴力を振るってまで軍はミャンマーをどうしたいのか」「民主化勢力に勝機はあるのか」「国際社会は事態をなぜ収束させられないのか」といった問いを立て、「たとえ朧ろげではあっても、ミャンマーの行方を見通すこと」を課題としています。
そのために、序章「ミャンマーをどう考えるか」では、ミャンマーという国をどうみるのかについて、中西先生の基本的な視座を提示しつつ、本書が主に対象とする1988~2011年以前の時代について大きな流れがまとめられています。
ミャンマー現代史クロニクルと4人のキーマン
つづく本論となる各章では、軍事クーデターの背景にせまるべく、2021年の政変をひとつの政治経済変容の終着点とみなして、1988年からはじまる約35年間のミャンマー現代史が描かれています。具体的には以下の4人の国家最高権力者たちを中心としたクロニクルで構成され、論証へと進んでいます。(1)1988~2011年:タンシュエ(軍人・政治家)
(2)2011~2016年:テインセイン(軍人・政治家)
(3)2016~2021年:アウンサンスーチー(民主化運動指導者)
(4)2021年~現在:ミンアウンフライン(軍人・政治家)
まず1988~2011年、タンシュエ氏が最高権力者であった時代が、第1章「民主化運動の挑戦(1988-2011)」と、第2章「軍事政権の強権と停滞(1988-2011)」です。1988年から始まった民主化運動がアウンサンスーチー氏を政治指導者とし民主化を求める大衆運動へと変容した一方で、軍と民主化勢力という基本的な対立構図が生まれた時代。なぜ国民から反発を受け、欧米の制裁で国際的に孤立し、経済を停滞させながらも、23年間も軍事政権が続いたのか、その理由を探究しています。
つぎの2011~2016年、テインセイン氏が最高権力者であった時代は、第3章「独裁の終わり、予期せぬ改革(2011-2016)」です。軍事政権からの転換といえる2011年の民政移管に焦点を当てると同時に、5年間続いたテインセイン政権下の政治と経済を検証しています。
つづく2016~2021年、アウンサンスーチー氏が最高権力者であった時代は、第4章「だましだましの民主主義(2016-2021)」です。ミャンマーを民主化に導く指導者として世界中から期待されたアウンサンスーチー氏が最高権力者の座に就いた5年間を、スーチー政権の実態を通しても論じています。
そして2021年~現在、ミンアウンフライン氏が最高権力者である時代は、第5章「クーデターから混迷へ(2021-)」です。冒頭でも述べた、2021年2月1日に起きたクーデターを検討しつつ、その後の余波として混迷が続くミャンマーの現状を考察しています。
変容するアジアと世界を前にした心構えを説く一冊
さらに、第6章「ミャンマー危機の国際政治(1988-2021)」と、終章「忘れられた紛争国になるのか」では、約35年間のミャンマーに対する世界や日本が行ってきた動向を概観すると同時に、ミャンマーのこれからに対して今だからこそ民主的な理念を共有した国々や日本ができることを省察しています。以上のように本書の主軸は、23年間続いた軍事政権のあと、2011年から進んだ民主化・自由化・市場経済化・グローバル化の試みがクーデターによって頓挫した2022年現在から振り返る、約35年間のミャンマー現代史です。
中西先生は「断言してもよい。この国(ミャンマー)がクーデター前の状況に戻ることはない。混迷含みの新たな時代に突入する。だが、その新たな時代がどういったものになるのかは、いまだに像を結ばない」と述べています。エキスパートの中西先生をもってしても、ミャンマーが予断や想像すらおよばない、厳しい状況下にあることがうかがえます。
ミャンマーは同じアジア地域に属し、日本と縁が深い国です。しかしながら、このままではやがて多くの人が約5000キロも離れた紛争国として忘れてしまいかねません。「忘却でも単純化でもなく、現実を変えるための冷めた他者理解が必要とされていると思う。現状の救いのなさに戸惑うことになるかもしれないが、それでも、変容するアジアと世界を前にした大事な心構えだろう」と、中西先生は説いています。
個人であっても国であっても、歴史に学ぶことはとても大事です。ただ、そのなかでも現在と地続きの現代史と真正面から向き合うことは、ときに痛みを伴うため、簡単なことではありません。それだけに、現在までの約35年間と真摯に対峙した本書は、グローバリゼーションや民主主義の恩恵と弊害を読み解くための合わせ鏡としての現代史にもなりえる、大変貴重な一冊なのです。まさに混沌とする今の時代から未来を考えるために、ぜひ本書『ミャンマー現代史』を手に取り、ページをめくってみてください。
<参考文献>
『ミャンマー現代史』(中西嘉宏著、岩波新書)
https://www.iwanami.co.jp/book/b609322.html
<参考サイト>
京都大学東南アジア地域研究研究所
https://kyoto.cseas.kyoto-u.ac.jp/
『ミャンマー現代史』(中西嘉宏著、岩波新書)
https://www.iwanami.co.jp/book/b609322.html
<参考サイト>
京都大学東南アジア地域研究研究所
https://kyoto.cseas.kyoto-u.ac.jp/
人気の講義ランキングTOP20
実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない
長谷川眞理子










