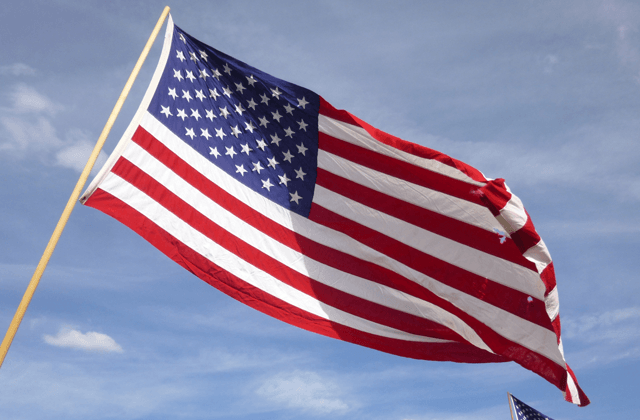
アメリカとロシアが揺さぶるユーラシア地政学大変動時代
日露関係の前進とプーチン大統領のユーラシア地政学
2016年末、ロシアのプーチン大統領来日は「トランプ景気」への注目の陰に隠れた格好になってしまいました。しかし、安倍首相の提案した「8項目の経済協力」に沿う事業については合意され、新年からは具体化が始まっていく様子。天然ガスパイプラインの実現は、まさに日露の架け橋となってくれるのでしょう。しかしながら、「日露の関係は前進している」とプーチン大統領が笑顔を見せるのは単に経済戦略のみならず、ユーラシア地政学という大きな枠組みあってのことだ、と歴史学者で東京大学名誉教授の山内昌之氏は指摘されています。ロシアとの接近が、日米同盟・日米関係にどんな影響を与えていくのかも忘れてはなりません。
プーチン大統領はすでに2016年6月、「大ユーラシア・パートナーシップ」のデザインを打ち出しています。旧ソ連5カ国で構成される「ユーラシア経済同盟」に中国やインド、イランなども取り込んだ壮大な構想です。その目的は「米国の影響から外れた巨大経済圏を形成」することに他ならないのですが、新大統領トランプ氏は、これに対応するような大きな戦略を持っているのでしょうか。
トランプ氏の最優先する中東課題は、IS解体
まず、トランプ氏の中東戦略から見ていくと、選挙中から「アサドは嫌いだが、IS戦闘員を殺している」と評価する発言がありました。また、中東のみならず「他国のトラブルにアメリカがこれ以上巻き込まれるのはごめん」というのがトランプ氏のスタンスでもあります。それらに基づく方針は「イスラム国解体が一番重要で、そのためにはアサド政権とも協力する」ことです。そのため、トランプ氏はすでにシリアのアサド大統領やイランのハメネイ師と並んで、ロシアのプーチン大統領にもディール(交渉、取引)を呼び掛けています。その内容は、簡単にいえば「君たちの既得権益は認める。だから、アメリカの優位性とイスラエルの特殊権益も認めろ」というもの。これが自国民から理解を得られるかどうかは疑問ですが、これまで日々およそ1200万ドルを費やしてきた軍事費を国内のテロ防止や雇用創出に充てるといったポピュリズム手法を用いることは間違いないでしょう。
トランプ・ディールによって、中東が近代史において初めて米欧など大国の監視者を失うことになる事態を、山内氏は重く見ています。権力の真空状態をもたらしてくれるトランプ氏の政策は、ジハーディストたちにとって極めて歓迎すべきものなのです。
中東情勢が揺れる中、ユーラシア地政学において最も注目される国は日本だ、と山内氏。現在、プーチン構想を最も悩ませている国が中国である以上、日本との国交正常化や経済協力は、プーチン大統領にとって何より大切だからです。
激動する国際情勢の中で日本が理性を保つためには
日本が理性的な平和国家であることは、激動の中東情勢と比べるまでもなく、米欧と比べても際立っています。その理由の一つを、ヨーロッパの識者たちは「象徴天皇制が国民統合の中心にあるから」と見ているのだそうです。天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議に加わっている山内氏は、「トランプ氏とプーチン氏という個性的な政治家が起こすユーラシア地政学の変動の渦に『ご退位』の問題を巻き込まない努力」を常に念頭に置いているといいます。
トランプ・ディールやプーチン旋風などの「大変動」を起こす力に対比してみると、2016年8月に発表された天皇陛下のおことばも、その意味を深めるかもしれません。トランプ現象やユーラシア政治力学の変化に心を乱さず、冷静な議論を進めていくことこそが、明日の日本が生き残るための知恵に他ならないのかもしれません。山内氏の談話に、その決意を見る思いがします。
人気の講義ランキングTOP20
『種の起源』…ダーウィンとウォレスの自然淘汰の理論
長谷川眞理子







