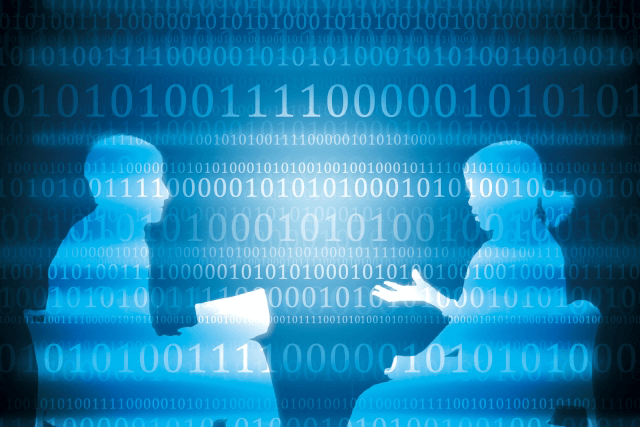●「課題解決コンペ」でイノベーションを起こす
司会:実は私たちで、技術研究の長期未来予測という体系的な検討を行っています。このまま何もせずに黙っていると、2030年までに約780万人の生産年齢人口減少は自明です。しかし先ほどから申し上げているAIやロボットが産業化できれば、10年後のGDPは約50兆円、年率でいうと0.6パーセントの押し上げはあるだろうと思われます。さらに新しい雇用に関しては、およそ500万人の新規雇用が創出できるはずである。こういう検討結果を公表しています。
とにかく、ブルーオーシャンが開きつつあるという認識はその通りだと思いますので、次のテーマに移りましょう。「日本は、このチャンスにどう立ち向かうべきなのか」ということです。これだけのいろいろなことが10年後には起こり得るとされる中で、このチャンスをつかむために、私たちは何をしなければならないのか。このテーマでご提案いただければと思います。小宮山先生、お願いします。
小宮山:今の日本の弱点をどうするかという話でいえば、二つのことが重要です。一つは、日本では大企業が強すぎることです。こういうところは、先ほどの防災ロボットをつくるにしても、リスクを取って思い切って前に進むことをあまりやらないのです。だから、若くてやる気のある人たちに、社外でベンチャーをつくらせてそこに出資するという形で、もっと思い切ったことをやっていけないだろうか。これが一つ目の提案です。
もう一つ注目したいのは、コンペです。DARPA(国防高等研究計画局)がロボットのコンテストをやったり、アマゾンもコンテストをやったりしています。そういう海外でのコンペに参加するのもいいのですが、私は日本で賞金が付いたコンペをたくさんやればいいと思っています。
一例として、北海道の上士幌町で2016年10月に行われたイベント(Japan Innovation Challenge 2016)があります。雪山で遭難した人がいるという前提で、マネキンを遭難した人に見立て、これを見つけると50万円がもらえるというものです。そこに、毛布や薬などの入った3キログラムのキットを届けると、500万円がもらえる。さらにそのマネキンを下ろしてこられたら(ずたずたになっては駄目ですよ)、2,000万円がもらえるというコンテストをやっています。2016年は10チームが参加して、2チームだけが見つけるところまでいきました。ドローンか何か...