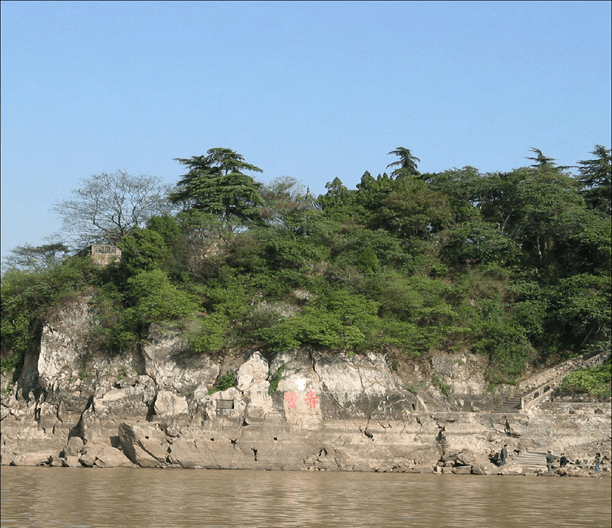●袁術と孫氏の自立
こんにちは。早稲田大学文学学術院教授の渡邊です。今日は「江東の自立」というテーマで、孫権 (ソンケン)の話をさせていただくことになります。
『三国志』には、まず父親の孫堅(ソンケン)が登場します。孫堅は、「黄巾の乱」の後、董卓と反董卓連合が戦った頃から活躍した強い武将です。彼は董卓を破り、洛陽に一番乗りしていった時に、皇帝の玉璽を手に入れました。
その玉璽はやがて袁術 (エンジュツ)の手に渡ることになるのですが、それによって彼の自立を促すわけです。しかし、なぜ袁術の手に渡ったのかというと、孫堅が兵を挙げた時にお金を出したのが袁術だったからです。孫堅が死んだ後を継いだ孫策も袁術によって支えられますが、むしろ奴隷扱いを受けます。各地で戦っては手に入れた拠点を横取りされるということが繰り返されたのです。
ところが、その袁術が皇帝を称したことをきっかけとして自立をしていきます。孫策は袁術から離れたことによって、周瑜 (シュウユ)という中国の江南地方を代表する名家の協力を得て、江東という長江の下流域を支配下に入れることができたのです。
●孫氏と江東の地方豪族たち
孫氏はそれほど名門の家ではありませんでした。呉の北東部、現在の杭州近辺には「呉の四姓」と呼ばれる大豪族たちがいましたし、昔は越と呼ばれた国には「会稽の四姓」という豪族たちもいました。呉の四姓や会稽の四姓に比べると、孫氏は小さな家としてばかにされていたのです。
そういう状況の中で、孫策は呉の四姓の筆頭である陸抗(リクコウ)の家を虐殺してしまったため、支配はなかなか安定しませんでした。漢との戦いの最中、曹操が袁紹と激しく戦う隙をついて都を襲い、献帝を拉致しようと孫策は考えていたのですが、暗殺されて亡くなってしまいます。自分の支配地で暗殺されたのですから、支配がいかに安定しなかったかが分かります。
「覇権の争いでは劣るものの、江南の統治にかけては俺よりも優れている」と孫策に言われていたのが、弟の孫権です。陸抗の一族を殺した時にまだ幼かった彼は、手が汚れていないため、江東の人々との和解が可能になるということです。
実際に孫権は、懸命に名士を登用していきます。張昭(チョウショウ)や周瑜が中心となって、次々に名士を呼んできました。諸葛亮の兄である諸葛瑾 (ショカツキン)なども、孫策...