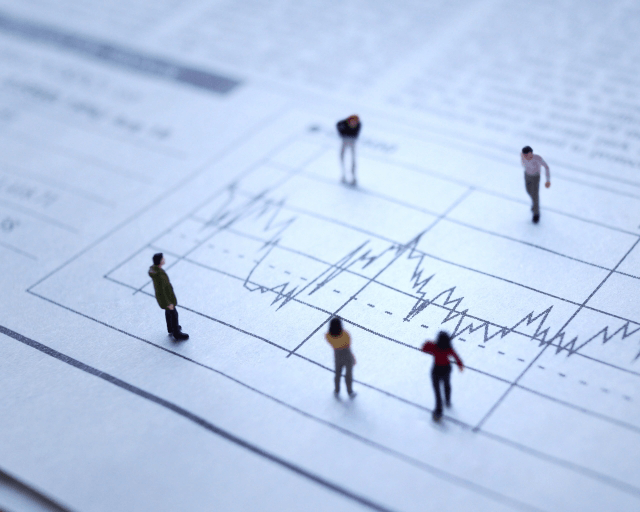●経済再開と感染拡大の防止のバランスをいかに取るか
―― はい。最後の問題になりますが、先ほどのご指摘で、専門家組織の中に経済学の専門家を含めるという話がありました。これから問題になるのが、感染の拡大防止を目指す一方で、自粛などによって打撃を受けた経済の回復をどのように両立していくかという点です。この点に関して、今後どのように考えていけば良いと思われますか。
曽根 現在、特に槍玉に挙げられているのは、東京・新宿におけるホストクラブやあるいはライブハウスなどです。そういったところは、三密の状態で、唾を飛ばすなどしてそれを吸い込みやすいという状況が生まれやすいことは確かです。しかし、実はそれ以外の場所でも同じような状況はつくられていて、感染は拡大しています。
現在までに分かっていることに基づいて判断するならば、リスクが非常に高そうな場所での営業は当面やめてもらう、自粛してもらうという、ピンポイントの政策はあり得ると思います。例えば、東京都と岩手県では全く状況が異なるので、本当にリスクが高そうな場所にのみ、休業や自粛してもらうのです。
そうした措置を取った場合、補償をどうするかというのは厄介な問題です。東京都も財源をかなり使い尽くしてしまい、国の財政も逼迫してきている。こうした状況で、補償問題というのは、例えば、天災が起きたときに補償するのかという問題とも大きく関わることなのですが、経済学者的な一つのアイディアとしては、営業を許可する代わりに、営業に対する税金(例えばコロナ税)をかけるという案があります。環境税と同じようなロジックの話です。
こうしたシステムについて、これから考えていかなければなりません。一律全員に補償するのは難しい。一方、二者択一ではないのですが、つまり、全てロックダウンして、経済もストップして、接触禁止にするという選択と、経済活動を再開してフル活動させるという選択の間には、さまざまな選択肢があるのです。この間に存在する最適なオプションに関しては、さまざまな人が試算して検討しています。自粛と経済活動の再開のバランスの最適な組み合わせに関する試算がいくつかあるので、先ほど小宮山先生が指摘されたように、ABCなどのプランを比較して判断するのも、一つの手だと思います。
●蓄積された知識を生かし、リスクを最小限に抑えた経済活動の再開を
...