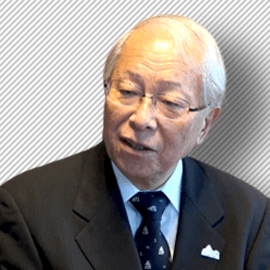●武田、北条氏から学んだ領地経営の方法
―― (徳川家康と)武田との関係ですが、本能寺の変が終わった後、甲斐と信濃を攻略して自分の領地にしていくことになります。先生がおっしゃるように、そこで武田の遺臣などもずいぶん召し抱えました。では、領国の統治について、統治法などで武田から影響を受けたことはあるのでしょうか。
小和田 領地経営という点から見ると、武田の場合は有名な「信玄堤」というものがあります。河川の制御、要するに洪水をいかに防ぐかといった点で、いわゆる「甲州流川除(かわよけ)法」を家康は結構学んだのでしょう。後に有名な伊奈忠次など、河川対策に長けた人を登用しています。
それからもう一つ、甲斐には金山がたくさんありました。そこから、おそらく金山収入のようなものが大事だということを武田から学んだと思います。その点で象徴的なのは大久保長安です。もともと武田の家臣だったのですが、武田が滅びた後、自分の家臣に取り込み、石見銀山や佐渡金山の奉行のような職を任せています。そういう点から、武田から学んだのは、いわゆる錬金術的なことが結構大きいのではないかと思います。
さらに加えると、取り込んだ(武田の武士)800人のうちほぼ1割を家臣の井伊直政につけた。武田のいわゆる「赤備え」、つまり旗や鎧を赤に統一した軍団ですが、彼らを井伊直政につけたことで、「井伊の赤備え」ができたわけです。
これらを見ると、武田から受けた影響は、家康のその後の発展にかなり大きな役割を果たしています。
―― 自分が領国にしたところからの影響ということでは、(武田の)次に小田原攻めがあります。秀吉に命じられて、これまでの領地から「関八州(関東)」への国替えとなりました。北条氏も領国統治では有名な大名ですが、こちらの影響はあるのでしょうか。
小和田 北条氏からの影響としては、北条氏がかなり先進的に行っていた検地があります。太閤検地の時と重なりますが、家康独自の検地を行う基礎として、検地の方法は学んだでしょう。
もう一つ、北条氏の領地では街道整備と伝馬制が進んでいました。そうした彼らの進んだやり方を家康は後の東海道整備や伝馬制度にうまく取り入れています。
私はよく「信長と家康の違いは何か」という質問を受けます。信長は自分に敵対した者に対しては徹底的な排除を行いましたが、家康はむしろ自...