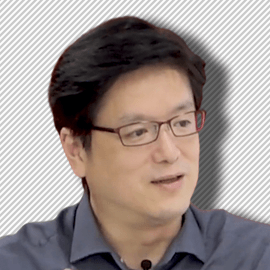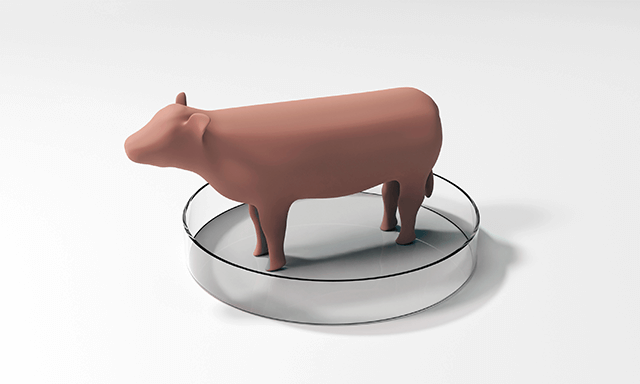●いかに牛肉の味を再現するか、カギは鉄分にあり
―― 今この培養肉を見た多くの方が思っていらっしゃると思うのですが、先生はこれを召し上がったわけですよね。
竹内 はい。これをそのものではないのですが、別の形のものは食べました。
―― どんな感じなのですか。
竹内 予想はしていたのですが、食感としては期待以上に噛み応えがありました。ゼリー状のものなので、噛んでもすぐなくなっちゃうのではないかと僕は思っていたのですが、意外と残っていて、それは期待とはちょっと違っていました。期待通りだったのは、味がなかったことです。牛肉の細胞を大量に培養して牛肉の組織を作ったのですが、牛肉の味はなかったということです。
では、牛肉以外の味としてはどういうものがあったかというと、おそらく培養液由来だと思うのですが、しょっぱさです。意外とほのかなしょっぱさがあって、このままご飯につけて食べたらおいしいのではないかという味ではありました。
あとは、どこから来たのかまだ分からないのですが、うま味がありました。ただ、牛肉の味はなかったので、培養する中でどうやって牛肉の味を出していくかということが基礎研究としての課題なのではないかと思っています。
その中で重要なのは、やっぱり脂ももちろんあるのですが、鉄分だと思っています。鉄分はまさに赤身にも通じる部分があります。赤身を作るにはどうしたらいいかということで、1つのヒントとしては、例えば培養中に、筋肉を基本的に僕らは動くものとして使っているわけです。そうなると、動きや力をずっとかけた力学的な負荷のあるような状態、あるいは一定の期間負荷をかけたような状態で培養するのがいいのではないかということで、培養中に電気刺激をかけてみました。そうすると、筋繊維の数とかサルコメアの量がグッと増えるということが分かってきました。
なので、今は電気刺激を例に取ったのですが、いろいろな培養のコンディションを変えることによって筋肉の成熟度が変わってくるのではないかと僕らは思っています。そのあたりを調整していこうというのが1つです。
●分厚い培養肉を作るための課題は「養分の浸透」
―― 今、実際に作ったところから電気刺激などで行うというお話がありましたが、他...