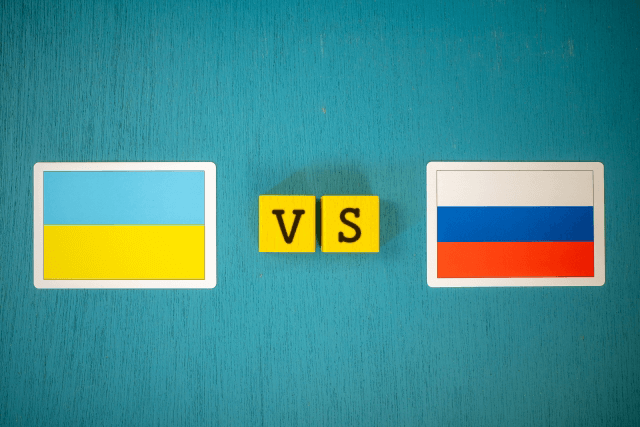●武器の有償・無償の問題と「ピュロスの勝利」の意味
皆さん、前回(第1話)は、今のウクライナ戦争を考える上で「ピュロスの勝利(ピュロニアン・ビクトリー)」という言葉について少しお話ししました。
どちらが勝ってもピュロスの勝利なのだろうというのはこういうことです。ウクライナは東部領土のもともと占領されていた2州に加えて他の2州を合わせた東部4州のかなりの部分が占領されたというダメージがあります。さらに、それに付随して産業が破壊されました。それから都市において企業やサービス業、情報産業、何であれその企業のビルが破壊されてなかなか稼働していません。すなわち、平和がよみがえったところですぐに国民が戻るべき仕事場があるわけでもないし、雇用があるわけでもないのです。
そして工場が直ちに稼働するわけではありません。したがって、仮にウクライナが勝利という形式で終わったとしても、この勝利が、ただちに平和がよみがえるということや国民が戻るべき企業や工場がそこで健在だということを意味しないというつらさ、厳しさがあるわけです。
武器にしましても、欧米から現実に無限の援助を必要としておりますし、戦闘機以外のたくさんの武器が、ほぼウクライナの希望する形で入ってきております。その中でも、特にウクライナ軍が習熟していた旧ソ連製の武器はほとんど使い果たしてしまいました。ここで使い果たすと、他のポーランドをはじめとする旧ワルシャワ条約機構の加盟諸国からも来ている旧ソ連製の武器も使い果たしていくということになり、結局、欧米からの援助の武器はたいへん最新鋭で頼もしい限りなのですが、それを学ぶために兵器の改造をしたり、技術を習得したりしなければなりません。この大変さもあります。
戦争が仮に終わったとして、この武器の支援が有償なのか、無償であるのかということが、今、私たち日本人にも分かっていないのです。イメージとして無償供与をしているようなイメージを与えられていますが、そういうことは原理的になく、少なくとも全てに関して無償だということはあり得ません。
ベトナム戦争が終わった時に、ベトナムの政府はソ連への有償供与(援助は無償ではなかったので)を返すために大変な思いをしました。外貨がありませんので、どうしたかというと、ベトナム人が労働に出かけていき、外国人労働者として旧ソ連で働いたと...