テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
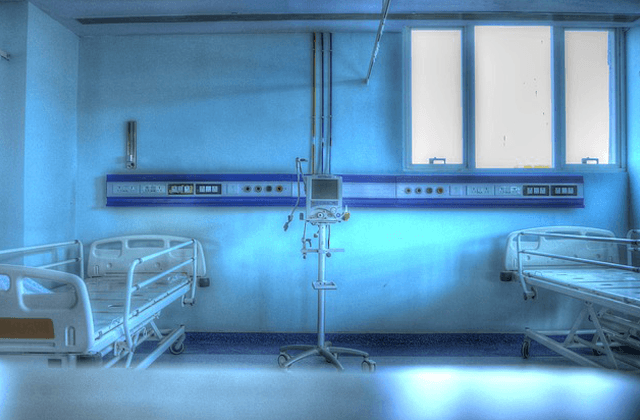
どう死を迎える?クオリティ・オブ・デスの考え方
「クオリティ・オブ・ライフ(QOL)」はよく聞く言葉ですが、それと対照的な言葉「クオリティ・オブ・デス(QOD)」をご存知でしょうか?直訳すれば「死の質」、言い換えればどのように死を迎えるか、という見方、考え方のことです。充実した人生であったなら、最期も満足した形で終わりたい、そう考える人が増えているのも当然のことでしょう。
イギリスが1位に選ばれたのは緩和治療が広く理解されていることや、終末医療が国の方針もあり進められていることが理由に挙げられています。日本は上述した通り1回目に比べれば2回目で大きく順位を上げていますが、これはがん対策推進基本計画により緩和治療への注目が集まりそうだ、という点が評価のポイントになったようです。
例えば、緩和治療や医療的なレベルで見たときのケアの質は相対的に病院より低かったとしても、自宅で死を迎えたいという人は一定の割合でいるはずです。人口動態統計によると、調査を始めた1951年には自宅で死を迎える人は80%超でしたが、2017年は約13%。一方病院で亡くなる人は9.1%→73%と伸びています。ただし、病院での死は2005年の79.8%をピークに漸減傾向にはあるので、死に場所の多様化の兆しは少しずつ見えているとも言えるでしょう。
超高齢化社会という点では世界の最先端をいっている日本。幸か不幸か世界が今後迎えるであろう課題を先取りするわけです。その分介護やシニアを対象とした分野で日本が先行するという予想もされていますが、QODの分野でも状況は同じです。誰しもいつかは迎える死というステージ。ここでも日本流のおもてなしに注目が集まる日がやってくるかもしれません。
QODのランキング 日本は世界で何位?
日本では近年少しずつ注目を浴びている概念ですが、欧米では1980年代から使われている言葉だといわれています。イギリスの経済誌「エコノミスト」は「緩和治療などの理解」「医療従事者の豊富さ」「患者の費用負担」「ケアの質」「地域コミュニティへの参加」の5つの観点からQODの国別ランキングを過去2度にわたり発表しています。日本は1回目の2010年は40か国中23位、2回目の2015年は80か国中14位でした。ちなみに2回目の調査で上位に入った国は1位からイギリス、オーストラリア、ニュージーランド、アイルランド、ベルギーでした。アジアトップは台湾の6位です。イギリスが1位に選ばれたのは緩和治療が広く理解されていることや、終末医療が国の方針もあり進められていることが理由に挙げられています。日本は上述した通り1回目に比べれば2回目で大きく順位を上げていますが、これはがん対策推進基本計画により緩和治療への注目が集まりそうだ、という点が評価のポイントになったようです。
死に場所はどこ? QODの重要な要素に
高齢者の比率は今後伸びていく一方で、厚生労働白書によると、今後2040年までは年間死亡者数が右肩上がりに増えていくと推計されています。となると、終末期医療が重要になるのは当然のこと。むしろQODが注目されるのは遅すぎたとも言えるかもしれません。ここで考えなければいけないのは、エコノミストが挙げた5つの観点以外にもQODを構成する重要な要素があるのではないか、ということです。例えば、緩和治療や医療的なレベルで見たときのケアの質は相対的に病院より低かったとしても、自宅で死を迎えたいという人は一定の割合でいるはずです。人口動態統計によると、調査を始めた1951年には自宅で死を迎える人は80%超でしたが、2017年は約13%。一方病院で亡くなる人は9.1%→73%と伸びています。ただし、病院での死は2005年の79.8%をピークに漸減傾向にはあるので、死に場所の多様化の兆しは少しずつ見えているとも言えるでしょう。
超高齢化社会という点では世界の最先端をいっている日本。幸か不幸か世界が今後迎えるであろう課題を先取りするわけです。その分介護やシニアを対象とした分野で日本が先行するという予想もされていますが、QODの分野でも状況は同じです。誰しもいつかは迎える死というステージ。ここでも日本流のおもてなしに注目が集まる日がやってくるかもしれません。
<参考サイト>
・The 2015 Quality of Death Index Ranking palliative care across the world
https://eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/2015%20EIU%20Quality%20of%20Death%20Index%20Oct%2029%20FINAL.pdf#search='The+Quality+of+Death+Index+2015'
・厚生労働白書
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/07/dl/0102-b.pdf
・1 高齢化の現状と将来像|平成30年版高齢社会白書(全体版) - 内閣府
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2018/html/zenbun/s1_1_1.html
・人口動態調査 人口動態統計 確定数 死亡上巻 5-5 死亡の場所別にみた年次別死亡数・百分率 | 統計表・グラフ表示 | 政府統計の総合窓口
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003214716
・The 2015 Quality of Death Index Ranking palliative care across the world
https://eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/2015%20EIU%20Quality%20of%20Death%20Index%20Oct%2029%20FINAL.pdf#search='The+Quality+of+Death+Index+2015'
・厚生労働白書
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/07/dl/0102-b.pdf
・1 高齢化の現状と将来像|平成30年版高齢社会白書(全体版) - 内閣府
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2018/html/zenbun/s1_1_1.html
・人口動態調査 人口動態統計 確定数 死亡上巻 5-5 死亡の場所別にみた年次別死亡数・百分率 | 統計表・グラフ表示 | 政府統計の総合窓口
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003214716
人気の講義ランキングTOP20
ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ
テンミニッツ・アカデミー編集部










