テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
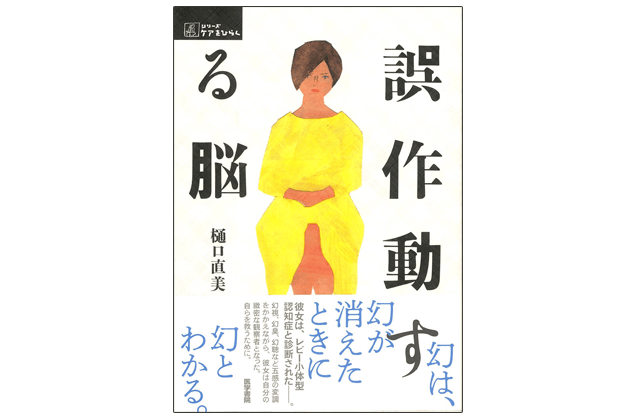
『誤作動する脳』書評│末井昭
自分の観察者になって書き続ける
文・末井昭(編集者・作家)
緊急事態宣言が発令され、家ごもりするようになって、本を読むことが多くなったのですが、その中で面白かったのが樋口直美さんの『誤作動する脳』でした。
樋口さんは、レビー小体型認知症という聞きなれない病気の当事者です。
レビー小体型認知症は、アルツハイマー型認知症に次いで多く、症状が人によって多種多様なので、違う病気に診断されることも多いようです。樋口さんも41歳のときうつ病と診断されて、苦しい服薬治療を6年間も続けました。
レビー小体型認知症は、レビー小体というたんぱく質の塊が脳の中に蓄積されて発症する病気の総称で、認知症状のない患者さんも含まれます。主な症状は、見えないものが見える幻視、聞こえないものが聞こえる幻聴、臭わないものが臭ったり、嗅覚がなくなったり、味覚がなくなったり、時間の感覚がなくなったり、記憶が消えたり、眠れなかったり、大声で寝言を言ったり、数え上げるときりがないほどの症状があります。
樋口さんが長い間苦しめられたのは幻聴でした。最初は忘年会などの飲み会で、目の前の人に話しかけられても、声がまったく聞き取れないことが何度もありました。また、廃品回収車の流す音楽に頭が占領され、会話不能状態に陥ったりすることもありました。聴覚検査も受けたのですが、生活に問題はないという診断でした。まだレビー小体型認知症と診断される前のことです。
幻聴体験で面白かったのは、樋口さんが一人で居間にいた時、突然隣室からガサガサと物音がし、驚いて扉を見つめると、せわしなく引き出しを開けたり、物を動かし続ける音が聞こえてくるのです。泥棒かもしれないと思い、おそるおそる隣室のドアを少し開け部屋を覗くと、人影も物色された跡もなく、物音は消えていました。
柳田国男が岩手県の遠野地方に伝わる逸話や伝承を記録した『遠野物語』に、福の神のように慕われている座敷童子(ざしきわらし)の話が出てきます。姿は12、3歳の男の子のようだったとありますが、家の中で紙のガサガサという音がしたり、しきりに鼻を鳴らす音がしたりするので、その部屋の板戸を開けたら誰もいなかったということもあったと書かれています。樋口さんはそれを読んで、「私の症状と似ている」と思ったそうです。(座敷童子の証言を分析して、レビー小体型認知症の症状と類似点が多いと結論づけた論文もあるそうです)
樋口さんが最初に〝人〟を見たのは、30代の終わりでした。車を集合住宅の定位置にバックでピタッと駐車した時、助手席を見ると中年の女性が乗っていて前を見据えているのです。心臓が止まりそうになり、思わず声を上げそうになった瞬間、その女性はパッと消えたそうです。
ひょっとして、幽霊やお化けを見たという人も、レビー小体型認知症の症状だった可能性もあります。僕は、幽霊や妖怪や座敷童子など実際にいてほしいと思っている者なので、病気の症状だと結論づけるのは微妙なのですが。
この本を読んで一番感じたことは、著者が自分の病気のことを書いている本なのに、全然暗くないということです。大変な症状をたくさん抱えているわけですから、生活するだけで苦労がつきまとうと思うのですが、樋口さんは自分の症状を観察者のように見つめ、病気と仲良く生きて行こうとしているからではないかと思います。そしてどこか、病気を楽しんでいるようにも見えます。
自分の話ですが、先日病院に行くため家を出たら、ハンカチを忘れていることに気がつき、取りに戻りました。普段ならハンカチなんてどうでもいいのですが、手洗いが欠かせない今、ハンカチを忘れたらダメです。ハンカチを持って出直したら、今度は財布を忘れていることに気がつき、またテクテク引き返しました。その時、思わず笑ってしまいました。「もうろくしたなぁ」と思うと暗い気持ちになりますから、「今度は何を忘れるんだろう、楽しみだなぁ」ぐらいに思うと、人生が楽しくなります。忘れ物が多ければ、家を早く出ればいいだけの話です。
老化とともに、体力が落ちたり、物忘れがひどくなったり、記憶力がなくなったり、いろいろマイナス面が出てきますが、それを楽しむぐらいの気持ちでいようと、『誤作動する脳』を読んで思ったのでした。
樋口さんは、この本のあとがきに次のように書いています。
『誰もが、どこかに必ず人と違うちょっとヘンなところを持っているのですから、みんな〝ヘンな人〟として生きるようになれば、こんな息苦しい社会にも風が通って活気が生まれ、病気になる人も減るのではないかと妄想したりします』
『誰もが、どこかヘンなままで、苦しむことなく、そのままに生きられたらいいなぁと、強く願っています』
胸にジーンとくる、励まされる言葉でした。
-----
2020/7/30追記
本書評の内容に一部、間違いがありました。
脳の神経細胞内に、レビー小体(α-シヌクレインなどのたんぱく質が集まった塊)が蓄積されて発症する病気の総称を「レビー小体病」と言い、認知症状がある場合を「レビー小体型認知症」と言います。「レビー小体型認知症は、認知症のない患者さんも含まれる」は間違いです。 忘年会などの飲み会で、目の前の人に話しかけられても、まったく聞き取れなかったことは、「幻聴」ではなく「注意障害」でした。 謹んでお詫び申し上げます。
-----
本書評の内容に一部、間違いがありました。
脳の神経細胞内に、レビー小体(α-シヌクレインなどのたんぱく質が集まった塊)が蓄積されて発症する病気の総称を「レビー小体病」と言い、認知症状がある場合を「レビー小体型認知症」と言います。「レビー小体型認知症は、認知症のない患者さんも含まれる」は間違いです。 忘年会などの飲み会で、目の前の人に話しかけられても、まったく聞き取れなかったことは、「幻聴」ではなく「注意障害」でした。 謹んでお詫び申し上げます。
-----
<著者紹介>
樋口直美(ひぐち・なおみ)
1962年生まれ。50歳でレビー小体型認知症と診断された。41歳でうつ病と誤って診断され、治療で悪化していた6年間があった。多様な脳機能障害のほか、幻覚、嗅覚障害、自律神経症状などもあるが、思考力は保たれ執筆活動を続けている。2015年に上梓した『私の脳で起こったこと』(ブックマン社)が日本医学ジャーナリスト協会賞優秀賞を受賞。「飽きっぽいので何でも長続きしませんが、読むことと書くことだけは、子どものころから好きです。書いて生計を立てたことはないのですが、ずっと書いてきましたし、これからも書き続けることが夢です」(樋口直美)
樋口直美(ひぐち・なおみ)
1962年生まれ。50歳でレビー小体型認知症と診断された。41歳でうつ病と誤って診断され、治療で悪化していた6年間があった。多様な脳機能障害のほか、幻覚、嗅覚障害、自律神経症状などもあるが、思考力は保たれ執筆活動を続けている。2015年に上梓した『私の脳で起こったこと』(ブックマン社)が日本医学ジャーナリスト協会賞優秀賞を受賞。「飽きっぽいので何でも長続きしませんが、読むことと書くことだけは、子どものころから好きです。書いて生計を立てたことはないのですが、ずっと書いてきましたし、これからも書き続けることが夢です」(樋口直美)
人気の講義ランキングTOP20
2025年のテンミニッツ・アカデミーを振り返る
テンミニッツ・アカデミー編集部










