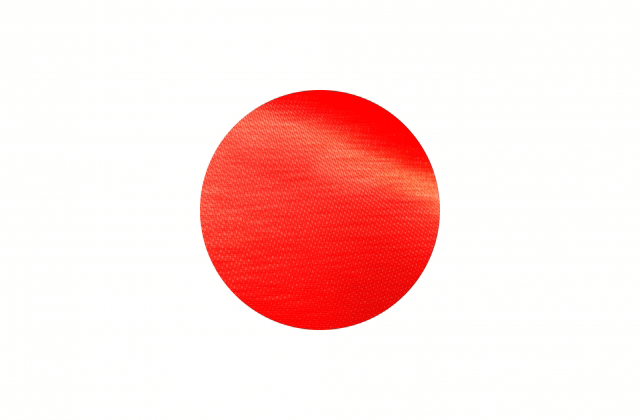
「君が代」はいつから歌われているのか?
古くから日本人にはよく知られ、歌われてきた「君が代」ですが、国歌として法制定されたのは平成に入ってからという事実をご存知でしょうか。
実は「君が代」が法的な国歌として定められたのは、21世紀に近い1999(平成11)年に「国旗及び国歌に関する法律」が制定された時となります。
しかし、「君が代」はもっと以前から歌われてきました。では「君が代」はいつ頃から歌われるようになったのでしょうか。
「わが君は千代に八千代に細れ石の巌と成りて苔のむすまで」『古今和歌集』(「賀歌」343番)
この一首は「賀歌(がのうた)」という長寿や繁栄などをことほぐ寿歌(ほきうた・ほぎうた)に分類されており、現代語訳は「わが君のご寿命は千代、八千代にまで続いていただきたい。小さい石が少しずつ大きくなり、大きな岩になり、それに苔が生えるまでも」となっています。ちなみに「読人しらず」、つまり作者が誰かはわかっていません。
なお「細れ石(さざれいし)」は、小さい石・細かい石・小石といった意味で、対する「巌(いわお)」には、大きい石・巨石・岩石といった意味があります。そのため、“細れ石が巌と成る”は、自然経過的には矛盾した表現といえますが、そのような文芸的表現の背景には、古代日本のアニミズム的な世界観や、中国渡来の伝奇や説話が由来しているのではないかと考えられています。閑話休題でした。
しかしながら、『古今和歌集』の段階では「わが君」であり、「君が代」ではありません。ではいつから、「君が代」となったのでしょうか。
印刷機もコピー機もない当時、著作を広めるためには写本といって手で書き写すか、口頭で伝承するしか手段はありませんでした。名著の誉れ高い『古今和歌集』は写本され、またその中に収められた名歌も様々な場面に応じて多くの人々に歌われることにより広まっていきました。
ただし、写本では写す際のまちがいともいえるバリエーションが生まれ、口頭伝承でも変化が生じていくことになります。そしていよいよ平安末頃になると歌詞も「君が代」と変り、さらには宴会や歌舞の後に“祝いおさめる歌”となって歌われるようになっていったとも考察されています。
なお、現存する「君が代(きみがよ)」の初句は、鎌倉時代前期の『和漢朗詠集』(「祝」775番)の写本といわれています。
『和漢朗詠集』とは、平安中期の歌人・藤原公任が、朗詠(詩歌などを節をつけて声高くうたうこと)に適した漢詩文と和歌を選んだ詩歌選集です。複数の写本が現存するため、「わが君」のままに伝わっているものが多いのも事実ですが、宮内庁書陵部所蔵の1228(安貞2)年の奥書のある『和漢朗詠集』の写本は、「君が代(きみがよ)」となっています。
さらに「君が代」の歌詞は、江戸時代初期の流行歌謡である「隆達節(りゅうたつぶし)」や、江戸時代中期以後には箏曲・地歌・長唄などにも用いられます。また謡曲などの他の文芸にも取り入れられ、多くの人々に歌われていったと考えられています。
「君(きみ)」には、主人や家長だけでなく友人や愛する人など、“(私の)敬愛する方”“(私の)大切なあなた”というような意味が含まれた二人称や三人称として、幅広く使われてきたといわれています。
以上から、「君が代」が「(私の敬愛する・私の大切な)あなたの健康長寿を祈る歌」として、平安の頃から歌われ始め、そして時代とともに変化しながらも、多くの人に歌われてきたことがみえてきました。
まずはさかのぼること1869(明治2)年、横浜滞在のイギリス人軍楽隊長フェントンが、薩摩藩砲兵隊長・大山弥助(のちの元帥陸軍大将・大山巌)に近代国家における国歌の必要を説きます。これを受けて大山は、薩摩琵琶歌「蓬莱山」の歌詞の一部ともなっていた、「君が代」の詞を推薦し、フェントンがヘ長調の曲をつけました。
次いで1880(明治13)年、海軍省から宮内省雅楽課に「君が代」の作曲が委嘱されます。これを受けて、雅楽家で伶人長であった林広守が旋律を作り、ドイツ人音楽教師エッケルトが四声体に編曲し、同年に初演されました。
そして1893(明治26)年、文部省が全国の小学校にむけて告示した「祝日大祭日歌詞並楽譜」の冒頭に「君が代」が所載され、全国で歌われるようになりました。またその際の曲として、前述の林広守の旋律が定着し、現在に至ることとなります。
さらに時代が過ぎた1958(昭和33)年、告示された「小学校学習指導要領」の中で、学校において国民の祝日などの儀式を行う場合、国旗を掲揚し、「君が代」を斉唱することが望ましいとされます。
以上のような変遷を経て、冒頭の1999(平成11)年の「国旗及び国歌に関する法律」に至り、「君が代」は日本の国歌として法的に定められ、歌われることとなりました。
例えば英語が苦手であっても洋楽には親しめるように、またあるいは標準語がなかった近世以前の日本において謡曲が武士の共通語の役割を果たしたともいわれているように、さらには明治の新政府が唱歌や軍歌を近代化政策の際に活用したように、新しい概念といえるような言葉でも、歌うことで取り入れやすくなります。
さらに和歌という日本固有の詩歌は、日本文芸の正統な核にして、日本的な“心の有り様”の映し鏡ともいえます。その中の一首であり、時代の風雪に耐え抜いた「君が代」には、大きな力が潜んでいて、歌うたびにその力がよみがえるのかもしれません。
ただし、誰であってもいかなる時にも、“心の有り様”は真に自由であることが何よりも大事です。一人ひとりの素直な“心の有り様”をよりよく増幅するためにこそ歌の力が活用される時代と、そのような時代の末永い継続が望まれます。
実は「君が代」が法的な国歌として定められたのは、21世紀に近い1999(平成11)年に「国旗及び国歌に関する法律」が制定された時となります。
しかし、「君が代」はもっと以前から歌われてきました。では「君が代」はいつ頃から歌われるようになったのでしょうか。
「君が代」の歌い始め
「君が代」の歌詞の原典は、平安時代前期にあたる905年に、醍醐天皇の勅命によって紀貫之・紀友則・凡河内躬恒・壬生忠岑といった名歌人らが撰者となった、最初の勅撰和歌集である『古今和歌集』に収録された、以下の和歌とされています。「わが君は千代に八千代に細れ石の巌と成りて苔のむすまで」『古今和歌集』(「賀歌」343番)
この一首は「賀歌(がのうた)」という長寿や繁栄などをことほぐ寿歌(ほきうた・ほぎうた)に分類されており、現代語訳は「わが君のご寿命は千代、八千代にまで続いていただきたい。小さい石が少しずつ大きくなり、大きな岩になり、それに苔が生えるまでも」となっています。ちなみに「読人しらず」、つまり作者が誰かはわかっていません。
なお「細れ石(さざれいし)」は、小さい石・細かい石・小石といった意味で、対する「巌(いわお)」には、大きい石・巨石・岩石といった意味があります。そのため、“細れ石が巌と成る”は、自然経過的には矛盾した表現といえますが、そのような文芸的表現の背景には、古代日本のアニミズム的な世界観や、中国渡来の伝奇や説話が由来しているのではないかと考えられています。閑話休題でした。
しかしながら、『古今和歌集』の段階では「わが君」であり、「君が代」ではありません。ではいつから、「君が代」となったのでしょうか。
印刷機もコピー機もない当時、著作を広めるためには写本といって手で書き写すか、口頭で伝承するしか手段はありませんでした。名著の誉れ高い『古今和歌集』は写本され、またその中に収められた名歌も様々な場面に応じて多くの人々に歌われることにより広まっていきました。
ただし、写本では写す際のまちがいともいえるバリエーションが生まれ、口頭伝承でも変化が生じていくことになります。そしていよいよ平安末頃になると歌詞も「君が代」と変り、さらには宴会や歌舞の後に“祝いおさめる歌”となって歌われるようになっていったとも考察されています。
なお、現存する「君が代(きみがよ)」の初句は、鎌倉時代前期の『和漢朗詠集』(「祝」775番)の写本といわれています。
『和漢朗詠集』とは、平安中期の歌人・藤原公任が、朗詠(詩歌などを節をつけて声高くうたうこと)に適した漢詩文と和歌を選んだ詩歌選集です。複数の写本が現存するため、「わが君」のままに伝わっているものが多いのも事実ですが、宮内庁書陵部所蔵の1228(安貞2)年の奥書のある『和漢朗詠集』の写本は、「君が代(きみがよ)」となっています。
さらに「君が代」の歌詞は、江戸時代初期の流行歌謡である「隆達節(りゅうたつぶし)」や、江戸時代中期以後には箏曲・地歌・長唄などにも用いられます。また謡曲などの他の文芸にも取り入れられ、多くの人々に歌われていったと考えられています。
「君(きみ)」には、主人や家長だけでなく友人や愛する人など、“(私の)敬愛する方”“(私の)大切なあなた”というような意味が含まれた二人称や三人称として、幅広く使われてきたといわれています。
以上から、「君が代」が「(私の敬愛する・私の大切な)あなたの健康長寿を祈る歌」として、平安の頃から歌われ始め、そして時代とともに変化しながらも、多くの人に歌われてきたことがみえてきました。
国歌としての「君が代」の歌い始め
ところで、現代を生きる多くの人々にとって、「君が代」といえば和歌や歌謡というよりは、日本の国歌としての印象が強いように思います。では「君が代」は、国歌もしくはそれに準ずるような扱いとしては、いつから歌われているのでしょうか。まずはさかのぼること1869(明治2)年、横浜滞在のイギリス人軍楽隊長フェントンが、薩摩藩砲兵隊長・大山弥助(のちの元帥陸軍大将・大山巌)に近代国家における国歌の必要を説きます。これを受けて大山は、薩摩琵琶歌「蓬莱山」の歌詞の一部ともなっていた、「君が代」の詞を推薦し、フェントンがヘ長調の曲をつけました。
次いで1880(明治13)年、海軍省から宮内省雅楽課に「君が代」の作曲が委嘱されます。これを受けて、雅楽家で伶人長であった林広守が旋律を作り、ドイツ人音楽教師エッケルトが四声体に編曲し、同年に初演されました。
そして1893(明治26)年、文部省が全国の小学校にむけて告示した「祝日大祭日歌詞並楽譜」の冒頭に「君が代」が所載され、全国で歌われるようになりました。またその際の曲として、前述の林広守の旋律が定着し、現在に至ることとなります。
さらに時代が過ぎた1958(昭和33)年、告示された「小学校学習指導要領」の中で、学校において国民の祝日などの儀式を行う場合、国旗を掲揚し、「君が代」を斉唱することが望ましいとされます。
以上のような変遷を経て、冒頭の1999(平成11)年の「国旗及び国歌に関する法律」に至り、「君が代」は日本の国歌として法的に定められ、歌われることとなりました。
歌い継がれる“心の有り様”
“歌う”ことには力(パワー)があります。そして、メロディーやリズムに乗せれば言葉を口ずさみやすくなります。例えば英語が苦手であっても洋楽には親しめるように、またあるいは標準語がなかった近世以前の日本において謡曲が武士の共通語の役割を果たしたともいわれているように、さらには明治の新政府が唱歌や軍歌を近代化政策の際に活用したように、新しい概念といえるような言葉でも、歌うことで取り入れやすくなります。
さらに和歌という日本固有の詩歌は、日本文芸の正統な核にして、日本的な“心の有り様”の映し鏡ともいえます。その中の一首であり、時代の風雪に耐え抜いた「君が代」には、大きな力が潜んでいて、歌うたびにその力がよみがえるのかもしれません。
ただし、誰であってもいかなる時にも、“心の有り様”は真に自由であることが何よりも大事です。一人ひとりの素直な“心の有り様”をよりよく増幅するためにこそ歌の力が活用される時代と、そのような時代の末永い継続が望まれます。
<参考文献・参考サイト>
・「君が代」『日本大百科全書』(榊原烋一著、小学館)
・「君が代」『世界大百科事典』(山住正己著、平凡社)
・『君が代の歴史』(山田孝雄著、講談社学術文庫)
・『ふしぎな君が代』(辻田真佐憲著、幻冬舎新書)
・『新編 日本古典文学全集 11 古今和歌集』(小沢正夫・松田成穂校注・訳、小学館)
・『古今和歌集全評釈 中』(片桐洋一著、講談社)
・「賀歌」『日本大百科全書』(新井栄蔵著、小学館)
・『新編 日本古典文学全集 19 和漢朗詠集』(藤原公任撰、菅野礼行校注・訳、小学館)
・『新潮日本古典集成 和漢朗詠集(新装版)』(藤原公任撰、大曽根章介・堀内秀晃校注、新潮社)
・『和漢朗詠集新釈(改修版)』(金子元臣・江見清風著、明治書院)
・「君が代」『日本大百科全書』(榊原烋一著、小学館)
・「君が代」『世界大百科事典』(山住正己著、平凡社)
・『君が代の歴史』(山田孝雄著、講談社学術文庫)
・『ふしぎな君が代』(辻田真佐憲著、幻冬舎新書)
・『新編 日本古典文学全集 11 古今和歌集』(小沢正夫・松田成穂校注・訳、小学館)
・『古今和歌集全評釈 中』(片桐洋一著、講談社)
・「賀歌」『日本大百科全書』(新井栄蔵著、小学館)
・『新編 日本古典文学全集 19 和漢朗詠集』(藤原公任撰、菅野礼行校注・訳、小学館)
・『新潮日本古典集成 和漢朗詠集(新装版)』(藤原公任撰、大曽根章介・堀内秀晃校注、新潮社)
・『和漢朗詠集新釈(改修版)』(金子元臣・江見清風著、明治書院)
人気の講義ランキングTOP20
『種の起源』…ダーウィンとウォレスの自然淘汰の理論
長谷川眞理子
毛繕いを代行!?脳の大型化が可能にしたメンタライジング
長谷川眞理子







