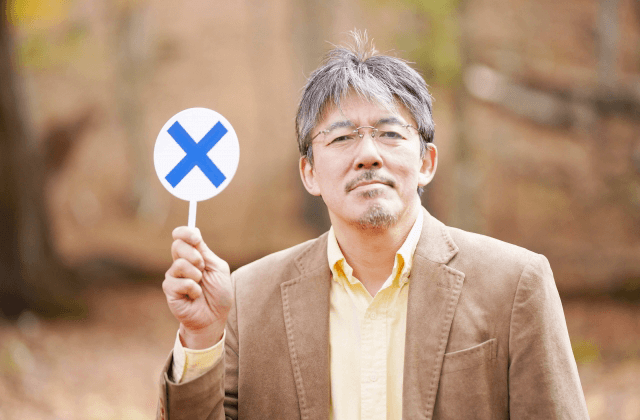
「定年後にしてはいけないこと」8選
定年が視野に入る年齢を迎えると、「定年したら夫婦で旅行三昧したい、ゴルフ通いをしたい」という夢や「毎日どう暮らしたらいいのか、お金は大丈夫か」という不安など、さまざまに老後の暮らしを想像することだと思います。たとえ色々と考えを巡らせていても実際に定年で生活が一変すると、「こんなはずではなかった…」と戸惑ったり後悔することもあるでしょう。その先も長い定年退職後の生活を健康的で充実したものにするためには、定年後に「しない方がいいこと」を知っておくことも大切です。
社会的なしがらみから解放され自由を満喫するのもいいですが、そのうち出掛けたり人と会うのも面倒になると段々と社会から孤立してしまいます。誰とも話さない、関わらないでいると認知症やうつ、言語や嚥下機能に問題が出てくることも。サークルやカルチャーセンターなど、週に1,2回は家族以外の他人と会話をする機会を作り、情報交換ができるコミュニティを持ちましょう。
2:行動範囲を狭め、運動不足になる
出社しなくていいとなると行動範囲は近所だけ、歩く時間はどんどん減ってしまいます。まだ体力のあるうちはパートタイムで仕事をしたり、地域の朝のラジオ体操に参加したり、また犬を飼うなど外出して「歩く」時間を維持する必要も。ハードな運動は必ずしも健康に良いとは言えませんが、無理のない範囲でこれまで続けてきたスポーツを継続するのもありです。
3:新しいことや変化を拒む
老後はシンプルに暮らしたいと、複雑なことや新しいことを拒むようになる人も。「現金でいい」とキャッシュレス決済を拒否したり、新しいスマホやPCなども「電話さえできればいい」と変えない人もいますが、頭の柔らかいうちに挑戦しないといずれ必要となった時に困ることになります。脳トレだと思って、あえて新しいことを楽しく学んで知ることも長い老後のプラスに。
4:退職金で過度な浪費をする
現役時代の生活レベルを落とせずお金を使ってしまったり、炊事が面倒で外食が増えたりタクシーを頻繁に利用したり、退職金で気が大きくなり子どもや孫に過剰な支援をしてしまうのもNGです。生活費はできるだけ年金で賄い、足らない分は元気なうちは働いて稼ぐという方法もあります。まずは定年後の収支を考えて、計画的に家計を整えましょう。
5:投資や株に老後資金を注ぎ込む
「寝かせておくのは勿体無い」「お金に稼いでもらいましょう」などの誘い文句で、退職金の運用を勧められることもあると聞きますが、投資や株に知識のないまま多額の資金を投入してはいけません。少しでも老後資金を増やしたいと思うのは当然ですが、そのお金がなくなっても生活できるレベルの余剰金でないのならリスクは膨大。攻めより守りを意識して、運用は慎重に。
6:退職金でローンの一括返済
毎月の利息や支出を考えたら自宅の残ローンを退職金で一括返済したくなりますが、老後は手元に現金を残しておくことも重要。急な病気や自宅のリペアや家電の買い替えなど、年金では賄えない高額な出費もあるのです。金利の高い時代なら普通だった一括返済ですが、今は幸いまだ低金利ですから、早く返すことがマストではありません。一部を繰上げ返済し、月々の支払いを抑える方法も要検討。
7:憧れの田舎暮らしで地方へ移住
「定年後は自然豊かな田舎暮らし」という夢のある都会人も多いのですが、体力が衰える老後に不便で不慣れな土地で暮らすのはリスク大。買物や病院通いに車が必要ですが免許があってもいつまでも乗れる訳ではなく、いざという時に頼れる仲間や家族とも離れて暮らすのは簡単ではありません。勢いで完全移住することは避け、初めは便利な都会に帰れる自宅を残しておく方が良いとの経験談も。
8:趣味の延長での開業
「夫婦で夢だった喫茶店をやりたい」「趣味の仲間が集まれるお店を作る」、そんな老後計画のある人もいますが、一から経営を学ぶでもなく趣味の延長でお店を開業するのは危険です。退職金でまとまった資金はあっても、毎月の売上や運営が管理できなければランディング費用が嵩み資金難、老後破綻となるケースも。例えばタイムレンタルの店舗貸しシステムを利用してイベントとして実施してみたり、喫茶店等でパートを経験することからまずはスタートしてみては?
もちろん現役時代にも大切な3つですが、定年退職後はそれらを自力でリカバーしたり向上させるのは若い頃より簡単ではなく、いかに守って維持するかということを自主的に実践していかなくてはなりません。「してはいけないこと」を意識してリスクを減らし、暮らし上手な老後生活を送りたいですね。
それ大丈夫? してはいけない定年後8つのあれこれ
1:「煩わしい」と思って人との付き合いを断つ社会的なしがらみから解放され自由を満喫するのもいいですが、そのうち出掛けたり人と会うのも面倒になると段々と社会から孤立してしまいます。誰とも話さない、関わらないでいると認知症やうつ、言語や嚥下機能に問題が出てくることも。サークルやカルチャーセンターなど、週に1,2回は家族以外の他人と会話をする機会を作り、情報交換ができるコミュニティを持ちましょう。
2:行動範囲を狭め、運動不足になる
出社しなくていいとなると行動範囲は近所だけ、歩く時間はどんどん減ってしまいます。まだ体力のあるうちはパートタイムで仕事をしたり、地域の朝のラジオ体操に参加したり、また犬を飼うなど外出して「歩く」時間を維持する必要も。ハードな運動は必ずしも健康に良いとは言えませんが、無理のない範囲でこれまで続けてきたスポーツを継続するのもありです。
3:新しいことや変化を拒む
老後はシンプルに暮らしたいと、複雑なことや新しいことを拒むようになる人も。「現金でいい」とキャッシュレス決済を拒否したり、新しいスマホやPCなども「電話さえできればいい」と変えない人もいますが、頭の柔らかいうちに挑戦しないといずれ必要となった時に困ることになります。脳トレだと思って、あえて新しいことを楽しく学んで知ることも長い老後のプラスに。
4:退職金で過度な浪費をする
現役時代の生活レベルを落とせずお金を使ってしまったり、炊事が面倒で外食が増えたりタクシーを頻繁に利用したり、退職金で気が大きくなり子どもや孫に過剰な支援をしてしまうのもNGです。生活費はできるだけ年金で賄い、足らない分は元気なうちは働いて稼ぐという方法もあります。まずは定年後の収支を考えて、計画的に家計を整えましょう。
5:投資や株に老後資金を注ぎ込む
「寝かせておくのは勿体無い」「お金に稼いでもらいましょう」などの誘い文句で、退職金の運用を勧められることもあると聞きますが、投資や株に知識のないまま多額の資金を投入してはいけません。少しでも老後資金を増やしたいと思うのは当然ですが、そのお金がなくなっても生活できるレベルの余剰金でないのならリスクは膨大。攻めより守りを意識して、運用は慎重に。
6:退職金でローンの一括返済
毎月の利息や支出を考えたら自宅の残ローンを退職金で一括返済したくなりますが、老後は手元に現金を残しておくことも重要。急な病気や自宅のリペアや家電の買い替えなど、年金では賄えない高額な出費もあるのです。金利の高い時代なら普通だった一括返済ですが、今は幸いまだ低金利ですから、早く返すことがマストではありません。一部を繰上げ返済し、月々の支払いを抑える方法も要検討。
7:憧れの田舎暮らしで地方へ移住
「定年後は自然豊かな田舎暮らし」という夢のある都会人も多いのですが、体力が衰える老後に不便で不慣れな土地で暮らすのはリスク大。買物や病院通いに車が必要ですが免許があってもいつまでも乗れる訳ではなく、いざという時に頼れる仲間や家族とも離れて暮らすのは簡単ではありません。勢いで完全移住することは避け、初めは便利な都会に帰れる自宅を残しておく方が良いとの経験談も。
8:趣味の延長での開業
「夫婦で夢だった喫茶店をやりたい」「趣味の仲間が集まれるお店を作る」、そんな老後計画のある人もいますが、一から経営を学ぶでもなく趣味の延長でお店を開業するのは危険です。退職金でまとまった資金はあっても、毎月の売上や運営が管理できなければランディング費用が嵩み資金難、老後破綻となるケースも。例えばタイムレンタルの店舗貸しシステムを利用してイベントとして実施してみたり、喫茶店等でパートを経験することからまずはスタートしてみては?
定年後の生活を支える大切な3つ、その向き合い方が大事
定年後の生活を支えるのは「健康」と「お金」と「生き甲斐やつながり」といわれています。もちろん現役時代にも大切な3つですが、定年退職後はそれらを自力でリカバーしたり向上させるのは若い頃より簡単ではなく、いかに守って維持するかということを自主的に実践していかなくてはなりません。「してはいけないこと」を意識してリスクを減らし、暮らし上手な老後生活を送りたいですね。
人気の講義ランキングTOP20
欧州では不人気…木村資生の中立説とダーウィンとの違い
長谷川眞理子







