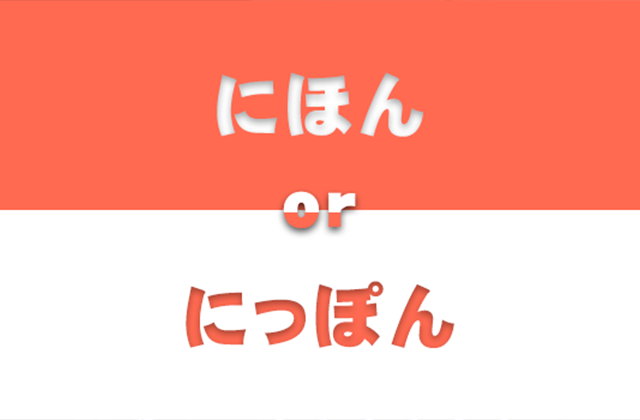
「にほん」と「にっぽん」どちらが正しいのか?
にほん国憲法と大にっぽん帝国憲法、にほん航空と全にっぽん空輸、にほん書紀とにっぽん永代蔵、にほん共産党とにっぽん維新の会、そして、東京のにほん橋と大阪のにっぽん橋……。
国名である「日本」の読み方は「にほん」と「にっぽん」ですが、一方に統一することは不可能なため、どちらの発音でもよいとされています。つまりニッポンの呼び方は、「にほん」と「にっぽん」はどちらも正しいといえます。
ただし、当初は「日本」という表記で「やまと」と呼ばれていました。古くは大和地方を基盤とする大和政権によって国家統一がなされたことから、国名を「やまと」や「おおやまと」と称していたからです。
ではなぜ、「日本」は「にほん」または「にっぽん」と呼ばれるようになったのでしょうか。
日本語の文字は漢字が基となっていますが、漢字は古代中国の統一王朝である「漢」の文字でした。飛鳥時代から奈良時代にかけての中国との交流で、日本に漢字がもたらされたことにより、日本語の発音に漢字の表記が当てられることとなります。
しかし、漢字には中国で使われていた本来の字音(読み方、発音)として、漢音(かんおん)や呉音(ごおん)などがありました。例えば、「日」の漢音は「ジツ」で呉音は「ニチ」、「本」は漢音・呉音とも「ホン」です。
つまり「日本」は、(1)最初に発音されていた「やまと」や「おおやまと」から、(2)呉音や漢音の「にちほん」となり、(3)さらに「にっぽん」に音変化したうえで、(4)時代が下がるにつれて発音のやわらかな「にほん」とも呼ばれるようになり、(5)「にほん」と「にっぽん」が併用されるようになった――のではないかといわれています。
まず、昭和9(1934)年に臨時国語調査会(国語審議会の前身)が国号呼称統一案として「ニッポン」を決議しましたが、政府採択には至りませんでした。
その後も、戦前の帝国議会や戦後の国会を通じて、何度か国号呼称の統一が問題になりました。例えば、昭和45(1970)年、日本初の万国博覧会(大阪万国博覧会)を開催中の閣議でも検討され、当時の佐藤栄作首相や中曽根康弘防衛庁長官が「ニッポン」を強く推したといわれています。しかし、この時も結論は出ず、問題は先送りにされました。
そして、平成21(2009)年に当時の麻生内閣は「今後、『日本』の読み方を統一する意向はあるか」の質問に対し、「『にっぽん』または『にほん』という読み方については、いずれも広く通用しており、どちらか一方に統一する必要はないと考えている」と答弁し、現在にいたっています。
ただし、日本放送協会は昭和26(1951)年に、正式の国号としては「ニッポン」、その他の場合は「ニホン」と言ってもよいとしました。ちなみに、『NHK日本語発音(にほんごはつおん)アクセント新辞典』の編者は、NHK(にっぽんほうそうきょうかい)放送文化研究所です。
いかがでしたでしょうか。身近にある「にほん」と「にっぽん」、ぜひ探してみてください。
国名である「日本」の読み方は「にほん」と「にっぽん」ですが、一方に統一することは不可能なため、どちらの発音でもよいとされています。つまりニッポンの呼び方は、「にほん」と「にっぽん」はどちらも正しいといえます。
「にほん」と「にっぽん」の誕生
国名として「日本」が使われ始めたのは、奈良時代までさかのぼります。大化の改新の頃、「日出づる処」の意味で「日本(ひのもと)」と称したことが始まりといわれています。ただし、当初は「日本」という表記で「やまと」と呼ばれていました。古くは大和地方を基盤とする大和政権によって国家統一がなされたことから、国名を「やまと」や「おおやまと」と称していたからです。
ではなぜ、「日本」は「にほん」または「にっぽん」と呼ばれるようになったのでしょうか。
日本語の文字は漢字が基となっていますが、漢字は古代中国の統一王朝である「漢」の文字でした。飛鳥時代から奈良時代にかけての中国との交流で、日本に漢字がもたらされたことにより、日本語の発音に漢字の表記が当てられることとなります。
しかし、漢字には中国で使われていた本来の字音(読み方、発音)として、漢音(かんおん)や呉音(ごおん)などがありました。例えば、「日」の漢音は「ジツ」で呉音は「ニチ」、「本」は漢音・呉音とも「ホン」です。
つまり「日本」は、(1)最初に発音されていた「やまと」や「おおやまと」から、(2)呉音や漢音の「にちほん」となり、(3)さらに「にっぽん」に音変化したうえで、(4)時代が下がるにつれて発音のやわらかな「にほん」とも呼ばれるようになり、(5)「にほん」と「にっぽん」が併用されるようになった――のではないかといわれています。
「日本」の読み方が統一されなかった経緯
「日本」が「にほん」と「にっぽん」と二つの呼び方で呼ばれるようになった歴史を考察してきましたが、やはり国名不統一の国はめずらしいといえます。そのため、日本の国名を統一するという動きは何度もありました。まず、昭和9(1934)年に臨時国語調査会(国語審議会の前身)が国号呼称統一案として「ニッポン」を決議しましたが、政府採択には至りませんでした。
その後も、戦前の帝国議会や戦後の国会を通じて、何度か国号呼称の統一が問題になりました。例えば、昭和45(1970)年、日本初の万国博覧会(大阪万国博覧会)を開催中の閣議でも検討され、当時の佐藤栄作首相や中曽根康弘防衛庁長官が「ニッポン」を強く推したといわれています。しかし、この時も結論は出ず、問題は先送りにされました。
そして、平成21(2009)年に当時の麻生内閣は「今後、『日本』の読み方を統一する意向はあるか」の質問に対し、「『にっぽん』または『にほん』という読み方については、いずれも広く通用しており、どちらか一方に統一する必要はないと考えている」と答弁し、現在にいたっています。
ただし、日本放送協会は昭和26(1951)年に、正式の国号としては「ニッポン」、その他の場合は「ニホン」と言ってもよいとしました。ちなみに、『NHK日本語発音(にほんごはつおん)アクセント新辞典』の編者は、NHK(にっぽんほうそうきょうかい)放送文化研究所です。
いかがでしたでしょうか。身近にある「にほん」と「にっぽん」、ぜひ探してみてください。
<参考文献・参考サイト>
・『デジタル大辞泉』(小学館)
・『歴史に「何を」学ぶのか』(半藤一利著、ちくまプリマー新書)
・『社会人の社会科』(吹浦忠正著、祥伝社 )
・『NHK日本語発音アクセント新辞典』(NHK放送文化研究所編、NHK出版)
・日本は「にっぽん」と「にほん」どちらの呼び方が正しいの?
https://topics.tbs.co.jp/article/detail/?id=4012
・「ニホン」も「ニッポン」も正しい!「日本」の読み方はなぜ統一しない?/毎日雑学
https://ddnavi.com/serial/695538/a/
・言葉のてびき - 教育出版 - Q18「日本」は「ニッポン」か「ニホン」か
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/chuu/kokugo/guidanceq018-00.html
・「ニホン」と「ニッポン」、なぜ2つの呼び方が存在するのか?
https://diamond.jp/articles/-/297292
・『デジタル大辞泉』(小学館)
・『歴史に「何を」学ぶのか』(半藤一利著、ちくまプリマー新書)
・『社会人の社会科』(吹浦忠正著、祥伝社 )
・『NHK日本語発音アクセント新辞典』(NHK放送文化研究所編、NHK出版)
・日本は「にっぽん」と「にほん」どちらの呼び方が正しいの?
https://topics.tbs.co.jp/article/detail/?id=4012
・「ニホン」も「ニッポン」も正しい!「日本」の読み方はなぜ統一しない?/毎日雑学
https://ddnavi.com/serial/695538/a/
・言葉のてびき - 教育出版 - Q18「日本」は「ニッポン」か「ニホン」か
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/chuu/kokugo/guidanceq018-00.html
・「ニホン」と「ニッポン」、なぜ2つの呼び方が存在するのか?
https://diamond.jp/articles/-/297292
人気の講義ランキングTOP20
『種の起源』…ダーウィンとウォレスの自然淘汰の理論
長谷川眞理子







