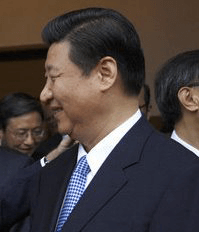●加熱し始めた「中国初の普遍」
「東洋の普遍、西洋の普遍」非常に大きなタイトルを掲げました。1年半前にこちらでお話をさせていただいた時に、非常に知的な議論を共有することができたので、今日はそれをさらに続けようということで、少し挑戦的な内容にしてみました。
副題が「科学、民主主義、資本主義」とあります。この三つは、近代の私たちにとっては、ある種の普遍的なものですね。ただ、それがいったいいかなる意味での普遍なのか。これがすぐに問題になってきます。
日本の近代を少し振り返ってみると、20世紀の半ばまでは「西洋的な普遍に参入していこう。そしてそれを我が物とした上で乗り越えていこう」という方向性がありました。しかし20世紀後半になると、戦争への反省ということもあり、どちらかと言えば日本の思想は、普遍に向かうよりも特殊に向かう方向へ舵を切ったのかと思っています。
ところが冷戦が終わったことで、いよいよそうも言っていられなくなった。日本的な特殊に閉じこもっているだけでは、グローバル化の時代にうまく入っていけないわけです。そうすると改めて、日本にとって「普遍を問う」とはいったい何なのか、当然これが問題になってくるわけです。
ただ20世紀前半と違うのは、今やそういう普遍を問うのが日本だけではないということです。とりわけ私が専門にしている中国を見ると「中国発の普遍をどうするのか」という議論が今、非常に熱くなっています。ただ残念ながら、それが日本の文脈になかなか紹介されません。そこで今日は、その一端を披露しまして、中国で論じられる普遍が、近代日本の考えた普遍とどういう形で切り結んでいくのか、これを軸に考えてみたいと思っています。
●東洋的な普遍を再発明する
これが今日の概要です。現在、中国発の普遍というテーマでしばしば語られるのは、例えば「天下」や「王道」という概念です。もちろん、皆さんは「天下」や「王道」という概念を聞くと、「あれあれ? ちょっと待てよ」とお思いになるでしょう。これは非常に前近代的な概念で、西洋近代と遭遇したときにいったんは捨てられたものではないのか。
確かにそうなのです。(西洋近代と出会ったことで)「天下」という概念の代わりに、「世界」という概念が中国に登場してきます。中国的な「天下」というのは、「世界」にとってのサブ概念、従...