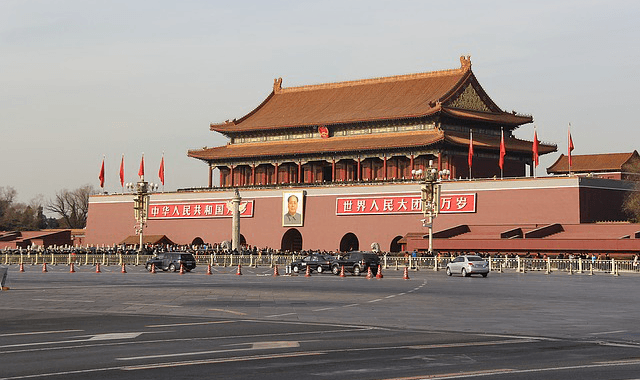●「核心利益」の提示
中国共産党は、巨大国家の安定と経済の発展を維持していく上で、さまざまな難題を抱えてきました。その中でも最も大きな問題の1つが、少数民族問題です。それは1つ間違えば、中国の領土の一体性を突き崩す一撃にもなりかねません。2008年にはチベット自治区で、2009年には新疆ウイグル自治区で暴動が起き、胡錦濤指導部はその収拾に追われました。そして、中国の発展を望まずその分裂を画策する国外の勢力が、その背後に存在するという警戒感を強めます。
外交においても、「台独」すなわち台湾の独立、「藏独」すなわちチベットの独立、「疆独(きょうどく)」すなわち新疆の独立、こうした勢力との闘争に奉仕することを求められます。胡錦濤国家主席は、「外交工作は、国家主権、安全、発展利益に奉仕すべきだ」と強調し、交渉の余地のない「核心利益」が中国外交の前面に登場するのです。
2009年、戴秉国(たいへいこく)国務委員は、1.中国の国家体制や政治体制、2.主権の安全、領土の一体性、国家の統一、3.中国経済の持続的発展の保障、これらを「核心利益」と位置付け、これを侵すことは許さないと強調しました。このように、中国の核心利益は、中国が警戒する脅威の裏返しであって、中国の脅威認識を色濃く反映しているといえます。1の中国の国家体制や政治体制には中国共産党が敏感になり、2の主権の安全、領土の一体性、国家の統一にはナショナリズムを帯びた世論が反発します。
内政と外交が一体化する時代にあって、国内に火種を抱えながら経済成長を維持していく必要がある中国の指導者にとって、中国のボトム・ラインを「核心利益」として提示して予防線を張ることが、「内外を総攬する」上で必要とされたのです。
2009年11月のバラク・オバマ大統領訪中時の共同声明には、「核心利益を互いに尊重する」という文言が盛り込まれました。これはアメリカ国内の批判を招き、2011年1月の胡錦濤国家主席訪米時の共同声明においては、「核心利益」という言葉は盛り込まれませんでした。そこでは、「主権と領土保全を尊重する」という表現に落ち着いたのです。
●「核心利益」の再定義
この2011年に中国は、「平和発展白書」を発表しています。その中では7つの「核心利益」が提示されました。1つ目は国家主権、2つ目は国家安全、3つ目は領土保全、4つ目は国家統一、5つ目は中...