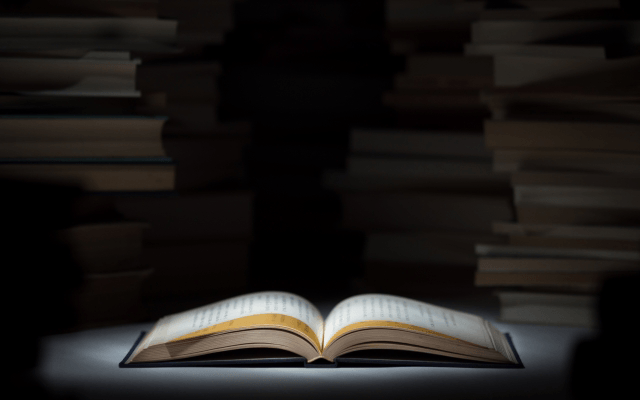●なぜビジネススクールで『孫子』が重視されているのか
今回は『孫子』の講義をいたします。
本題に入る前に、2000年ごろに始まった『孫子』のブームに関して、少しご説明をさせていただきます。特にビジネススクールで『孫子』が非常に重視されているのですが、それはなぜでしょうか。その理由は、ビジネスの世界で用いられている戦略論にあります。この戦略論は、マーケティング戦略論に終始しているきらいがあるのですが、それでは本当の戦争戦略論はどこにあるのか、と徐々に関心が出てきます。つまり、マーケティング戦略論の前提としての戦争戦略論をみんなが欲しているのだと思うのです。
この場合、最初に手を出すのは、クラウゼヴィッツの『戦争論』が多いでしょう。しかし、クラウゼヴィッツの『戦争論』を読んでみても、何か物足らないと感じる。より根源的な戦略論はないかということで、自ずと『孫子』の戦略論にいきつくということになります。
われわれ漢籍を研究する人間のあいだでは、『孫子』『呉子』『六韜』『三略』の「孫呉韜略」と呼ばれる4篇については、最低限読了することになっております。『孫子』と『呉子』は非常に似通ったもので、本質的戦略論としての思想・哲学がしっかり基礎づけられています。さらに具体的な戦法も詳しく明示されています。
●「戦わずして勝つ」ことを訴える『孫子』のユニークさ
近代戦争戦略論で有名なリデル=ハートというイギリス人がいます。リデル=ハートという人は『孫子』読みで有名で、西洋世界で最も読み込んだ人ではないかと思います。それゆえ、リデル=ハートの機甲戦略論などにも『孫子』は反映されています。また、海洋戦略論という分野では、マハンという人が有名ですが、マハンの海洋戦略論にも『孫子』の影響が色濃く見られると私は思います。
このように、幅広く影響を及ぼしている『孫子』の原文を読んでみると、戦略なるものの本質がよく分かります。『孫子』の主張の最も重要な点は、周知の通り「戦わずして勝つ」ということです。戦略論でありながら「戦わずして勝つ」という主張は、論法として矛盾しているという意見を聞くことも多いのです。しかし、決してそうではなく、むしろ戦いなどしなくても勝てるほどの守備を万端整えることなくして、国家の安定はないといっているのです。
そういう意味では、この「戦わず...