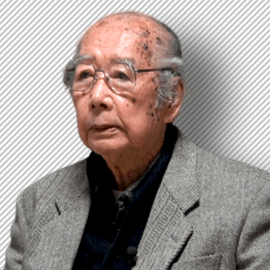●経済活動を支えたヒューマニズム
── その静岡でつくった商法会所ですが。
童門 はい。
── その商法会所もそうですし、今の第一銀行もそうですけれども、渋沢としては、要するにお金をうまく回していくことで、資金に困っているが力のある人にお金を融通して、彼らが事業を起こして儲けるようになってくれば、それが返ってくるし、利子も返ってくる。経済のまさに中核にあるような機能で、本来、資本主義の社会ではこれこそ非常に重要な機能だと思いますが、フランスで見てきたこれをそのままやったわけですね。
童門 そうです。
── ある意味では、自分自身がお金がなくて助けられたことを、日本でもう一回やろうと。
童門 おっしゃる通りです。自分が、困った立場、どうしようか苦しむ立場に置かれたから、むしろその経験を一つの武器として生かして、日本に持ち込んで、同じような思いをする人を救わなきゃいけないという。ヒューマニズムでしょうね。
その後の渋沢さんは、最初にお話したように、あなたが今言われたような趣旨で企業を立ち上げることはもう大賛成で、企業によって国ではやれないいろんな補完事業がありますよね。今でいうガード(警備)の仕事とか、昔の逓信省などがやるような、流通(物流)の仕事。これらは今はもう全く民間で機能しているでしょ。だから、そういうことじゃないかな。政府がやらなきゃいけないんだけれども、まだやれない、あるいは永遠に金の関係でやれない事業を、民間がやってくれるなら大いにそれを応援しようということかなと。
そうして、500だか600だか、会社を立ち上げるわけです。その中には、うまくいかなかったものもあるかとも思うんですけどね。ただ、そのために渋沢さん、責任を負って、必ずその株を自分でも買っています。だからその保証はしているんですね。
●生涯で唯一変わらなかった肩書「養育院院長」
童門 渋沢さんは、名刺の肩書が始終変わります。
── はい。
童門 だけど、変わらないで、ずっと残っていた肩書が1つありましてね。それが「養育院院長」という肩書なんです。
── 養育院というと、孤児の福祉施設でしょうか。
童門 いえ、老人(年寄り)で身寄りのない人を収容するんですね。それから、今言われた孤児院も同時につくるんですよ。それもいきさつがあります。江戸時代、徳川八代将軍・吉宗は割合に民...