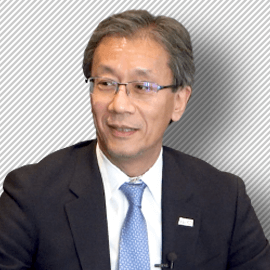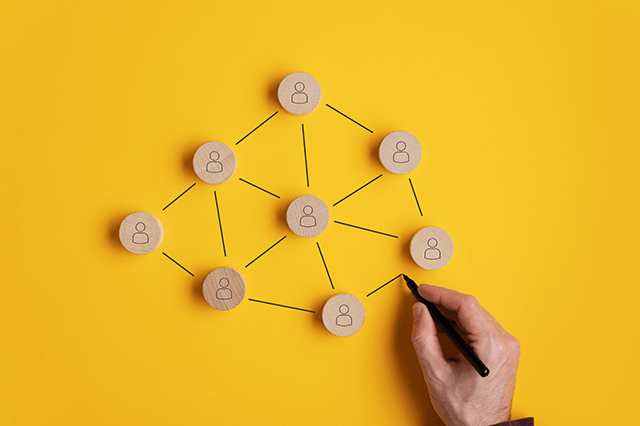●女性理事を過半数にする東大改革
―― 先生、今日はお忙しいなか、お時間をいただいて、ありがとうございます。
藤井 いいえ。こちらこそ、ありがとうございます。
―― 私が非常に驚いたのは「最初に、女性活用でダイバーシティを実現するぞ」ということで、いきなり理事の半分が女性になりました。まず、このあたりからお聞かせ願えますか。
藤井 ありがとうございます。もともと私には、女性のなかにも非常に優秀で「一緒に仕事ができたらいいな」と思っていた方々がいらっしゃいました。今回、そういうなかでお願いをしたところお引き受けいただけて、あのような布陣になったということです。
―― やはりリソースをたくさん持たれていたことが大きいですね。あと東京大学のなかにいらしているし。
藤井 そうですね。私はもともと学内の生産技術研究所(生研)の出身ですけれども、生研のなかだけではなく、いろいろ全学的な仕事をしていましたので、そこでもともと、いろいろな交流があったということです。
やはり今、世界の状況を見ても、非常に変化が大きくなっていると感じています。とくに感じているのは、世界のなかのものの考え方の変化です。いろいろな価値観や境遇を持つ人々がいるし、地球の環境もそうですけれども、今までのようなリニアなものではありません。
―― (従来の)延長線上にはないということですね。
藤井 いわゆる経済的な発展の延長線だけでものを考えればいいということではなく、全体としてのいろいろなことに気を配らねばならない。経済や物質的なことだけではなく、文化的・社会的な全体の発展を考えなければいけない時期に差し掛かってきていると思います。
●さまざまな価値観を架橋する「対話と共感」
藤井 それを考えると、大学というのはいろいろなものをつないでいくような役割を果たせる存在だと感じます。ですから、ぜひそういうかたちで東京大学が人類や世界の発展に貢献できるようなことをやっていきたいと思っています。今は、まさにここからそれを始めたいというふうに感じているところです。
―― 「知の構造化」の拠点ですね。
藤井 そうですね(笑)。ある意味、そう言うのかもしれません。「知の構造化」については、昔お聞きしていました。これをベースに、人と人をつないでいく、組織と組織をつないでいく、さまざまな価値観の間をつ...