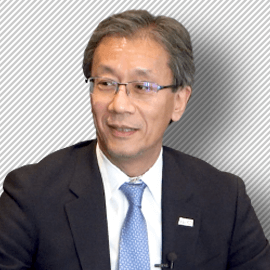●学生の高いクオリティを生かした社会実装実験
―― 東京大学の強みについてですが、やはり北京大学やソウル大学や東京大学は、入学した段階の学生のクオリティがこれだけ高いところは、世界にもあまりないことだろうと思います。
藤井 そう思います。相当にクオリティが高く、とくに日本の場合は数学のレベルが非常に高いです。また、総合力というのか、総合的な教科のバランスも含めて相当にレベルが高いと思います。
―― そうですよね。「社会実装」の実験をするときに、実は東京大学が非常にいい学生さんを集めている。五神真先生(前総長)が中心になって行った社会実装実験で、(2020年11月から2021年1月までで)赤門のところのトイレを直すときに学生を使ったら、ものすごくいいアイディアが出てきたという話を聞きました。
藤井 そうですね。非常に短期間にすばらしい提案がたくさん出てきました。本当に学生の地力に驚きました。
―― あの話はかなり印象に残っています。藤井先生は、あらゆる場所でキャンパスのデジタル化をという話をされていますが、これに関連しても学生に社会実装させるような機会や素材がたくさんありますね。
藤井 ああ、そうですね。まだ詳しいところまで検討を進めてはいませんが、デジタル化の一つの観点として、学生に使ってもらえるアプリを開発したらどうかと議論しているところです。アプリができたら、卒業したときには「卒業生版」にして入れ替えて使えるようにしたらどうかなど、いろいろなアイディアがあります。今おっしゃっていただいたように、ここはむしろ学生たち自身からアイディアを聞いて進められたらいいのかもしれないですね。
●机の上で学んだことを、社会で活かす場をしっかり設けたい
―― 種子島を訪れたことがあります。宇宙センターでロケットをやっているところですが、東大の研究者や学生がたくさんいて、島全体がかなり活性化している。島の高校生に東大の学生さんたちがいろいろ教えてあげているので、ロケットだけではなく、水の話など非常に詳しいのです。あれには相当驚きました。種子島で、東京大学と東京大学の学生さんによる「社会実装トライアル」が進められているのですね。
藤井 ああ、そうですよね。長らく関わってやっておられますね。
―― あれをやると、地域の力が全体的に上がってくる。また、(SDGs策定にも関わった)ジ...