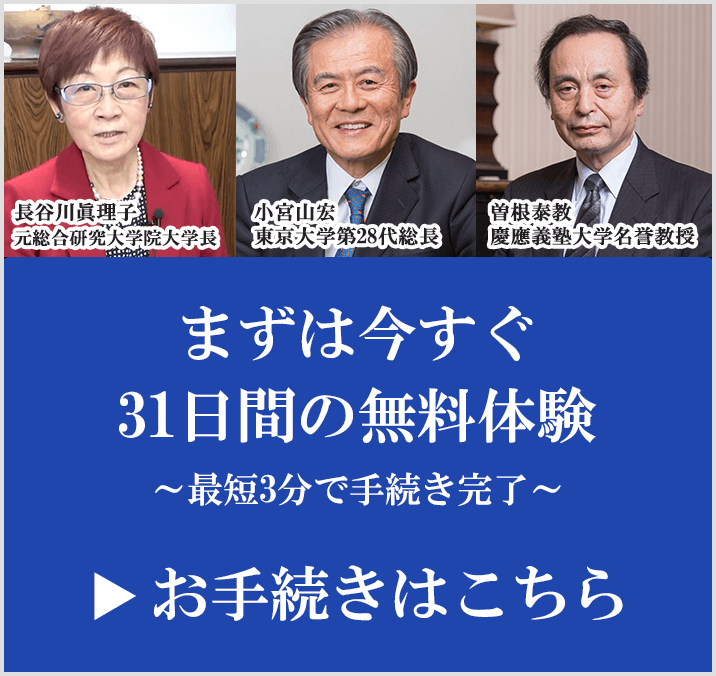●実際に活用されている不便益なモノ
こういう話をすると、「それって、ポジティブシンキングですか?」とか、「昔は良かったねというノスタルジーですか?」と言われることがあります。
確かにここまでの例は、私が後づけ的に「これ、不便益ではないか」と説明しただけなので、そう思われるかもしれません。しかし、実は違います。世の中には、積極的に不便であることをデザインに活用する例がたくさんあります。
例えば、「バリアフリー」という言葉は皆さん聞いたことがあると思います。これに対して、山口県山口市のデイケアセンターでは、「バリアアリー」ということをやっています。
日本語が分かる人なら、「フリー」と「アリー」がダジャレになっているのが分かると思います。これは、あえてデイケアセンターの中に軽微なバリアをしつらえ、入居者の方がそのバリアを超えることで、日々の生活で身体能力の衰えるスピードを経験するという、とても人気な施設だそうです。
このように私は、いろいろなところで人がやったことを勝手に不便益認定して回っています。勝手に不便益認定その2は「足漕ぎ車椅子」です。その名も「Cogy」です。
車椅子は、もともと足の不自由な方のためのものですが、足で漕げとはどういうことなのでしょうか。なんと不便な製品だと最初私は思いました。しかしよく聞いてみると、車椅子のユーザーは片足しか動かないとか、力が弱まってバランスが取れないだけの方もいらっしゃいます。そういう人たちにとって、自分の足で移動できるということは、電動で勝手に動いてくれることよりもクオリティ・オブ・ライフを上げるため、喜ばれるのだそうです。
さらに、この写真のペダルのところを見てもらうと、ソケットが付いています。オプションでソケットを付けることができるそうなのですが、両足を挿して漕ぐと、動く方の足で漕いだときに動かない方の足もつられて動くようになっています。それによって、動かない方の足を司る脳の部位に反応が戻ったという報告があるそうです。これはリハビリにも使えるのではないかといわれています。
勝手に不便益認定その3は「デコボコ園庭」です。園庭をデコボコにして、園児をこけさせようと画策する園長先生がそこそこいらっしゃ...