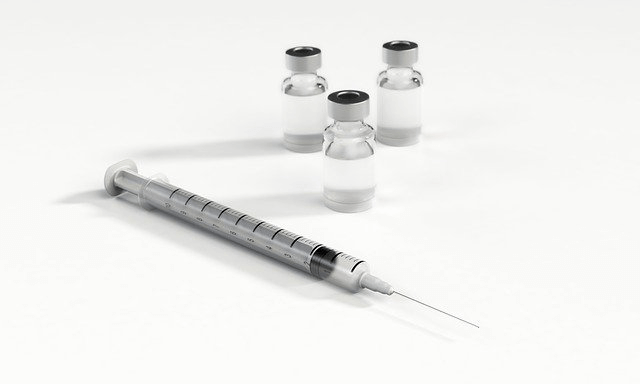●タンパク質医薬の優れた特徴
―― 続きまして、タンパク質がどのように身体に働いていくのか、またその詳しいメカニズムについて教えていただきたいと思います。
内田 はい。こちらですね。
このタンパク質は特定のタンパク質とだけ相互作用する特徴を持っています。ここで青、赤、黄、緑という4種類のタンパク質があったとします。この青のタンパク質は、赤や黄のタンパク質とはあまり形が合わないので、安定に結合していることはできません。しかし、この緑のタンパク質とはちょうど形が合っていて、フィットします。したがって、緑のタンパク質とだけ安定に相互作用します。このように、特定のタンパク質とだけ相互作用ができる点は、生命機能を維持する上でも重要であり、医薬品としても優れた特長です。
例えば、こうして緑のタンパク質のような特定のタンパク質とだけ相互作用することによって、緑のタンパク質が実際に担っている生体内のプロセスにちゃんと介入することができます。また、他の意図しないタンパク質とは相互作用しないので、副反応も起きないと考えられます。
では従来の医薬品はどうだったかというと、実は「低分子薬剤」といって、タンパク質よりもっと小さい分子が薬として用いられていました。こういった小さい分子を使うと、さまざまなタンパク質にくっついてしまうので、高度な機能を担うことはできず、副反応が起きてしまう懸念もあります。
●タンパク質医薬の歴史
内田 このタンパク質医薬の歴史について簡単に説明します。タンパク質医薬は1980年代初頭にインスリン製剤が実用化されたのを皮切りに、特に2000年以降、「抗体医薬」というのが、がんやリウマチなど、さまざまな病気に対して応用されるようになりました。今やこの抗体医薬は現在の医療になくてはならないものです。
右上に実際の世界医薬品売上上位トップ10を示しています。そのうち、なんと7品目がこのようなタンパク質医薬という状態です。ただ、このタンパク質医薬にはまだまだ問題があります。
製造や精製の過程が非常に煩雑で、そのために経済的コストがかかる他、そうして高いお金をかけて実際投与しても、ヒトに投与すると速やかに代謝されて、効果が消失することが挙げられます。
さら...