●1950年代に分かった「脳の自発的活動」としての睡眠
―― 西野先生、今回は「睡眠はそもそもなぜ必要なのか」というお話をうかがいたいと思いますが、人間というのはなぜ寝るのでしょうか。
西野 夜は非活動期ですから、そのときに睡眠を行うということは、結局は日中の活動を上げて健康な生活を送るということだと思うのですね。
私の専門は睡眠医学なのですが、睡眠医学というのは非常に歴史が浅いものです。例えば1950年の時点では、睡眠はあまり大した役割をしておらず、「疲れを取る」「眠気の放出」程度のこととしか思われていなかったのです。
ところが、そこから二つの大きな発見があります。一つは、それまで睡眠は受動的なもので、部屋が暗かったり音がなかったりすれば勝手に眠ってしまうと考えられていました。ところが動物実験で、「感覚遮断」といってそうした音が聞こえない、光が感じられない状態にしてみても動物は寝ることがなく、むしろ脳のある部位の活動を止めるようなことをすると、寝たような状態に達することが分かりました。
今では当たり前のことなのですが、睡眠は脳の自発的な行動であり、脳のある部位が覚醒を維持するために活動を続けなければいけないということが分かりました。つまり、その活動が減絶すれば睡眠が引き起こされるということです。それが分かったのが、70~80年前です。
●「レム睡眠」の発見と記憶を整理する役割
西野 ほぼ同じ頃に、レム睡眠の発見がありました。レム睡眠の発見というのは現象の発見です。その発見は、アメリカでも日本でもですが、日本では東京大学の時実利彦先生、フランスではリヨンのミッシェル・ジュべー氏、アメリカはシカゴ大学のユージン・アセリンスキー教授とナサニエル・クレイトマン教授、そしてウィリアム・C・デメント氏です。
彼らの業績により、寝ているときにも起きているときと同じように脳が活発に動いて夢を見るような睡眠があることが1950年代に分かったのです。
それからは盛んに「レム睡眠の役割」ということが研究されます。なぜそういった睡眠があるのか。その中から、レム睡眠が脳を活発にさせる、夢を見させる、その間に記憶を整理して定着させるということが分かってきました。
この発見により、それまで睡眠にあまり興味のなかった神経科学者たちが、睡眠研究に興味をもち始めます。そこから...











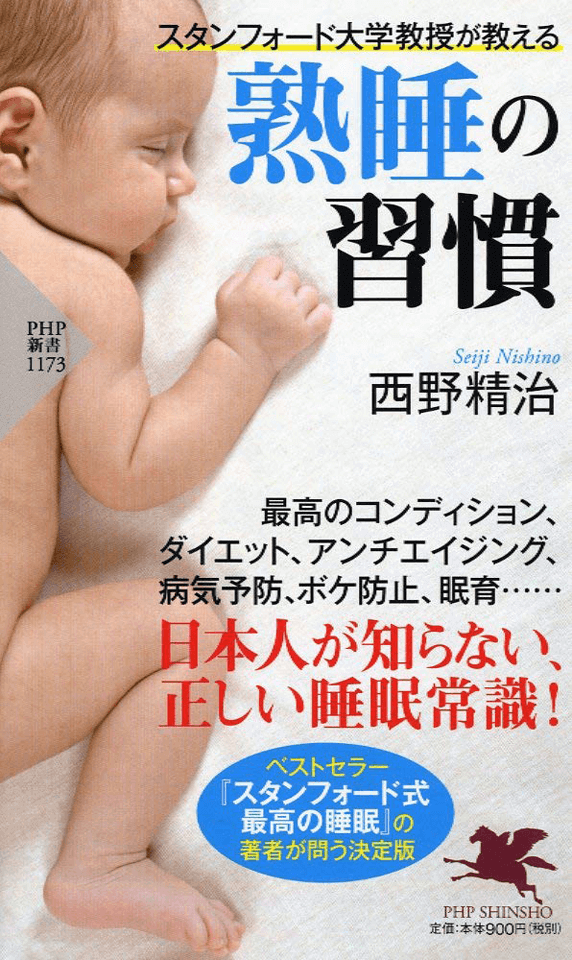

(西野精治著、PHP新書)