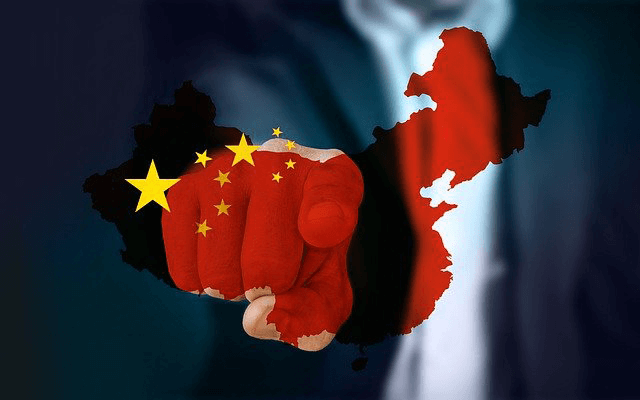●「中国の夢」に向かって突き進む習近平政権
非常に大きい文脈の中で米中対立は考えたほうがよいのではないかというのが、私が前回まで大きいコンテクストを申し上げてきた理由です。
米中対立ということで、もうご承知の通り、習近平氏は「中国の夢」と言っています。もうすでに2017年の党大会ではっきり「強国」という言葉を頻繁に使うようになってきています。2018年には憲法を改正して、参戦規定も止めてしまいました。ついこの間の中央委員会総会(2021年11月)では、歴史の見方も変えてしまいました。ここには書いていませんが、習近平中心の歴史の見方になったのです。
そこでの基本的な判断は、世界の趨勢は「中国の夢」を実現する好機であるという考え方です。この場合の「中国の夢」は“China Dream”であり、“Chinese Dream”ではありません。つまり、国が偉大になる夢です。中国はこれからも台頭しますが、米国は衰えると思っています。しかし、2040年あるいは2045年頃を見通すと、中国には少子高齢化の未来が待っています。そのため、「中国の夢」を実現する時間、あるいはそのウィンドウは限られています。たかだか20年ほどしかありません。だから、その間に何としても自分がやるというのが習近平氏なのだと思います。
●米中では、ルールメイキングにおける違いがある
歴史的に見たときに、その転機はいつかというと、私はほぼ間違いなく2008年の世界金融危機だと考えています。その後、まだ胡錦濤時代ですが、中国の党と国家は「韜光養晦(とうこうようかい)」から自己主張へと動きました。習近平氏が主席になったらすぐにバラク・オバマ大統領にG2の提案をし、同時に周辺外交ということで、「一帯一路」を言い始めました。
特に地域秩序について私自身が関心を持っていることですが、仮に自分を中心とした秩序を作ろうとすれば、何らかの原理が要ります。これは別に中国とアメリカだけではなくて、かつては日本もそういう秩序を作ろうとしました。そして中国の場合、原理は何かというと、「中国はどんな国よりも大きいのだから、小国は言うことを聞け」ということで、それがどうも中国の基本的な考え方であると私は思います。実はこれは帝国的ルールメイキングの...