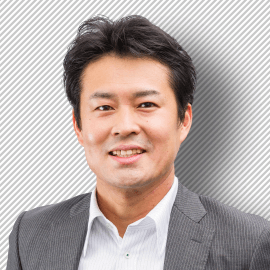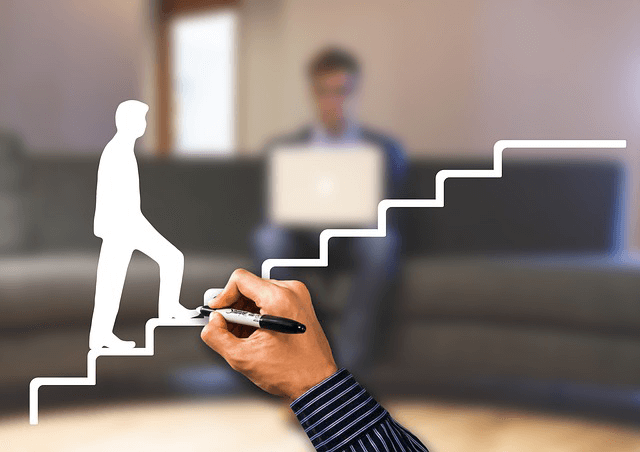●常日頃からキャリアについて考えることが大事
―― プロティアンという考え方の場合、カメレオン型ではなく本質が変わっていくというお話を最初の講義でお聞きしました。今まで、変わっていくといえば「結局、転職だよね」というイメージがあったと思います。ところが、先生のお考えでは変わっていくこと=転職ではなく、要は自律してキャリアを自分に取り戻すということですね。
そうなると、たとえ同じ会社にずっといたとしても、会社から「これをやりなさい」「あれをやりなさい」と言われたメニューだけをやるのではない。その会社にいる前提、自分の仕事にどう生かせるかという視点で、前回いわれた朝活などの外の交流を行い、知見を深めていくというイメージが近いのでしょうか。
田中 そうです。これは今、本当に重要なポイントだと思いますが、キャリアはいつ考えるものでしょう。普通は転職する直前に考えます。これは、「キャリアの非日常」だと私は思っています。仕事があって、「このままでは、どうだろう。転職しようか」というときだけ「これからのキャリアはどうしよう」というのは、常日頃からキャリアを考えていないということなのです。
私自身がプロティアン・キャリアでお伝えしているのは、「常日頃からチェックしていいのではないか」ということです。私など、最近はよく医療系の論文を読んでいますが、なぜかというと、年に一度の健康診断で少し数値が悪いと思えば気になるからです。キャリアもそれと同様で、常にコンディション・チェックを行い、日常的にトリートメントするのが大切だと思っています。
これからの1年、3年、5年というふうに刻めば、その中には一つのアクションとして、結果的にキャリア選択として「転職」を迎えることもあるかもしれない。しかし、キャリア形成の観点でいうと、これまでは30年、40年のスパンだったのが、それ以上に長くなっていく。これを踏まえると、やはり持続可能な形、皆さんそれぞれのリズムでいいから、キャリア形成を継続していってほしいと思うわけです。
●キャリア形成に重要な「二つのA」
田中 プロティアン・キャリアによるキャリア形成の重要なポイントとして、皆さんにお伝えしておきたいことが二つあります。
スライドを準備しましたので、「二つのA」と覚えてください。一...