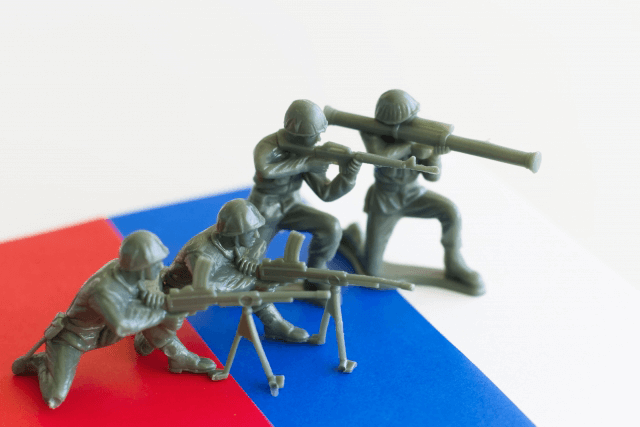●ロシアによる核使用の脅威と民主主義国の条件
皆さん、こんにちは。ロシアのプーチン大統領とその後のウクライナ戦争、あるいは日本との関わりなどについて、いろいろと触れてきたわけですが、日本国民の一番の関心事、懸念材料というのは、世界の人々と同じように、プーチン氏がかつて戦術核の使用を匂わせたことです。つまり、核恫喝が恫喝だけで終わるのかです。あるいは、実際に戦術核が使われるのかというのは、大変大きな問題点です。
これは特に、原爆を使われて多くの被害者を出した日本国民が、揺るがせにできない点です。同時に、世界中にその核というものの使用の怖さというものが、理念や言葉だけではなくて、現実あるいは実際の事実として起こり得るということを意味しているのですね。そうなった場合、今後の国際秩序というのは、どうなるのか、どういう影響を及ぼすのかというのは、大変重要な問題です。
基本的に民主主義国家同士は戦わないとよくいわれます。これは20世紀にフランシス・フクヤマが『歴史の終わり』(The End of History and the Last Man)という中で強調した見方です。もちろん、これの揚げ足を取って、「いや、第一次英米戦争と第二次英米戦争、つまり独立戦争と第二次英米戦争で、実際はカナダを主力とする軍隊がワシントンを陥れて、ホワイトハウスを焼いた」と。これは密かにカナダ人が、心の中で何か自負している独特の経験なのです。
実際はカナダなのですが、法的にはイギリスで、五大湖においても海戦が行われました。だから、民主主義国家間でも戦争があったではないかという混ぜっ返しになったのです。フクヤマもおそらく言いたかったことで、そして、私もフクヤマのほうに寄せて考えるのは、確立された20世紀の自由と民主主義を価値観の基本とする国家が民主主義国家だとすれば、民主主義国家はたしかに互いが戦ったということはないということです。ほぼないと言ってよろしいわけです。
したがって、ここから引き出されるのは、民主主義国家の間では、核戦争、核を使用するということはあり得ない、核による恫喝もしない、ということ。これは基本的に重要な民主主義国家の資格要件だろうと私は思います。核を使うということをあえて発言した、プーチン氏は、やはりそういう意味でも民主主義国家のリーダーとしての資質はない。そもそもG8として、G7プラス1になる...