テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
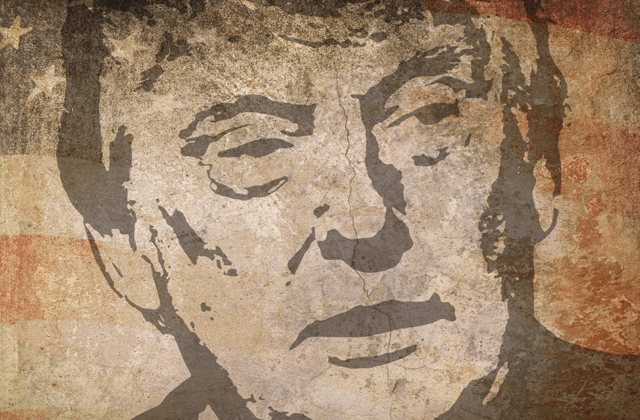
トランプ大統領に欠けている国際社会で重要な2つの概念
2017年6月1日、トランプ大統領が地球温暖化対策の国際枠組み・パリ協定から離脱表明をし、物議をかもしました。大統領補佐官イヴァンカ氏をはじめとする周囲の反対をおしきっての離脱は、またしても「アメリカに利益を取り戻す」という米国第一主義が理由になっているようです。
もともとアメリカはモンロー主義を外交方針の伝統としてきたのですが、この一種の孤立主義とトランプ大統領の一連の保護主義政策とは明らかに異なる、と政治学者で慶應義塾大学大学院教授の曽根泰教氏は語ります。
トランプ大統領は四方八方に「世界最強の国アメリカを取り戻す」とアメリカファーストを繰り返しており、他国に余計な干渉をしないと同時に手だしもさせないというアメリカ本来の孤立主義と、トランプ流介入を手段とする保護主義とは随分違っているわけです。
その1つが、「比較優位の原則」という概念です。これはイギリスの経済学者デヴィッド・リカードが提唱した概念で、「自由貿易では各国が最も生産性の高い分野に力を入れることで、いずれの国も利益を得ることができる」というもの。つまり、生産性を国全体ではなく、優位な産業分野別で比較すれば、双方いずれも高品質のもの、サービス、そして収益を獲得することができるという説で、現在ではこの原則に則り、多くの経済学者が自由貿易を議論の前提としています。
この概念はなかなか理解するのが難しく、一般的には「自由貿易でダメージを受ける人が出るから、保護主義で自国の利益を守る方がいい」と考えてしまいがちです。2017年1月23日、TPP離脱の大統領令に署名したトランプ大統領も、この比較優位の原則をあまり理解していないのではないか、と思わざるを得ません。
公共財は、非排除性、非競合性という特性を持っています。公園という公共の場を考えてみましょう。公園にはウォーキング、犬の散歩、緑に囲まれてゆったり過ごすなど、さまざまな目的をもったさまざまな人が自由に出入りします。公園の存在そのものが、多くの人に公平の利益をもたらしていて、その消費に関する競合性もありません。
また、公共財を論じる場合、フリーライダーの存在を忘れてはなりません。つまり、費用を負担することなく、ただでその財やサービスを享受する「ただ乗り」の人が発生することを認めざるを得ないのです。都立の公園なら、東京都民は税金を払うことでその管理、維持に貢献しているわけですが、だからといって他県民を「フリーライダー」として入園禁止にするようなことはできません。
また、トランプ大統領が主張する日本に対する米軍の駐留費用の負担増については、今のところ強硬姿勢を引っ込めてはいるものの、そこには「直接関係する誰かが必ず費用を負担する」というクラブ財的発想が見え隠れしています。やはりこの点も、国際公共財に対する根本的な理解不足といえる、曽根氏は指摘します。
考えてみれば、「地球」も生物すべてにとっての公共財のようなもの。パリ協定離脱を発表したトランプ氏は、この唯一無二の公共財をどのように考えているのでしょうか。TPP、安全保障、地球環境等の問題に、介入、ディールで当たろうとするアメリカ大統領の動向に世界の目が注がれています。
もともとアメリカはモンロー主義を外交方針の伝統としてきたのですが、この一種の孤立主義とトランプ大統領の一連の保護主義政策とは明らかに異なる、と政治学者で慶應義塾大学大学院教授の曽根泰教氏は語ります。
アメリカ伝統の外交方針-モンロー主義
アメリカ外交は、1823年、第5代大統領ジェームズ・モンローが年次教書で発表して以来、「モンロー主義」と呼ばれる独自の孤立主義を基本姿勢として継承してきました。それは、対ヨーロッパとの関係において、南北アメリカ大陸の権益を確保しようとしたもので、「アメリカはヨーロッパ諸国の紛争に干渉しないが、アメリカ大陸全域に対するヨーロッパによるいかなる干渉にも反対する」という方針に基づいています。トランプ大統領は四方八方に「世界最強の国アメリカを取り戻す」とアメリカファーストを繰り返しており、他国に余計な干渉をしないと同時に手だしもさせないというアメリカ本来の孤立主義と、トランプ流介入を手段とする保護主義とは随分違っているわけです。
トランプ大統領は「比較優位の原則」を理解しているのか?
トランプ氏の一連の政策傾向を見て、曽根氏は「トランプ大統領は国際社会で重要な2つの概念理解に欠けているのではないか」と言います。その1つが、「比較優位の原則」という概念です。これはイギリスの経済学者デヴィッド・リカードが提唱した概念で、「自由貿易では各国が最も生産性の高い分野に力を入れることで、いずれの国も利益を得ることができる」というもの。つまり、生産性を国全体ではなく、優位な産業分野別で比較すれば、双方いずれも高品質のもの、サービス、そして収益を獲得することができるという説で、現在ではこの原則に則り、多くの経済学者が自由貿易を議論の前提としています。
この概念はなかなか理解するのが難しく、一般的には「自由貿易でダメージを受ける人が出るから、保護主義で自国の利益を守る方がいい」と考えてしまいがちです。2017年1月23日、TPP離脱の大統領令に署名したトランプ大統領も、この比較優位の原則をあまり理解していないのではないか、と思わざるを得ません。
「公共財」ならではの特性
もう一つの重要な概念、それは公共財に関するものですが、曽根氏は安全保障問題の側面から、トランプ大統領の概念理解に疑問を投じています。公共財は、非排除性、非競合性という特性を持っています。公園という公共の場を考えてみましょう。公園にはウォーキング、犬の散歩、緑に囲まれてゆったり過ごすなど、さまざまな目的をもったさまざまな人が自由に出入りします。公園の存在そのものが、多くの人に公平の利益をもたらしていて、その消費に関する競合性もありません。
また、公共財を論じる場合、フリーライダーの存在を忘れてはなりません。つまり、費用を負担することなく、ただでその財やサービスを享受する「ただ乗り」の人が発生することを認めざるを得ないのです。都立の公園なら、東京都民は税金を払うことでその管理、維持に貢献しているわけですが、だからといって他県民を「フリーライダー」として入園禁止にするようなことはできません。
安全保障条約はクラブ財とはわけが違う
以上のように、公共財の概念を整理すると、安全保障条約というものも一種の公共財と考えることができます。日米安全保障条約は、東アジア全域の安全秩序に関わっており、そこにはフリーライダー的存在の国があって当然。会費を払った会員だけがその恩恵に預かるクラブ財とはわけが違います。また、トランプ大統領が主張する日本に対する米軍の駐留費用の負担増については、今のところ強硬姿勢を引っ込めてはいるものの、そこには「直接関係する誰かが必ず費用を負担する」というクラブ財的発想が見え隠れしています。やはりこの点も、国際公共財に対する根本的な理解不足といえる、曽根氏は指摘します。
考えてみれば、「地球」も生物すべてにとっての公共財のようなもの。パリ協定離脱を発表したトランプ氏は、この唯一無二の公共財をどのように考えているのでしょうか。TPP、安全保障、地球環境等の問題に、介入、ディールで当たろうとするアメリカ大統領の動向に世界の目が注がれています。
人気の講義ランキングTOP20
実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない
長谷川眞理子










