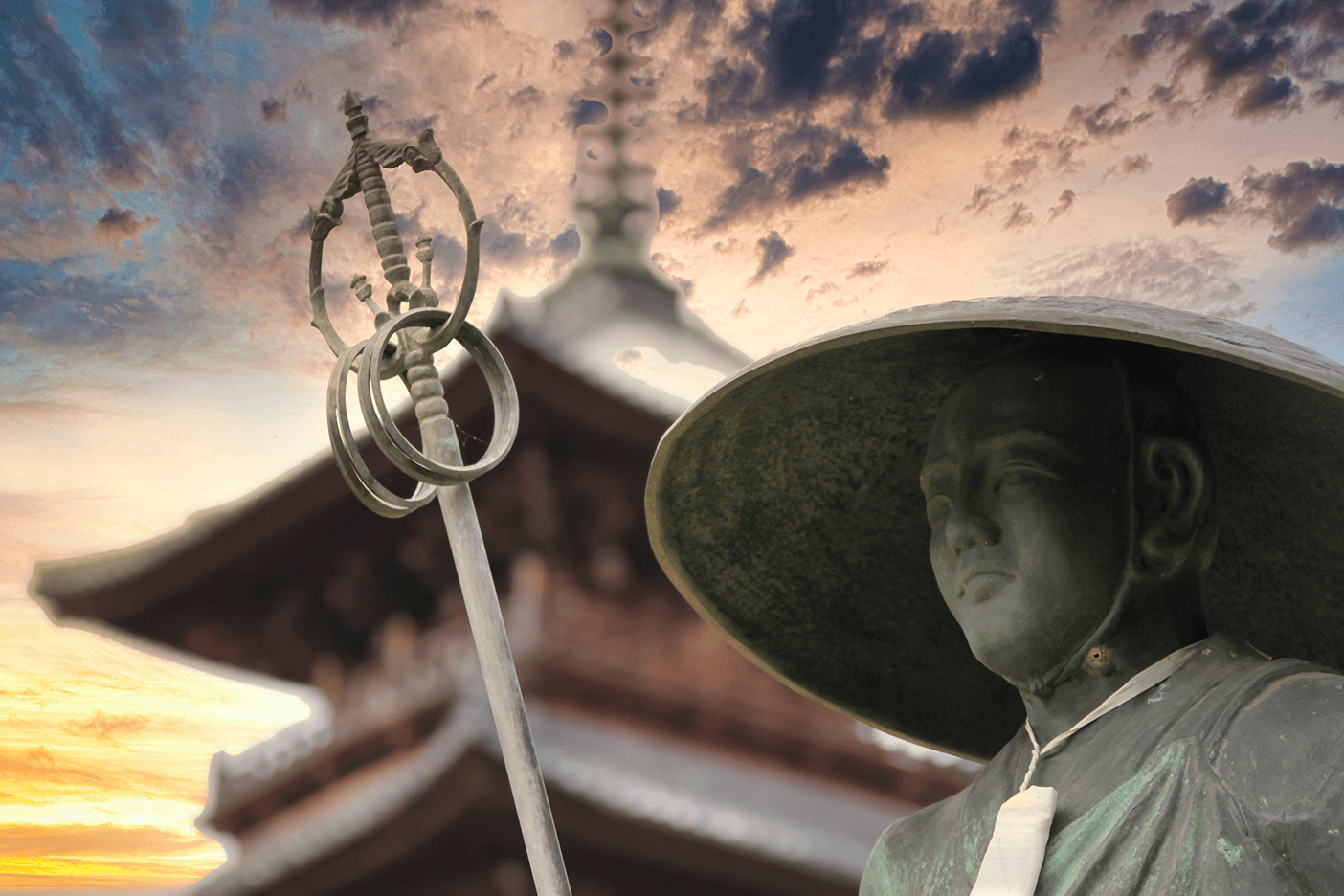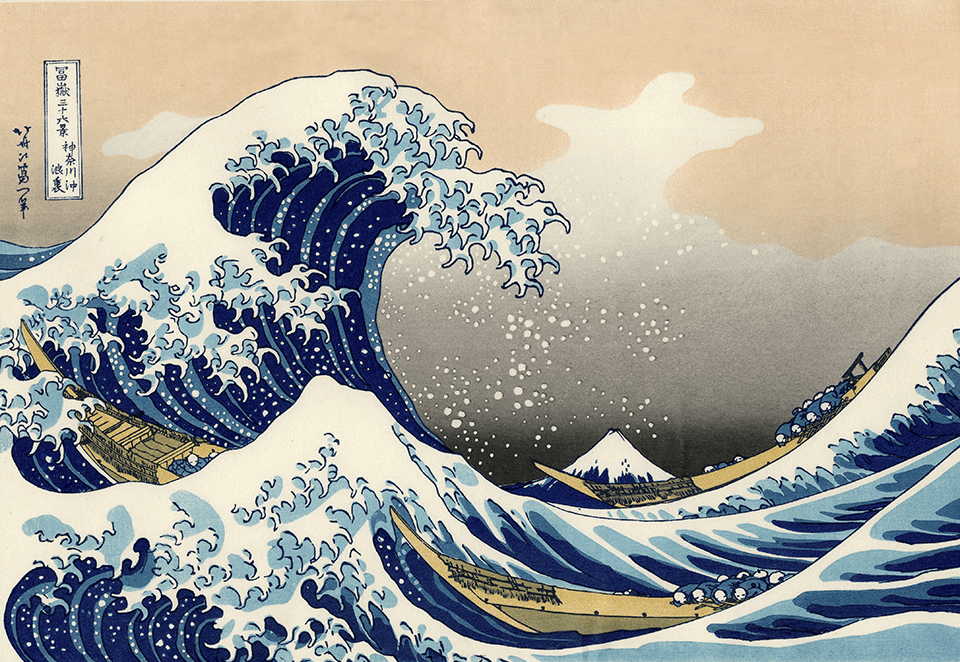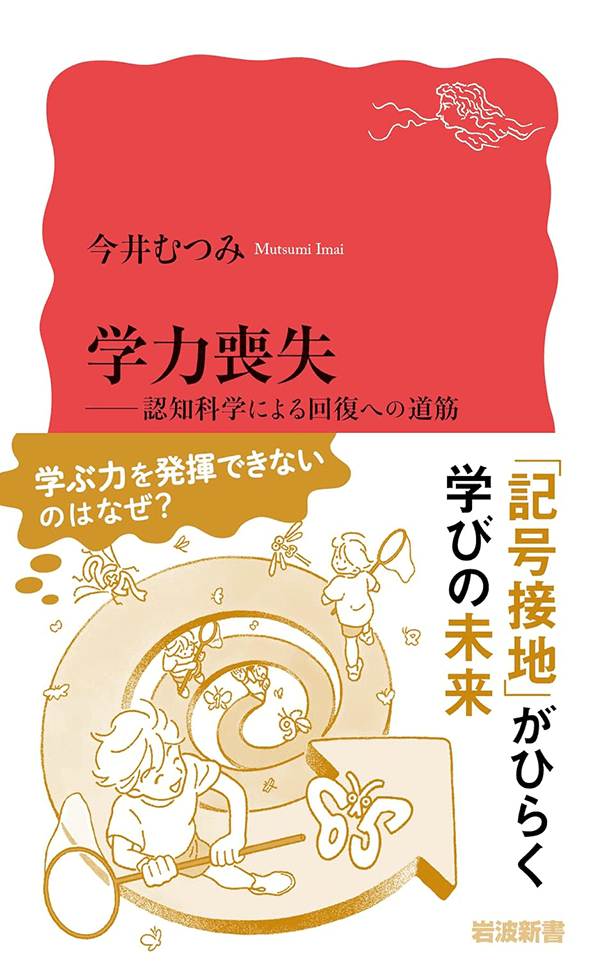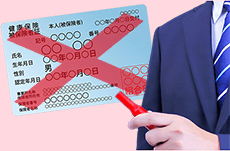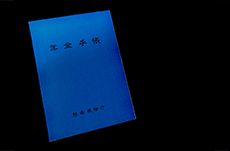社会人向け教養サービス 『テンミニッツ・アカデミー』 が、巷の様々な豆知識や真実を無料でお届けしているコラムコーナーです。

年収別にみる貯蓄額の平均は?
不透明な世界の動向、ますます感じる将来の不安。いざとなった時に頼りになるのはやはり貯金です。あればあるだけ安心できますが、隣の人はどれだけ、また、どのように貯めているのでしょう。
たくさん稼いでいればさぞや貯金も、という感覚があります。資産家など出自によって貯蓄のバラツキがあるでしょうが、年収と貯金はどのような関係にあるのでしょう。
仕事や勤め先である程度の年収は予測できますが、貯蓄まではなかなか知ることはできません。そこで頼りにしたいのが、総務省統計局のデータです。
総務省統計局では、貯蓄・負債編を含めた家計調査を行っています。今回は2017年の調査データをもとに、年収別の貯蓄額について調べてみました。
<年収:貯蓄額/持ち家率/平均世帯主年齢>
200万円未満:397万円/56.5%/45.2歳
200万円以上-250万円未満:843万円/47.3%/46.6歳
250万円以上-300万円未満:587万円/43.6%/45.9歳
300万円以上-350万円未満:839万円/55.5%/46.2歳
350万円以上-400万円未満:786万円/57.6%/46.4歳
400万円以上-450万円未満:878万円/62.3%/46.2歳
450万円以上-500万円未満:901万円/67.1%/46.3歳
500万円以上-550万円未満:908万円/68.0%/45.6歳
550万円以上-600万円未満:1171万円/71.7%/45.6歳
600万円以上-650万円未満:1120万円/74.2%/46.3歳
650万円以上-700万円未満:1055万円/78.6%/47.9歳
700万円以上-750万円未満:1172万円/73.6%/47.0歳
750万円以上-800万円未満:1489万円/82.9%/47.9歳
800万円以上-900万円未満:1548万円/85.8%/49.2歳
900万円以上-1,000万円未満:1820万円/88.0%/49.5歳
1,000万円以上-1,250万円未満:1976万円/84.4%/50.6歳
1,250万円以上-1,500万円未満:2316万円/87.2%/52.8歳
1,500万円以上:3048万円/92.7%/53.5歳
このデータは、平均世帯主年齢から見ても分かる通り、二人以上の勤労世帯からの抽出になります。高齢化した全世帯モデルを平均するとさらに、貯蓄額と世帯主年齢はアップし、平均値貯蓄額1658万
(平均年齢57.3歳)となります。当然のことながら、年収に応じて持ち家率もアップしていくのが興味深いところです。
困ったときにすぐに使える通貨性の高い普通預金の額面を抽出するとこのような結果になります。
<年収:普通預金>
200万円未満:111万円
200万円以上-250万円未満:143万円
250万円以上-300万円未満:141万円
300万円以上-350万円未満:168万円
350万円以上-400万円未満:156万円
400万円以上-450万円未満:215万円
450万円以上-500万円未満:186万円
500万円以上-550万円未満:215万円
550万円以上-600万円未満:259万円
600万円以上-650万円未満:280万円
650万円以上-700万円未満:258万円
700万円以上-750万円未満:302万円
750万円以上-800万円未満:292万円
800万円以上-900万円未満:292万円
900万円以上-1,000万円未満:323万円
1,000万円以上-1,250万円未満:417万円
1,250万円以上-1,500万円未満:491万円
1,500万円以上:810万円
より現実感の高い額面になったのではないでしょうか。
たくさん稼いでいればさぞや貯金も、という感覚があります。資産家など出自によって貯蓄のバラツキがあるでしょうが、年収と貯金はどのような関係にあるのでしょう。
仕事や勤め先である程度の年収は予測できますが、貯蓄まではなかなか知ることはできません。そこで頼りにしたいのが、総務省統計局のデータです。
総務省統計局では、貯蓄・負債編を含めた家計調査を行っています。今回は2017年の調査データをもとに、年収別の貯蓄額について調べてみました。
平均すると年間収入691万円で貯蓄1233万円
総務省統計局には様々な統計データがあり、「年間収入階級別貯蓄及び負債の1世帯当たり現在高」を参照すると、年間収入691万で貯蓄1233万という平均値になっています。ご自身の世帯収入と比較して、いかがでしょうか?<年収:貯蓄額/持ち家率/平均世帯主年齢>
200万円未満:397万円/56.5%/45.2歳
200万円以上-250万円未満:843万円/47.3%/46.6歳
250万円以上-300万円未満:587万円/43.6%/45.9歳
300万円以上-350万円未満:839万円/55.5%/46.2歳
350万円以上-400万円未満:786万円/57.6%/46.4歳
400万円以上-450万円未満:878万円/62.3%/46.2歳
450万円以上-500万円未満:901万円/67.1%/46.3歳
500万円以上-550万円未満:908万円/68.0%/45.6歳
550万円以上-600万円未満:1171万円/71.7%/45.6歳
600万円以上-650万円未満:1120万円/74.2%/46.3歳
650万円以上-700万円未満:1055万円/78.6%/47.9歳
700万円以上-750万円未満:1172万円/73.6%/47.0歳
750万円以上-800万円未満:1489万円/82.9%/47.9歳
800万円以上-900万円未満:1548万円/85.8%/49.2歳
900万円以上-1,000万円未満:1820万円/88.0%/49.5歳
1,000万円以上-1,250万円未満:1976万円/84.4%/50.6歳
1,250万円以上-1,500万円未満:2316万円/87.2%/52.8歳
1,500万円以上:3048万円/92.7%/53.5歳
このデータは、平均世帯主年齢から見ても分かる通り、二人以上の勤労世帯からの抽出になります。高齢化した全世帯モデルを平均するとさらに、貯蓄額と世帯主年齢はアップし、平均値貯蓄額1658万
(平均年齢57.3歳)となります。当然のことながら、年収に応じて持ち家率もアップしていくのが興味深いところです。
普通預金で見てみると
平均値貯蓄額1233万円、そして、400万円以上~450万円未満の世帯でも878万円の貯蓄額になっています。ここでの貯蓄額は、普通預金といった流動性の高い普通預金と、将来のための定期預金、さらには生命保険、有価証券の合算数値になります。困ったときにすぐに使える通貨性の高い普通預金の額面を抽出するとこのような結果になります。
<年収:普通預金>
200万円未満:111万円
200万円以上-250万円未満:143万円
250万円以上-300万円未満:141万円
300万円以上-350万円未満:168万円
350万円以上-400万円未満:156万円
400万円以上-450万円未満:215万円
450万円以上-500万円未満:186万円
500万円以上-550万円未満:215万円
550万円以上-600万円未満:259万円
600万円以上-650万円未満:280万円
650万円以上-700万円未満:258万円
700万円以上-750万円未満:302万円
750万円以上-800万円未満:292万円
800万円以上-900万円未満:292万円
900万円以上-1,000万円未満:323万円
1,000万円以上-1,250万円未満:417万円
1,250万円以上-1,500万円未満:491万円
1,500万円以上:810万円
より現実感の高い額面になったのではないでしょうか。
働くお金として投資も視野に
限りなくゼロに近い低金利時代を生きる私たちにとっては、銀行に貯金することの意味を問いたくなります。今回のデータ「年間収入階級別貯蓄及び負債の1世帯当たり現在高」からは、年収の高さに応じて、有価証券の割合も増えてくることも当然のように読み取れます。投資にはリスクも伴いますが、人生に必要なお金のポートフォリオ、貯蓄の配分を見直してみるのはいかがでしょうか。<参考サイト>
・総務省統計局:家計調査┃貯蓄・負債編
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200561&tstat=000000330001&cycle=7&year=20170&month=0&tclass1=000000330007&tclass2=000000330008&tclass3=000000330009&result_back=1
・総務省統計局:家計調査┃貯蓄・負債編
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200561&tstat=000000330001&cycle=7&year=20170&month=0&tclass1=000000330007&tclass2=000000330008&tclass3=000000330009&result_back=1
~最後までコラムを読んでくれた方へ~
自分を豊かにする“教養の自己投資”始めてみませんか?
明日すぐには使えないかもしれないけど、10年後も役に立つ“大人の教養”を 5,600本以上。
『テンミニッツ・アカデミー』 で人気の教養講義をご紹介します。
なぜ空海が現代社会に重要か――新しい社会の創造のために
エネルギーと医学から考える空海が拓く未来(1)サイバー・フィジカル融合と心身一如
現代社会にとって空海の思想がいかに重要か。AIが仕事の仕組みを変え、超高齢社会が医療の仕組みを変え、高度化する情報・通信ネットワークが生活の仕組みを変えたが、それらによって急激な変化を遂げた現代社会に将来不安が増...
収録日:2025/03/03
追加日:2025/11/12
世界は音楽と数学であふれている…歴史が物語る密接な関係
数学と音楽の不思議な関係(1)だれもがみんな数学者で音楽家
数学も音楽も生きていることそのもの。そこに正解はなく、だれもがみんな数学者で音楽家である。これが中島さち子氏の持論だが、この考え方には古代ギリシア以来、西洋で発達したリベラルアーツが投影されている。この信念に基...
収録日:2025/04/16
追加日:2025/08/28
布団に入る何分前がいい?入眠しやすいお風呂の入り方
熟睡できる環境・習慣とは(3)睡眠にいい環境とお風呂の入り方
眠る環境は各家庭の状況や個人の好みによって大きく異なるが、一般的に「良い睡眠」のために望ましい環境はどのようなものだろうか。布団や枕などの寝具、エアコンなどの室温コントロールを含めた寝室の環境、また寝つきの良く...
収録日:2025/03/05
追加日:2025/12/07
葛飾北斎と応為…画狂の親娘はいかに傑作へと進化したか
葛飾北斎と応為~その生涯と作品(1)北斎の画狂人生と名作への進化
浮世絵を中心に日本画においてさまざまな絵画表現の礎を築いた葛飾北斎。『富嶽三十六景』の「神奈川沖浪裏」が特に有名だが、それを描いた70代に至るまでの変遷が実に興味深い。北斎とその娘・応為の作品そして彼らの生涯を深...
収録日:2025/10/29
追加日:2025/12/05
なぜ算数が苦手な子どもが多いのか?学力喪失の真相に迫る
学力喪失の危機~言語習得と理解の本質(1)数が理解できない子どもたち
たかが「1」、されど「1」――今、数の意味が理解できない子どもがたくさんいるという。そもそも私たちは、「1」という概念を、いつ、どのように理解していったのか。あらためて考え出すと不思議な、言葉という抽象概念の習得プロ...
収録日:2025/05/12
追加日:2025/10/06