テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
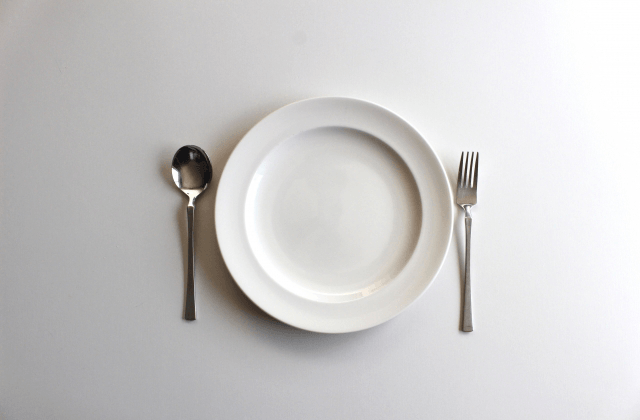
食事を1人で取る「孤食」の何が悪いのか?
電通総研「食生活ラボ」のコミュニケーション・プランナーである吉羽優子氏は、「日本で“孤食”という言葉を耳にするようになったのは、2000年代半ばからでしょうか」といいます。
吉羽氏の言葉が示すように、2001年に発行された『三省堂国語辞典 第五版』から「こしょく」には、「個食」と「孤食」が掲載されるようになっています(「個食」は第四版から掲載)。
「孤食」には「1人きりの食事」「1人ずつ食べるものが違う」「バラバラの時間に食事を取る」とい意味やニュアンスがあります。近年、「孤食」は増加傾向にあり、世代間を問わずに多様な社会問題になっています。
さらに興味深いことは、同調査での、1人で食べる「孤食」と、家族もしくは家族以外の主に気の合う人たちと一緒に食べる「共食」の比較です。5つの観点評価、おいしさ・量・楽しさ・賑やかさ・くつろぎで、「孤食」と「共食」を比較したところ、全てにおいて「共食」の方に、プラス面が高い結果がでました。
この結果からは、本来「何を食べるか」という選択の問題である、「おいしさ」や「量」にまで、「孤食」がマイナスの影響をおよぼしていることがわかります。
「孤食」の問題の1つに、一緒に食事をすることで育まれる連帯感や、食に関する知識や能力の習得機会を失うことがあります。特に受け身の立場で「孤食」となり、その弊害を被ることになるのが子どもです。
大正大客員教授・キユーピー顧問で、食と現代家族の調査・研究の第一人者でもある岩村暢子氏は、1960年以降に生まれた首都圏在住の子どもを持つ主婦を対象とした食卓の定点観測「食DRIVE」調査に基づき、離乳食時期から「1人食べ」育ちの子どもたちを取り上げています(『家族の勝手でしょ!』)。
子どものリクエストに応えて親とは違う食事を食べさせる家庭や、各自が勝手に好きな時間に好きな物だけを食べている家庭などを紹介し、「みんな一緒の食事」が大切だとは語りながらも、各自勝手な「食事の個人化」が進んでいることを明示し、健康面の問題や親子間の伝承の断絶等を危惧しています。
大妻女子大学家政学部教授で管理栄養士・医学博士の川口美喜子氏は、高齢者の「孤食」や偏食は栄養不足の原因となり、さらには「フレイル(虚弱・老年症候群)」につながる可能性があると警告しています(『週刊朝日』2018年5月4-11日合併号)。
川口氏は、一人暮らしの老人が多く住む団地で、毎週食事会を開催しています。「週一度の“身体に優しい食事会”だけでは、1週間の健康を保つ栄養補給にはなりません。ただ、みんなと一緒に食べれば孤食やフレイル防止につながる。そう思って、食事会を始めました」と語っています。
「孤食」や「食事の個人化」が増加する現代ですが、石毛氏は、人間以外の動物の食事は個体単位での完結が原則であるが、「“共食する動物”である人間の食事は、原則として、一人で食べるものではない<中略>そして、もっとも日常的な共食集団は家族である」と述べています。
さらに、「家族のかこむ食卓のない家庭が実現するとき、それは家族という制度が崩壊するときである」と警鐘を鳴らしています。そう考えると、「共食」に伴う家族単位の発生やコミュニティの連帯感の形成、文化の伝承や知識の継承などが、ヒトを人間にしたともいえるのかもしれません。
食事はもっとも身近で大切な生きるために欠かせない行為です。だからこそ手間や煩わしさもありますが、同時に誰にでも改善することや、よりよい形に変えていくことも可能なはずです。ライフスタイルを省みながらも、今よりもベターな食生活をめざして、「孤食」の弊害を意識し「共食」のよさを見直してみてはいかがでしょうか。
吉羽氏の言葉が示すように、2001年に発行された『三省堂国語辞典 第五版』から「こしょく」には、「個食」と「孤食」が掲載されるようになっています(「個食」は第四版から掲載)。
「孤食」には「1人きりの食事」「1人ずつ食べるものが違う」「バラバラの時間に食事を取る」とい意味やニュアンスがあります。近年、「孤食」は増加傾向にあり、世代間を問わずに多様な社会問題になっています。
「孤食」は「おいしさ」も減少させる
2006年にNHK放送文化研究所が行った「食生活に関する世論調査」の結果、5人に1人が「孤食」の夕食を取るという結果が出ています(『崩食と放食』)。さらに興味深いことは、同調査での、1人で食べる「孤食」と、家族もしくは家族以外の主に気の合う人たちと一緒に食べる「共食」の比較です。5つの観点評価、おいしさ・量・楽しさ・賑やかさ・くつろぎで、「孤食」と「共食」を比較したところ、全てにおいて「共食」の方に、プラス面が高い結果がでました。
この結果からは、本来「何を食べるか」という選択の問題である、「おいしさ」や「量」にまで、「孤食」がマイナスの影響をおよぼしていることがわかります。
「孤食」の最たる被害者は子ども?
「孤食」の背景には、「一人暮らし」といった家族単位に由来する理由が多いのはもちろんですが、家族と一緒に暮らしていても、生活時間のズレによって「孤食」の人が増えるという傾向がありました。「孤食」の問題の1つに、一緒に食事をすることで育まれる連帯感や、食に関する知識や能力の習得機会を失うことがあります。特に受け身の立場で「孤食」となり、その弊害を被ることになるのが子どもです。
大正大客員教授・キユーピー顧問で、食と現代家族の調査・研究の第一人者でもある岩村暢子氏は、1960年以降に生まれた首都圏在住の子どもを持つ主婦を対象とした食卓の定点観測「食DRIVE」調査に基づき、離乳食時期から「1人食べ」育ちの子どもたちを取り上げています(『家族の勝手でしょ!』)。
子どものリクエストに応えて親とは違う食事を食べさせる家庭や、各自が勝手に好きな時間に好きな物だけを食べている家庭などを紹介し、「みんな一緒の食事」が大切だとは語りながらも、各自勝手な「食事の個人化」が進んでいることを明示し、健康面の問題や親子間の伝承の断絶等を危惧しています。
高齢者も「孤食」に要注意!
他方、高齢化による一人暮らしの老人の「孤食」も増加しています。大妻女子大学家政学部教授で管理栄養士・医学博士の川口美喜子氏は、高齢者の「孤食」や偏食は栄養不足の原因となり、さらには「フレイル(虚弱・老年症候群)」につながる可能性があると警告しています(『週刊朝日』2018年5月4-11日合併号)。
川口氏は、一人暮らしの老人が多く住む団地で、毎週食事会を開催しています。「週一度の“身体に優しい食事会”だけでは、1週間の健康を保つ栄養補給にはなりません。ただ、みんなと一緒に食べれば孤食やフレイル防止につながる。そう思って、食事会を始めました」と語っています。
「共食」がヒトを人間にした?
食事文化と比較文化が専門で、国立民族学博物館名誉教授で文化人類学者の石毛直道氏は、人類の食行動の文化的基盤を表現するために、「人間は料理する動物である」「人間は共食する動物である」という、2つのテーゼを掲げています(『食卓文明論』中央公論新社)。「孤食」や「食事の個人化」が増加する現代ですが、石毛氏は、人間以外の動物の食事は個体単位での完結が原則であるが、「“共食する動物”である人間の食事は、原則として、一人で食べるものではない<中略>そして、もっとも日常的な共食集団は家族である」と述べています。
さらに、「家族のかこむ食卓のない家庭が実現するとき、それは家族という制度が崩壊するときである」と警鐘を鳴らしています。そう考えると、「共食」に伴う家族単位の発生やコミュニティの連帯感の形成、文化の伝承や知識の継承などが、ヒトを人間にしたともいえるのかもしれません。
食事はもっとも身近で大切な生きるために欠かせない行為です。だからこそ手間や煩わしさもありますが、同時に誰にでも改善することや、よりよい形に変えていくことも可能なはずです。ライフスタイルを省みながらも、今よりもベターな食生活をめざして、「孤食」の弊害を意識し「共食」のよさを見直してみてはいかがでしょうか。
<参考文献・参考サイト>
・『崩食と放食』(NHK放送文化研究所世論調査部編、生活人新書)
・『家族の勝手でしょ!』(岩村暢子著、新潮文庫)
・『週刊朝日』(2018年5月4-11日合併号、朝日新聞出版)
・『食卓文明論』(石毛直道著、中央公論新社)
・電通報:孤食マーケティングのすすめ ~「食と孤独」を考える
https://dentsu-ho.com/articles/5812
・『崩食と放食』(NHK放送文化研究所世論調査部編、生活人新書)
・『家族の勝手でしょ!』(岩村暢子著、新潮文庫)
・『週刊朝日』(2018年5月4-11日合併号、朝日新聞出版)
・『食卓文明論』(石毛直道著、中央公論新社)
・電通報:孤食マーケティングのすすめ ~「食と孤独」を考える
https://dentsu-ho.com/articles/5812
人気の講義ランキングTOP20










