テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
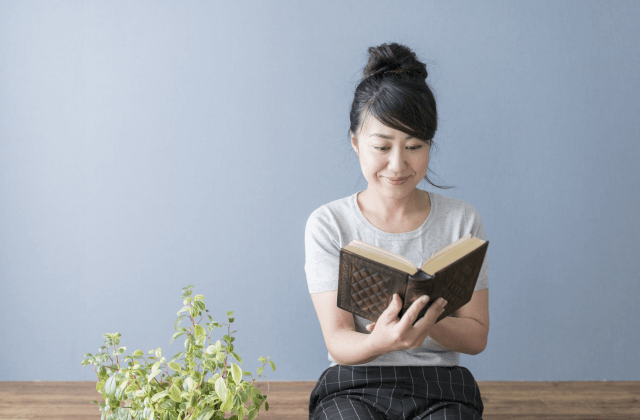
日本人の「読解力」は世界一ってホント?
「日本人の読解力は世界一」という意見がありますが、それは本当なのでしょうか。
この意見の背景には、2013年に公表された「PIAAC:ピアック(Programme for the International Assessment of Adult Competences)」の結果が潜んでいることが伺えます。
OECD加盟国を中心に、24ヵ国・地域(日・米・英・仏・独・韓・豪・加・蘭・露等)が参加し、2011年~2012年の期間に16歳~65歳までの約15万7000人の男女を対象に初めて実施され、2013年に結果が公表されました。日本では「国際成人力調査」として、結果がまとめられています(『OECD国際成人力調査(PIAAC)報告書』)。
このうち「読解力」スキルでは、「社会に参加し、自らの目標を達成し、自らの知識と可能性を発展させるために、書かれたテキストを理解し、評価し、利用し、これに取り組む能力」の測定を目的としています。具体的な設問では、ホテルなどにある電話のかけ方の説明を読んで指定された相手に電話をすることや、図書館の蔵書検索システムを使って指定された条件に合う本を選んだりすること、市民イベントの公式ホームページから開催者の電話番号を調べることなどが求められます。
ただし、設問の難易度が高いとはいえない問題での500点満点中の結果であり、裏を返せば作家の橘玲氏が述べているように、「日本人のおよそ3分の1は日本語が読めない」という結果でもあります(『もっと言ってはいけない』『週刊文春』)。
そしてこの結果は、全国2万5000人の中高生の基礎的読解力を調査し、3人に1人が問題文を読めないことを示して教育界はもとより社会に衝撃を与えた、数理論理学が専門で国立情報学研究所教授の新井紀子氏の調査結果とも合致しています(『AI vs.教科書が読めない子どもたち』)。
なお、「読解力」のOECD平均得点は273点で、2位から23位は以下の結果となっています。
2位 フィンランド:288点
3位 オランダ:284点
4位 オーストラリア:280点
5位 スウェーデン:279点
6位 ノルウェー:278点
7位 エストニア:276点
8位 ベルギー:275点
9位 チェコ:274点、
10位 スロバキア:274点
11位 カナダ:273点
12位 韓国:273点
13位 イギリス:272点
14位 デンマーク:271点
15位 ドイツ:270点
16位 アメリカ:270点
17位 オーストリア:269点
18位 キプロス:269点
19位 ポーランド:267点
20位 アイルランド:267点
21位 フランス:262点
22位 スペイン:252点
23位 イタリア:250点
(ロシアのデータは含まれていません)
このうち、OECD平均よりも統計的に有意に高い国は日本を含めて8ヵ国、反対にOECD平均よりも統計的に有意に低い国は10ヵ国になります。この結果を橘氏は、「先進国の成人の約半分(48.8%)はかんたんな文章が読めない」とまとめています。これらの成績を踏まえて日本人の「読解力」を考察すると、そもそも日本を含めて世界全体の「読解力」レベルが悲惨な状況であり、世界一といっても安易に喜んでいる場合ではないといえます。
では、「読解力」を向上させることはできるのでしょうか。また、なにか具体的な方策はあるのでしょうか。後者について新井氏は、「残念ながら、まだ見つかっていません」としながらも、リーディングスキルテストを活用して子どもともに教師も読解力を向上させている埼玉県戸田市の取り組みの実態などから、「読解力をつける道はあると思う」と述べています。
他方、個人だけの問題ではなく、社会全体における「読解力」の低下は、極端な考え方を助長させる危険性を秘めています。大規模な「読解力」のエビデンスが示されてきた今こそを、「読解力」の重要性を捉え直し、個々人が適切なフィードバックを始める好機としたいものです。
この意見の背景には、2013年に公表された「PIAAC:ピアック(Programme for the International Assessment of Adult Competences)」の結果が潜んでいることが伺えます。
「PIAAC」で測定された各国成人の「読解力」
「PIAAC」は、OECD(経済協力開発機構)によって、各国の成人の仕事や日常生活で必要とされる基本的で汎用的なスキルのうち、「読解力(Literacy)」「数的思考力(Numeracy)」「ITを活用した問題解決能力(Problem solving in technology-rich environments)」の3分野のスキルの習熟度を測定することを目的とした、国際比較調査です。OECD加盟国を中心に、24ヵ国・地域(日・米・英・仏・独・韓・豪・加・蘭・露等)が参加し、2011年~2012年の期間に16歳~65歳までの約15万7000人の男女を対象に初めて実施され、2013年に結果が公表されました。日本では「国際成人力調査」として、結果がまとめられています(『OECD国際成人力調査(PIAAC)報告書』)。
このうち「読解力」スキルでは、「社会に参加し、自らの目標を達成し、自らの知識と可能性を発展させるために、書かれたテキストを理解し、評価し、利用し、これに取り組む能力」の測定を目的としています。具体的な設問では、ホテルなどにある電話のかけ方の説明を読んで指定された相手に電話をすることや、図書館の蔵書検索システムを使って指定された条件に合う本を選んだりすること、市民イベントの公式ホームページから開催者の電話番号を調べることなどが求められます。
日本の「読解力」は世界一!しかし課題あり
日本の「読解力」の平均得点は296点で、下位に有意な差をつけての1位という結果となりました。また各国における習熟度レベル別の成人の分布においても、レベル1未満からレベル2の割合が参加国中最も少なく、逆にレベル3とレベル4の割合は最も多く、レベル5の割合は2以下が僅差の5位という結果でした(ちなみに日本は「数的思考力」も下位に有意な差をつけての1位で、平均得点は288点でした)。ただし、設問の難易度が高いとはいえない問題での500点満点中の結果であり、裏を返せば作家の橘玲氏が述べているように、「日本人のおよそ3分の1は日本語が読めない」という結果でもあります(『もっと言ってはいけない』『週刊文春』)。
そしてこの結果は、全国2万5000人の中高生の基礎的読解力を調査し、3人に1人が問題文を読めないことを示して教育界はもとより社会に衝撃を与えた、数理論理学が専門で国立情報学研究所教授の新井紀子氏の調査結果とも合致しています(『AI vs.教科書が読めない子どもたち』)。
なお、「読解力」のOECD平均得点は273点で、2位から23位は以下の結果となっています。
2位 フィンランド:288点
3位 オランダ:284点
4位 オーストラリア:280点
5位 スウェーデン:279点
6位 ノルウェー:278点
7位 エストニア:276点
8位 ベルギー:275点
9位 チェコ:274点、
10位 スロバキア:274点
11位 カナダ:273点
12位 韓国:273点
13位 イギリス:272点
14位 デンマーク:271点
15位 ドイツ:270点
16位 アメリカ:270点
17位 オーストリア:269点
18位 キプロス:269点
19位 ポーランド:267点
20位 アイルランド:267点
21位 フランス:262点
22位 スペイン:252点
23位 イタリア:250点
(ロシアのデータは含まれていません)
このうち、OECD平均よりも統計的に有意に高い国は日本を含めて8ヵ国、反対にOECD平均よりも統計的に有意に低い国は10ヵ国になります。この結果を橘氏は、「先進国の成人の約半分(48.8%)はかんたんな文章が読めない」とまとめています。これらの成績を踏まえて日本人の「読解力」を考察すると、そもそも日本を含めて世界全体の「読解力」レベルが悲惨な状況であり、世界一といっても安易に喜んでいる場合ではないといえます。
「読解力」を向上させることはできるのか?
「読解力」はあらゆる知的活動の基盤であり、私生活での幸福度や社会生活における貢献度などにも大きく関わってきます。特に、高度に情報化された知識社会である現代の先進国においては、職業スキルの基礎としても重要です。その大切な「読解力」が低いまたは欠落していることは大きな問題であり、手痛いハンデとなります。では、「読解力」を向上させることはできるのでしょうか。また、なにか具体的な方策はあるのでしょうか。後者について新井氏は、「残念ながら、まだ見つかっていません」としながらも、リーディングスキルテストを活用して子どもともに教師も読解力を向上させている埼玉県戸田市の取り組みの実態などから、「読解力をつける道はあると思う」と述べています。
他方、個人だけの問題ではなく、社会全体における「読解力」の低下は、極端な考え方を助長させる危険性を秘めています。大規模な「読解力」のエビデンスが示されてきた今こそを、「読解力」の重要性を捉え直し、個々人が適切なフィードバックを始める好機としたいものです。
<参考文献・参考サイト>
・「国際成人力調査」、『日本大百科全書(ニッポニカ)』(小学館)
・『OECD国際成人力調査(PIAAC)報告書』(国立教育政策研究所編、明石書店)
・『もっと言ってはいけない』(橘玲著、新潮新書)
・「言ってはいけない! 日本人の3分の1は日本語が読めない。」、『週刊文春』(2019年2月14日号、文藝春秋)
・『AI vs.教科書が読めない子どもたち』(新井紀子著、東洋経済新報社)
・国際成人力調査(PIAAC):国立教育政策研究所
http://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/div03-shogai-piaac-pamph.html
・国際成人力調査(PIAAC:ピアック):文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/data/Others/1287165.htm
・「ヘンタイよいこ」新井紀子は明日への希望を忘れない。 - ほぼ日刊イトイ新聞
https://www.1101.com/torobo_talk_arai/2018-05-18.html
・「国際成人力調査」、『日本大百科全書(ニッポニカ)』(小学館)
・『OECD国際成人力調査(PIAAC)報告書』(国立教育政策研究所編、明石書店)
・『もっと言ってはいけない』(橘玲著、新潮新書)
・「言ってはいけない! 日本人の3分の1は日本語が読めない。」、『週刊文春』(2019年2月14日号、文藝春秋)
・『AI vs.教科書が読めない子どもたち』(新井紀子著、東洋経済新報社)
・国際成人力調査(PIAAC):国立教育政策研究所
http://www.nier.go.jp/04_kenkyu_annai/div03-shogai-piaac-pamph.html
・国際成人力調査(PIAAC:ピアック):文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/data/Others/1287165.htm
・「ヘンタイよいこ」新井紀子は明日への希望を忘れない。 - ほぼ日刊イトイ新聞
https://www.1101.com/torobo_talk_arai/2018-05-18.html
人気の講義ランキングTOP20
ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ
テンミニッツ・アカデミー編集部










