テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
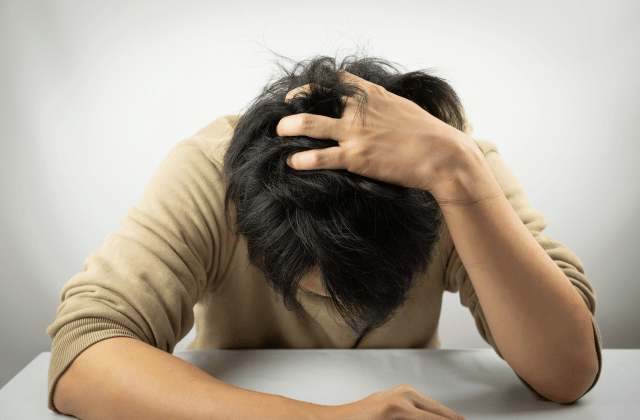
なぜ人はデマに騙されてしまうのか?
「中国の工場がストップするから紙製品が品薄になる」「特定の薬はウイルスを増殖させるから飲んではいけない」「納豆がコロナ予防に効く」…世の中が混乱すると真偽の定かではない情報があふれかえり、時にはデマ情報によって私たちの生活に大きな影響を与えてしまうことも少なくありません。
特にSNSが普及するようになってからは、個人が情報を拡散できるようになったため、正しい情報もデマ情報も区別されずに急激に広がるようになっています。情報があふれかえるこの時代、私たちがデマにだまされてしまうのはなぜなのでしょうか。2つのキーワードに分けて紹介していきましょう。
こうした非常時は特にデマ情報が発生しやすい状況になっています。しかし、私たちは情報を欲しがるあまり、精査しないうちに情報を鵜呑みにしてしまいがちになっているのです。その結果、「納豆がコロナ予防に効く」といったデマが広く拡散されてしまい、納豆が売り場からなくなる、という現象に発展しまうのです。
また、文章を読んで明らかにおかしいものであればだまされませんが、それらしいストーリーが組み立てられていると納得してしまうこともあります。「中国の工場がストップするから紙製品が品薄になる」というデマが広がりましたが、実際トイレットペーパーは国内での製造が多いので生産に影響はないというのが事実です。しかし、その事実を知っている人はあまりいなかったので、どこにもトイレットペーパーがないという大変な騒ぎになってしまったのです。
また、デマを見分けるコツは「ネットのデマ、嘘を嘘だと見抜く方法は?」でも紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。
特にSNSが普及するようになってからは、個人が情報を拡散できるようになったため、正しい情報もデマ情報も区別されずに急激に広がるようになっています。情報があふれかえるこの時代、私たちがデマにだまされてしまうのはなぜなのでしょうか。2つのキーワードに分けて紹介していきましょう。
分からないことへの「不安」
デマにだまされてしまう大きな原因のひとつが「不安」です。東日本大震災の発生や新型コロナウイルスの流行などで社会が混乱する事態に陥ると、少しでも多くの情報が欲しくなりますよね。そんな不安を払拭するためにネットで何か情報がないかと調べたり、SNSでリアルタイムの情報を追った経験がある人もいるのではないでしょうか。こうした非常時は特にデマ情報が発生しやすい状況になっています。しかし、私たちは情報を欲しがるあまり、精査しないうちに情報を鵜呑みにしてしまいがちになっているのです。その結果、「納豆がコロナ予防に効く」といったデマが広く拡散されてしまい、納豆が売り場からなくなる、という現象に発展しまうのです。
信じたいことを信じてしまう「脳のクセ」
私たち人間の脳は「信じたいものを信じる」というクセを持っています。Twitter(現X)を例にしてみると、何万件もリツイートされたり、いいねがついているツイートや、信頼する人がリツイートしているツイートは信憑性が生まれてきます。その情報が正しいかよりも、大多数が支持しているために、その情報を世間的に正しいものだと判断してしまうことがあるのです。また、文章を読んで明らかにおかしいものであればだまされませんが、それらしいストーリーが組み立てられていると納得してしまうこともあります。「中国の工場がストップするから紙製品が品薄になる」というデマが広がりましたが、実際トイレットペーパーは国内での製造が多いので生産に影響はないというのが事実です。しかし、その事実を知っている人はあまりいなかったので、どこにもトイレットペーパーがないという大変な騒ぎになってしまったのです。
善意から拡散されるデマ
非常時にこうしたデマが広がるのは、悪意ではなく「この情報は周りにも知らせないと」という善意からであることも厄介なポイントです。善意で行った情報のシェアが後々デマだとわかると、せっかくの善意が台無しになってしまうこともあります。自分が情報のシェアを行うときは、それが出所の確かな情報なのか、きちんと精査してから拡散することが大切です。また、デマを見分けるコツは「ネットのデマ、嘘を嘘だと見抜く方法は?」でも紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。
人気の講義ランキングTOP20










