テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
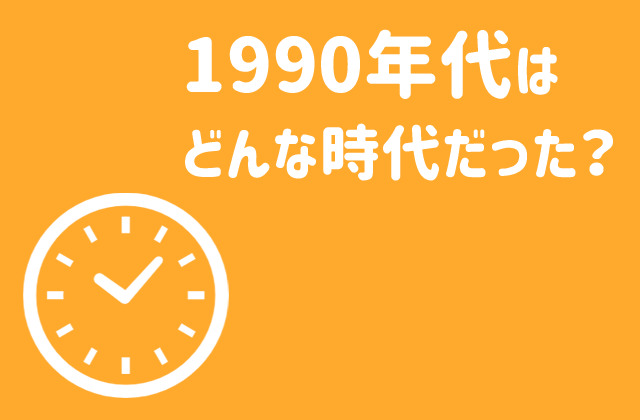
1990年代はどういう時代だったか振り返る
1990年代の日本とは、いったいどういう時代だったのでしょうか。今回は、記録や記憶に残る出来事や流行となった人物やフレーズなどを手がかりに、1990年代を振り返ってみたいと思います。
1991年はいよいよバブルが崩壊し、「失われた10年」の始まりの年となりました。ストレスによってメンタルヘルスの対象者が急増した一方で、東京芝浦に「ジュリアナ東京」が誕生し、角界では横綱千代の富士の引退と若貴フィーバーが起こります。世界では湾岸戦争が勃発し、ソ連が崩壊し、アウン・サン・スー・チー氏がノーベル平和賞を受賞する一方で、エコロジーがより広く意識されるようになり、国内でも「地球にやさしい」がキーワードとなりました。また、牛肉とオレンジの輸入自由化となり、雲仙・普賢岳で大規模な火砕流が発生するなど、財界や自然界でも変化が起こります。お笑いではチャーリー浜の「…じゃあ~りませんか」が流行り、「東京ラブストーリー」「101回目のプロポーズ」などのトレンディドラマが大ヒットしました。
PKO協力法の成立、ユーゴスラビア紛争など、平和維持への関心が高まった1992年。「生活大国構想」を掲げた宮澤喜一改造内閣発足しましたが、カード破産が増加し複合不況に陥るなど、経済状況には暗雲が立ち込めたままとなりました。しかしながら、バルセロナオリンピックでは水泳史上最年少の金メダリストに輝いた岩崎恭子氏の「いままで生きてきた中で一番幸せ」が流行語となり、日本人初の本格的宇宙飛行士・毛利衛氏の宇宙からの第一声「宇宙から見た地球に国境はありませんでした」や子どもたちとの「宇宙授業」が話題となるなど、明るいニュースもありました。100歳の双子姉妹「きんさんぎんさん」、ドラマ「ずっとあなたが好きだった」の冬彦さん、アニメ「クレヨンしんちゃん」などがブームとなったのも、東海道新幹線のぞみが運行開始し、第二土曜日が休校制となる学校週休2日制が始まったのも同年です。
皇太子殿下のご成婚に喜びがあふれた1993年。Jリーグが開幕し、レインボーブリッジが開通し、東京サミットが開催され、法隆寺や姫路城、屋久島や白神山地が日本で初めて世界遺産に登録されました。また、自民党からの離党者が新生党や新党さきがけが結成した新党ブーム、女性初の土井たか子衆議院議長就任といったマドンナ旋風など、政界にも新しい風が吹きました。しかし、冷夏に見舞われ米が大凶作となる「平成の米騒動」が起こり、「雇用なき成長」といわれる失業率の高さが課題となるなど、課題も目立ちました。世界では欧州連合(EU)が誕生し、国内ではコギャルがブームとなりました。
1994年はプロ野球オリックスのイチロー選手の活躍が際立ち、その波及効果が「イチロー効果」と呼ばれました。政界では自由民主党・日本社会党(現・社会民主党)・新党さきがけによる連立政権(自社さ連)による橋本龍太郎政権が誕生。不況下のなか、価格破壊、就職氷河期が進行する一方で、週40時間労働制実現など労基法改正が行われました。文化面の慶事としては、大江健三郎氏がノーベル文学賞を受賞。ドラマ「家なき子」の「同情するならカネをくれ」が「新語・流行語大賞」の大賞となりました。関西国際空港が開港し、松本サリン事件が発生したのもこの年です。
援助交際、ルーズソックス、チョベリバ、アムラー、たまごっちなど、女子高生文化が盛り上がった1996年。薬害エイズが顕在化し、病原性大腸菌O-157といった新たな感染症の恐怖が身近に迫った年でもありました。世界では原子力安全サミットが開催され、ペルー日本大使公邸人質事件が発生しました。また、アトランタオリンピックが開催され、女子マラソン銅メダルの有森裕子氏の「自分で自分をほめたい」が流行語となり、将棋棋士の羽生善治氏が史上初の七冠王となったのもこの年です。
1997年は、「日本版ビッグバン」と称される金融制度の大改革が行われ、郵政三事業の民営化論議が巻き起こり、消費税3%から5%へ引上げられ、北海道拓殖銀行や山一證券が経営破綻するなど、既存の枠組みに大きな亀裂が走りました。また、酒鬼薔薇聖斗事件が大きな社会問題となった年でもあります。国際的には香港返還やタイガー・ウッズの活躍などが話題となり、国内では『失楽園』がベストセラー、アニメ映画「もののけ姫」のヒット、漫画家・イラストレーターのみうらじゅん氏の「マイ・ブーム」ブームが起こりました。
「日本列島総不況」と嘆かれた1998年。「平成おじさん」「冷めたピザ」などと呼ばれた小渕恵三氏による内閣が発足し、孤独死が社会問題となり、金融機関に対する「モラル・ハザード」議論やイラクで発生した武装グループによる日本人人質事件発生による「自己責任」論が課題として取り上げられました。また、長野オリンピックが開催され、環境ホルモンに注目が集まり、お笑いコンビ「パイレーツ」の「だっちゅーの」が流行し、和歌山毒物カレー事件が発生し、明石海峡大橋が開通しました。夏の甲子園高校野球決勝戦で横浜高校の松坂大輔氏がノーヒットノーラン達成し、「ハマの大魔神」こと佐々木主浩投手が活躍した横浜ベイスターズが38年ぶりにリーグ優勝と日本一に輝いたのも同年です。
世紀末の1999年。国内では「iモード」がヒットし、「モー娘。」や「カリスマ」がブームとなり、「癒し」が求められました。また、自由民主党・自由党・公明党の自自公3党で成立した連立政権(自自公連立)が誕生し、周辺事態安全確保法や国旗・国歌法が課題となり、東海村臨界事故が発生し、学校・学級崩壊が危惧されました。池袋通り魔殺人事件・下関通り魔殺人事件・桶川ストーカー殺人事件・文京区幼女殺人事件・京都小学生殺害事件など相次いで凶悪事件が発生したのも同年です。一方、国際的には、単一通貨ユーロが導入され、ユーゴスラビアで和平案受諾がなされ、ロシアではプーチン新首相が誕生し、台湾中部ではM7・7の直下型地震が発生し、パキスタンで軍事クーデターが起こりました。また、NHK「おかあさんといっしょ」から生まれた「だんご3兄弟」がヒットし、乙武洋匡氏の『五体不満足』がベストセラーとなり、犬型ロボットAIBOが発売されました。
いかがでしたでしょうか。夢中になった出来事、すでになつかしいフレーズ、今では大切になっている思い出などありましたでしょうか。こうして流行のトピックスとともに駆け足で振り返ってみると、1990年代とは、既存の枠組みが機能不全を起こした激動の年代であったように思えます。日常の破壊、国家の崩壊、大企業の破綻、共同幻想の解体、安全神話の白紙化など、人々にまつわるハードとソフトのすべてにおいて、ミレニアムレベルの総決算が行われた時代であったように見えてきます。
1990年代前半を振り返る
バブル経済崩壊前年の1990年。国内では「ファジィ工学」を応用した家電製品が開発され、「オヤジギャル」やアニメ「ちびまる子ちゃん」が流行する一方、世界では東西ドイツ統一が行われ、ペルーで無名の日系2世のアルベルト・フジモリ氏が大統領に就任してフジモリ現象が起こるなど、今日的なグローバリズムが、皮膚感覚で拡大しはじめました。天皇陛下の即位の礼が行われ、大阪では「国際花と緑の博覧会(花博)」が開幕し、TBS記者の秋山豊寛氏が日本人初の宇宙飛行士として宇宙へと旅立ちました。1991年はいよいよバブルが崩壊し、「失われた10年」の始まりの年となりました。ストレスによってメンタルヘルスの対象者が急増した一方で、東京芝浦に「ジュリアナ東京」が誕生し、角界では横綱千代の富士の引退と若貴フィーバーが起こります。世界では湾岸戦争が勃発し、ソ連が崩壊し、アウン・サン・スー・チー氏がノーベル平和賞を受賞する一方で、エコロジーがより広く意識されるようになり、国内でも「地球にやさしい」がキーワードとなりました。また、牛肉とオレンジの輸入自由化となり、雲仙・普賢岳で大規模な火砕流が発生するなど、財界や自然界でも変化が起こります。お笑いではチャーリー浜の「…じゃあ~りませんか」が流行り、「東京ラブストーリー」「101回目のプロポーズ」などのトレンディドラマが大ヒットしました。
PKO協力法の成立、ユーゴスラビア紛争など、平和維持への関心が高まった1992年。「生活大国構想」を掲げた宮澤喜一改造内閣発足しましたが、カード破産が増加し複合不況に陥るなど、経済状況には暗雲が立ち込めたままとなりました。しかしながら、バルセロナオリンピックでは水泳史上最年少の金メダリストに輝いた岩崎恭子氏の「いままで生きてきた中で一番幸せ」が流行語となり、日本人初の本格的宇宙飛行士・毛利衛氏の宇宙からの第一声「宇宙から見た地球に国境はありませんでした」や子どもたちとの「宇宙授業」が話題となるなど、明るいニュースもありました。100歳の双子姉妹「きんさんぎんさん」、ドラマ「ずっとあなたが好きだった」の冬彦さん、アニメ「クレヨンしんちゃん」などがブームとなったのも、東海道新幹線のぞみが運行開始し、第二土曜日が休校制となる学校週休2日制が始まったのも同年です。
皇太子殿下のご成婚に喜びがあふれた1993年。Jリーグが開幕し、レインボーブリッジが開通し、東京サミットが開催され、法隆寺や姫路城、屋久島や白神山地が日本で初めて世界遺産に登録されました。また、自民党からの離党者が新生党や新党さきがけが結成した新党ブーム、女性初の土井たか子衆議院議長就任といったマドンナ旋風など、政界にも新しい風が吹きました。しかし、冷夏に見舞われ米が大凶作となる「平成の米騒動」が起こり、「雇用なき成長」といわれる失業率の高さが課題となるなど、課題も目立ちました。世界では欧州連合(EU)が誕生し、国内ではコギャルがブームとなりました。
1994年はプロ野球オリックスのイチロー選手の活躍が際立ち、その波及効果が「イチロー効果」と呼ばれました。政界では自由民主党・日本社会党(現・社会民主党)・新党さきがけによる連立政権(自社さ連)による橋本龍太郎政権が誕生。不況下のなか、価格破壊、就職氷河期が進行する一方で、週40時間労働制実現など労基法改正が行われました。文化面の慶事としては、大江健三郎氏がノーベル文学賞を受賞。ドラマ「家なき子」の「同情するならカネをくれ」が「新語・流行語大賞」の大賞となりました。関西国際空港が開港し、松本サリン事件が発生したのもこの年です。
1990年代後半を振り返る
阪神・淡路大震災が発生し、地下鉄サリン事件が引き起こされ、列島が震撼した1995年。この年から始まった「今年の漢字」にも「震」が選ばれ、安全神話の崩壊、ライフラインの確保などが課題となりました。また、金融破綻が相次ぎ、国民に大きな衝撃と影響を与えました。一方で、震災ボランティアが広まったことによる「ボランティア元年」、Windows95の発売などもあり「インターネット元年」とも呼ばれました。国際的にみると、世界貿易機関(WTO)が設立され、超円高ともなった同年、大リーグのドジャースに入団した野茂英雄投手が活躍し「NOM」ブームが巻き起こりました。援助交際、ルーズソックス、チョベリバ、アムラー、たまごっちなど、女子高生文化が盛り上がった1996年。薬害エイズが顕在化し、病原性大腸菌O-157といった新たな感染症の恐怖が身近に迫った年でもありました。世界では原子力安全サミットが開催され、ペルー日本大使公邸人質事件が発生しました。また、アトランタオリンピックが開催され、女子マラソン銅メダルの有森裕子氏の「自分で自分をほめたい」が流行語となり、将棋棋士の羽生善治氏が史上初の七冠王となったのもこの年です。
1997年は、「日本版ビッグバン」と称される金融制度の大改革が行われ、郵政三事業の民営化論議が巻き起こり、消費税3%から5%へ引上げられ、北海道拓殖銀行や山一證券が経営破綻するなど、既存の枠組みに大きな亀裂が走りました。また、酒鬼薔薇聖斗事件が大きな社会問題となった年でもあります。国際的には香港返還やタイガー・ウッズの活躍などが話題となり、国内では『失楽園』がベストセラー、アニメ映画「もののけ姫」のヒット、漫画家・イラストレーターのみうらじゅん氏の「マイ・ブーム」ブームが起こりました。
「日本列島総不況」と嘆かれた1998年。「平成おじさん」「冷めたピザ」などと呼ばれた小渕恵三氏による内閣が発足し、孤独死が社会問題となり、金融機関に対する「モラル・ハザード」議論やイラクで発生した武装グループによる日本人人質事件発生による「自己責任」論が課題として取り上げられました。また、長野オリンピックが開催され、環境ホルモンに注目が集まり、お笑いコンビ「パイレーツ」の「だっちゅーの」が流行し、和歌山毒物カレー事件が発生し、明石海峡大橋が開通しました。夏の甲子園高校野球決勝戦で横浜高校の松坂大輔氏がノーヒットノーラン達成し、「ハマの大魔神」こと佐々木主浩投手が活躍した横浜ベイスターズが38年ぶりにリーグ優勝と日本一に輝いたのも同年です。
世紀末の1999年。国内では「iモード」がヒットし、「モー娘。」や「カリスマ」がブームとなり、「癒し」が求められました。また、自由民主党・自由党・公明党の自自公3党で成立した連立政権(自自公連立)が誕生し、周辺事態安全確保法や国旗・国歌法が課題となり、東海村臨界事故が発生し、学校・学級崩壊が危惧されました。池袋通り魔殺人事件・下関通り魔殺人事件・桶川ストーカー殺人事件・文京区幼女殺人事件・京都小学生殺害事件など相次いで凶悪事件が発生したのも同年です。一方、国際的には、単一通貨ユーロが導入され、ユーゴスラビアで和平案受諾がなされ、ロシアではプーチン新首相が誕生し、台湾中部ではM7・7の直下型地震が発生し、パキスタンで軍事クーデターが起こりました。また、NHK「おかあさんといっしょ」から生まれた「だんご3兄弟」がヒットし、乙武洋匡氏の『五体不満足』がベストセラーとなり、犬型ロボットAIBOが発売されました。
いかがでしたでしょうか。夢中になった出来事、すでになつかしいフレーズ、今では大切になっている思い出などありましたでしょうか。こうして流行のトピックスとともに駆け足で振り返ってみると、1990年代とは、既存の枠組みが機能不全を起こした激動の年代であったように思えます。日常の破壊、国家の崩壊、大企業の破綻、共同幻想の解体、安全神話の白紙化など、人々にまつわるハードとソフトのすべてにおいて、ミレニアムレベルの総決算が行われた時代であったように見えてきます。
<参考文献・参考サイト>
・『誰でも読める 日本史年表』(吉川弘文館編集部編、吉川弘文館)
・2000年代の日本 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/2000%E5%B9%B4%E4%BB%A3%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC
・「現代用語の基礎知識」選 ユーキャン 新語・流行語大賞
https://www.jiyu.co.jp/singo/
・「新語・流行語大賞全記録」『現代用語の基礎知識 2019』(自由国民社)
・「ことばでたどる平成」『現代用語の基礎知識 2019』(自由国民社)
・「今年の漢字」一覧 | 事業・活動情報 | 公益財団法人 日本漢字能力検定協会
https://www.kanken.or.jp/project/edification/years_kanji/history.html
・『誰でも読める 日本史年表』(吉川弘文館編集部編、吉川弘文館)
・2000年代の日本 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/2000%E5%B9%B4%E4%BB%A3%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC
・「現代用語の基礎知識」選 ユーキャン 新語・流行語大賞
https://www.jiyu.co.jp/singo/
・「新語・流行語大賞全記録」『現代用語の基礎知識 2019』(自由国民社)
・「ことばでたどる平成」『現代用語の基礎知識 2019』(自由国民社)
・「今年の漢字」一覧 | 事業・活動情報 | 公益財団法人 日本漢字能力検定協会
https://www.kanken.or.jp/project/edification/years_kanji/history.html
人気の講義ランキングTOP20
ラマルクの進化論…使えば器官が発達し、それが子に伝わる
長谷川眞理子
島田晴雄先生の体験談から浮かびあがるアメリカと日本
テンミニッツ・アカデミー編集部
妻の両親と夫の両親で孫に与える影響が違うってホント?
長谷川眞理子










