テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
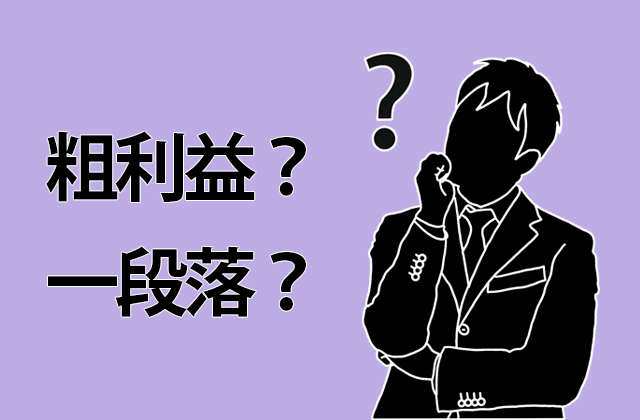
ビジネスシーンで読み間違えやすい漢字
音読みと訓読みだけでなく、熟語として独自の読みを持つ場合もある漢字。いくつもの読みのパターンがあるために、漢字を読み間違えてしまう場合や、さらには勘違いして間違えたまま漢字の読みを覚えてしまっている場合も多々あります。
そこで今回は、ビジネスシーンで読み間違えやすい漢字10選を取り上げてみました。あなたは全て読めるでしょうか?ぜひ振り返ってみてください。
1)そりえき
2)あらりえき
正解は2)あらりえき。「粗利益」は、売上額から生産原価を差し引いた額を示す、決算用語の一つで、「粗利(あらり)」「利幅(りはば)」ともいわれます。「粗」には、大ざっぱ、大まかといった意味があります。
第2選「発足」、読みは1)2)のどちらでしょう?
1)ほっそく
2)はっそく
正解は1)ほっそく。「発足」には、出発、出立などとともに、組織や機構、団体や会議などが設けられて活動し始めるといった意味があります。
第3選「相殺」、読みは1)2)のどちらでしょう?
1)そうさつ
2)そうさい
正解は2)そうさい。「相殺」は、互いに相手方に対して同種の債権を有する場合に、双方の債権を対当額だけ差し引いて消滅させることを、つまり、帳消しにすることを表します。「相殺」のおける「殺(さい)」は「減らす」を意味します。
第4選「凡例」、読みは1)2)のどちらでしょう?
1)はんれい
2)ぼんれい
正解は1)はんれい。「凡例」とは、ある書物や著述に関して、その編述の目的・方針・書中の約束事や使用法などを、巻頭に述べたもののことです。
第5選「代替」、読みは1)2)のどちらでしょう?
1)だいかえ
2)だいたい
正解は2)だいたい。「代替」は、他のもので代えること、それに見合う他のもので代えることを意味します。「だいかえ」は「だいたい」の重箱読みです。
※「重箱読み(じゅうばこよみ)」とは、漢字二字による語を、上の字を音、下の字を訓で読む読み方。⇔「湯桶読み(ゆとうよみ)」は、漢字二字による語の、上の字を訓で、下の字を音で読む読み方。
1)ひとだんらく
2)いちだんらく
正解は2)いちだんらく。「一段落」は、文章などの一つの段落、物事が一応かたづくこと、ひとくぎりを意味します。話し言葉では使われることも多い「ひとらんだく」ですが、正式には誤りです。
第7選「重複」、読みは1)2)のどちらでしょう?
1)ちょうふく
2)じゅうふく
正解は1)ちょうふく。「重複」は、同じ物事がいくたび重なること、重なり合うことを意味します。
第8選「貼付」、読みは1)2)のどちらでしょう?
1)ちょうふ
2)てんぷ
正解は1)ちょうふ。「貼付」は字義通り、貼り付けることを表します。メールの添附ファイルなどで「てんぷ」読みは慣用読みです。
第9選「言質」、読みは1)2)のどちらでしょう?
1)げんち
2)げんしち
正解は1)げんち。のちの証拠となる言葉やあとで証拠となる約束の言葉を意味する「言質」のうちの、「ち」は「質」の音の一つで、人質や抵当などの意に用います。「げんしつ」は誤読から生じた慣用読みです。
第10選「早急」、読みは1)2)のどちらでしょう?
1)さっきゅう
2)そうきゅう
正解1)さっきゅう。「早急」は、非常に急ぐことやきわめてさし迫っていること、急を要することを意味します。なお、「さっ」は「早」の慣用音です。
ただし、今回は二択で一方を正解としましたが、厳密にいえば言葉は変化していくもので、相手に伝わっていたりコミュニティ内で通用していたりすれば、絶対の間違いとはいえません。
例えば、正解解説中に示された「慣用読み(かんようよみ)」は、「慣用音」(呉音、漢音、唐音のいずれでもなく、日本で広く一般的に使われている漢字音)を用いた読み方を指し、「消耗」の「耗(こう)」を「もう」、「情緒」の「緒(しょ)」を「ちょ」、「運輸」の「輸(しゅ)」を「ゆ」と読むなどが挙げられます。つまり、言葉の変化、漢字の日本語化の一例といえます。
新語や流行語、音便化による変化など、時代や状況によって、漢字の読み方も変わっていきます。しかしながら、よりよい人間関係の構築において、正しく適切な言葉遣いは基本であり、またビジネスシーンにおいて、言葉の間違いや勘違いは、損害を出すおそれもあります。
適宜自身の言葉遣いを省みつつ正しい知識を学びなおしたり増やしたりすることも肝要でありながら、さらに加速度的に変わり続けるビジネスシーンに応じて、社会の変化を敏感に感じつつ、他者の言葉遣いに対する理解力と寛容さを深めることも、ますます必要となってきています。
そこで今回は、ビジネスシーンで読み間違えやすい漢字10選を取り上げてみました。あなたは全て読めるでしょうか?ぜひ振り返ってみてください。
ビジネスシーンで読み間違えやすい漢字・1~5選
第1選「粗利益」、読みは1)2)のどちらでしょう?1)そりえき
2)あらりえき
正解は2)あらりえき。「粗利益」は、売上額から生産原価を差し引いた額を示す、決算用語の一つで、「粗利(あらり)」「利幅(りはば)」ともいわれます。「粗」には、大ざっぱ、大まかといった意味があります。
第2選「発足」、読みは1)2)のどちらでしょう?
1)ほっそく
2)はっそく
正解は1)ほっそく。「発足」には、出発、出立などとともに、組織や機構、団体や会議などが設けられて活動し始めるといった意味があります。
第3選「相殺」、読みは1)2)のどちらでしょう?
1)そうさつ
2)そうさい
正解は2)そうさい。「相殺」は、互いに相手方に対して同種の債権を有する場合に、双方の債権を対当額だけ差し引いて消滅させることを、つまり、帳消しにすることを表します。「相殺」のおける「殺(さい)」は「減らす」を意味します。
第4選「凡例」、読みは1)2)のどちらでしょう?
1)はんれい
2)ぼんれい
正解は1)はんれい。「凡例」とは、ある書物や著述に関して、その編述の目的・方針・書中の約束事や使用法などを、巻頭に述べたもののことです。
第5選「代替」、読みは1)2)のどちらでしょう?
1)だいかえ
2)だいたい
正解は2)だいたい。「代替」は、他のもので代えること、それに見合う他のもので代えることを意味します。「だいかえ」は「だいたい」の重箱読みです。
※「重箱読み(じゅうばこよみ)」とは、漢字二字による語を、上の字を音、下の字を訓で読む読み方。⇔「湯桶読み(ゆとうよみ)」は、漢字二字による語の、上の字を訓で、下の字を音で読む読み方。
ビジネスシーンで読み間違えやすい漢字・6~10選
第6選「一段落」、読みは1)2)のどちらでしょう?1)ひとだんらく
2)いちだんらく
正解は2)いちだんらく。「一段落」は、文章などの一つの段落、物事が一応かたづくこと、ひとくぎりを意味します。話し言葉では使われることも多い「ひとらんだく」ですが、正式には誤りです。
第7選「重複」、読みは1)2)のどちらでしょう?
1)ちょうふく
2)じゅうふく
正解は1)ちょうふく。「重複」は、同じ物事がいくたび重なること、重なり合うことを意味します。
第8選「貼付」、読みは1)2)のどちらでしょう?
1)ちょうふ
2)てんぷ
正解は1)ちょうふ。「貼付」は字義通り、貼り付けることを表します。メールの添附ファイルなどで「てんぷ」読みは慣用読みです。
第9選「言質」、読みは1)2)のどちらでしょう?
1)げんち
2)げんしち
正解は1)げんち。のちの証拠となる言葉やあとで証拠となる約束の言葉を意味する「言質」のうちの、「ち」は「質」の音の一つで、人質や抵当などの意に用います。「げんしつ」は誤読から生じた慣用読みです。
第10選「早急」、読みは1)2)のどちらでしょう?
1)さっきゅう
2)そうきゅう
正解1)さっきゅう。「早急」は、非常に急ぐことやきわめてさし迫っていること、急を要することを意味します。なお、「さっ」は「早」の慣用音です。
読み間違いは…間違いではない!?しかし…
いかがでしょうか。ビジネスシーンで使われる漢字の振り返りはできたでしょうか。読み間違いや勘違いはなかったでしょうか。ただし、今回は二択で一方を正解としましたが、厳密にいえば言葉は変化していくもので、相手に伝わっていたりコミュニティ内で通用していたりすれば、絶対の間違いとはいえません。
例えば、正解解説中に示された「慣用読み(かんようよみ)」は、「慣用音」(呉音、漢音、唐音のいずれでもなく、日本で広く一般的に使われている漢字音)を用いた読み方を指し、「消耗」の「耗(こう)」を「もう」、「情緒」の「緒(しょ)」を「ちょ」、「運輸」の「輸(しゅ)」を「ゆ」と読むなどが挙げられます。つまり、言葉の変化、漢字の日本語化の一例といえます。
新語や流行語、音便化による変化など、時代や状況によって、漢字の読み方も変わっていきます。しかしながら、よりよい人間関係の構築において、正しく適切な言葉遣いは基本であり、またビジネスシーンにおいて、言葉の間違いや勘違いは、損害を出すおそれもあります。
適宜自身の言葉遣いを省みつつ正しい知識を学びなおしたり増やしたりすることも肝要でありながら、さらに加速度的に変わり続けるビジネスシーンに応じて、社会の変化を敏感に感じつつ、他者の言葉遣いに対する理解力と寛容さを深めることも、ますます必要となってきています。
<参考文献>
『日本国語大辞典』(小学館)
『日本大百科全書』(小学館)
『新選漢和辞典 Web版』(小学館)
『デジタル大辞泉』(小学館)
『社会人の日本語』(山本晴男著、クロスメディア・パブリッシング)
『日本国語大辞典』(小学館)
『日本大百科全書』(小学館)
『新選漢和辞典 Web版』(小学館)
『デジタル大辞泉』(小学館)
『社会人の日本語』(山本晴男著、クロスメディア・パブリッシング)
人気の講義ランキングTOP20
「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介
テンミニッツ・アカデミー編集部
科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか
長谷川眞理子










