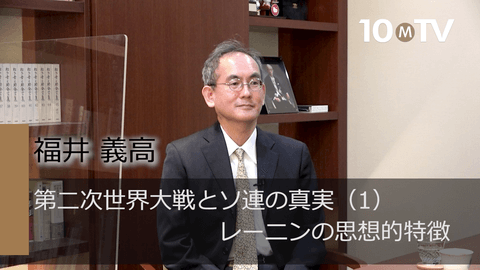テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
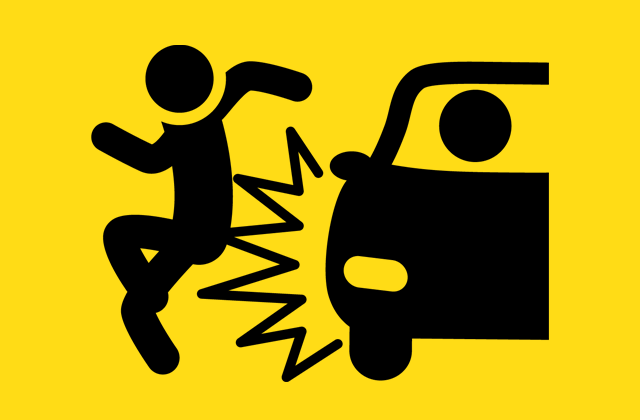
交通事故が起きやすい時間帯とは
信号無視やひき逃げなど、交通事故による悲しいニュースは後を絶ちません。実は自動車も歩行者も特に気をつけなければならない、事故が発生しやすい時間帯というのがあります。なぜ事故が起きやすくなるのか、そしてどんな事故防止策があるのかを、警察庁が発表している統計に基づき考察します。
警察庁が発表したデータによれば、平成28年から令和2年の5年間に起きた死亡事故の 16,786件中、日没時刻と重なる17時台から19時台に起きた死亡事故件数は3,210件と全体の19%を占めており、最も死亡事故が多いのは17時台の1,155件となっていました。
特にこの時間帯で多いのが「自動車と歩行者」の衝突事故で、「歩行者の横断中」が9割を占めるということです。この「自動車と歩行者」の事故件数は昼間の時間帯の約4倍となっています。
そのため、ドライバーは以下のことが求められます。
・薄暗くなる前(日没30分前)にライトを点灯する
・ハイビームを有効活用する
・昼間よりも速度を落とす
・ダイヤマーク(横断歩道前)やカーブでの減速を徹底
また、減速すると右側(車道側、対向車の陰)から渡ろうとする歩行者もいますので、そのような歩行者にも注意が必要です。
そして歩行者は、ドライバーにいち早く気づいてもらうため、以下の方法が有効です。
・反射材やライトを活用した安全グッズ(手首バンドやキーホルダー、靴など)を身につける
・夕暮れ時から夜間は明るい服を身につける
そして道を渡るときは右側だけでなく、左側から来る車にも十分注意しましょう。ただ、これらのことを行う何よりも前に「交通ルールと交通マナーを守ること」が大切です。
さきほど、主な死亡事故が「歩行者の横断中」が9割を占めたという話をしましたが、歩行者の横断中に起きた事故917件のうち、横断歩道付近、または横断歩道“以外”で発生した事故が704件となっており、横断歩道以外を横断中に起きた事故が8割以上を占めます。しかもそのうち、歩行者側の法令違反とみなされたのは約7割の489件でした。
以上のように、ほとんどの死亡事故は、歩行者側の法令違反により発生しているということになります。逆に言えば、歩行者側がきちんと法令を遵守すれば、たいていの事故は防げるのです。
とはいえ、どんなに気をつけていても不慮の事故は発生してしまうもの。ドライバーは歩行者心理をよく理解したうえで、より一層気を引き締めてハンドルを握りましょう。
あなた自身、そしてあなたの大切な人を守るためにも、もう一度自分の交通意識を振り返ってみてはいかがでしょうか。
もっとも死亡事故が多いのは17~19時の「薄暮時間帯」
一日の中で交通事故が起きやすい時間帯は「朝」そして「夕方から夜にかけて」とされています。中でももっとも死亡事故が起きやすいのが「夕方から夜にかけて」の時間帯です。警察庁では「薄暮(はくぼ)時間帯」と呼んでおり、日没前後1時間、17~19時台を指します。警察庁が発表したデータによれば、平成28年から令和2年の5年間に起きた死亡事故の 16,786件中、日没時刻と重なる17時台から19時台に起きた死亡事故件数は3,210件と全体の19%を占めており、最も死亡事故が多いのは17時台の1,155件となっていました。
特にこの時間帯で多いのが「自動車と歩行者」の衝突事故で、「歩行者の横断中」が9割を占めるということです。この「自動車と歩行者」の事故件数は昼間の時間帯の約4倍となっています。
なぜ「薄暮時間帯」で事故が起きやすい?
太陽が沈みだんだんと暗くなり始めるころは、人の目がまだ暗さに慣れておらず、視界が悪くなりやすい状態です。そのため、ドライバー、歩行者ともに相手の発見が遅れたり、距離や速度が判定しづらくなったりする状況に陥り、事故につながりやすくなると考えられています。運転者・歩行者がともに気をつけるべきこと
夕暮れ時や夜間は、歩行者よりもドライバーのほうが相手に気づきづらい傾向があります。そのため、ドライバーは以下のことが求められます。
・薄暗くなる前(日没30分前)にライトを点灯する
・ハイビームを有効活用する
・昼間よりも速度を落とす
・ダイヤマーク(横断歩道前)やカーブでの減速を徹底
また、減速すると右側(車道側、対向車の陰)から渡ろうとする歩行者もいますので、そのような歩行者にも注意が必要です。
そして歩行者は、ドライバーにいち早く気づいてもらうため、以下の方法が有効です。
・反射材やライトを活用した安全グッズ(手首バンドやキーホルダー、靴など)を身につける
・夕暮れ時から夜間は明るい服を身につける
そして道を渡るときは右側だけでなく、左側から来る車にも十分注意しましょう。ただ、これらのことを行う何よりも前に「交通ルールと交通マナーを守ること」が大切です。
さきほど、主な死亡事故が「歩行者の横断中」が9割を占めたという話をしましたが、歩行者の横断中に起きた事故917件のうち、横断歩道付近、または横断歩道“以外”で発生した事故が704件となっており、横断歩道以外を横断中に起きた事故が8割以上を占めます。しかもそのうち、歩行者側の法令違反とみなされたのは約7割の489件でした。
以上のように、ほとんどの死亡事故は、歩行者側の法令違反により発生しているということになります。逆に言えば、歩行者側がきちんと法令を遵守すれば、たいていの事故は防げるのです。
とはいえ、どんなに気をつけていても不慮の事故は発生してしまうもの。ドライバーは歩行者心理をよく理解したうえで、より一層気を引き締めてハンドルを握りましょう。
あなた自身、そしてあなたの大切な人を守るためにも、もう一度自分の交通意識を振り返ってみてはいかがでしょうか。
<参考サイト>
・薄暮時間帯における交通事故防止│警察庁HP
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/hakubo.html
・トピックス 薄暮時間帯の交通事故防止について│内閣府
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r01kou_haku/zenbun/genkyo/topics/topic_06.html
・夕暮れ時に歩行者が死亡する交通事故が多発!この時間帯の交通事故を防ぐには?│政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201711/1.html
・薄暮時間帯における交通事故防止│警察庁HP
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/hakubo.html
・トピックス 薄暮時間帯の交通事故防止について│内閣府
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r01kou_haku/zenbun/genkyo/topics/topic_06.html
・夕暮れ時に歩行者が死亡する交通事故が多発!この時間帯の交通事故を防ぐには?│政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201711/1.html
人気の講義ランキングTOP20